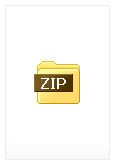連関資料 :: 教育
資料:11,677件
-
 教育原論 教育心理学 教育方法学 教育社会学セットレポート
教育原論 教育心理学 教育方法学 教育社会学セットレポート
- 佛教大学の「教育原論 教育心理学 教育方法学 教育社会学」のセットレポートです。学習の参考に使用ください。 レポートの評価 1.教育原論→A 2・教育心理学→B 3・教育方法学→B 4.教育社会学→A
- 佛教大学 通信 教育原論 教育心理学 教育方法学 教育社会学
 550 販売中 2013/01/08
550 販売中 2013/01/08- 閲覧(2,402)
-
 教育基本法の教育目的について学校における教育目的を設定せよ。
教育基本法の教育目的について学校における教育目的を設定せよ。
- わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。 『教育基本法』は、戦前の教育勅語の代わりとなる新しい教育の指針としてつくられた。教育を受ける機会の均等、男女共学などの理念を掲げた11条から成り立ち、「教育の憲法」と呼ばれている。 『教育基本法』の改正法案では、生涯学習、大学、家庭教育などの項目が新たに加わり、条文が18に増えている。しかし、与党の協議では、教育の目的に「愛国心」の言葉をどう盛り込むかが常に議論されてきた。 国を愛する心は人々の自然な気持ちであり、決して否定されるものではない。しかし、その愛し方は人によって違いがある。その結果、伝統と分化を育んできた我が国と故郷を愛するとの表現になり、「他国を尊重し」という言葉も付け加えられた。それでも心配されていることは、気に入らない相手を「愛国者ではない」と決めつける嫌な風潮があるからだろう。教育は国の将来につながる非常に大切な役割をもっている。その理念をうたう基本法は、憲法に準ずる重い法律だ。「国を愛すること」を教えるとはどういうことなのか。その影響はどのように及ぶか。さらに今の時期に基本法を変える必要はどこにあるのか。様々な疑問が浮かんでくる。 『教育基本法』では、前文が非常に有名である。「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」と書かれている。また、第1条には教育の目的として、「教育は、人格の完成をめざし、清和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と、されている。これに当たるべき学校は、学校独自の取り組みの狙いを自ら定める能力を持ち、それを実行できなければならないとされている。 教育の意図性は、何よりもまず、目的意識的であることを必要とする。目的とその実現方法とは、人間の作用・行為の過程における二つの基本的な側面であり、一つの対を形作っている。第二次世界大戦後の我が国において公布・施行された法規や文部科学省の文書においては、「目的」を上のレベルに置き、それを具体的に肉付けし、詳しく表現したものを「目標」と呼ぶようになって、その用語法が支配的になっている。 教育の目的は、教育を行う者がそれを成し遂げようとして、思い定めるだけではなく、それ以外の人々によっても考えられ、主張されるのが常である。なぜならば、それは教育が行われると共に、その行われる姿が見られ、見る人の思いを刺激するからである。 『教育基本法』にはいくつか問題点が挙げられている。それを三つに分けてみる。 (1)あまりに抽象的であって、具体的な内容に乏しく、また言葉が曖昧であって、文章が明確さを欠くような箇所が、散見される。 (2)内容的な諸事項相互間の関係が、はっきりとは伺われず、従って、全体としての構造がわからない箇所が、散見される。 (3)教育機関の実際の仕事を力強く導くのに必要な迫力に、欠けている。 これら三つの問題点をふまえて教育目標を設定しなければならないのである。また、『教育基本法』『学校指導要領』らは、学校一般を対象にして、その目的を述べているにすぎない。現在あ
- レポート 教育学 教育 基本法 目標
 550 販売中 2009/01/19
550 販売中 2009/01/19- 閲覧(2,957)
-
 教育課程論(幼稚園 初等教育)
教育課程論(幼稚園 初等教育)
- 幼稚園または、小学校の教育課程編成上留意すべきことについて述べなさい。 平成10年改訂幼稚園教育要領には「幼稚園においては、法令及びこの幼稚園教育要領の示すところに従い、創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即した適切な教育課程を編成するものとする」と冒頭に述べている。さらに続く(1)の中に「この場合においては、特に、自我の芽生え、他者との存在を意識し、自己を抑制しようとする気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ、入園から修了に至るまでの長期的な視野を持って」と書かれている。 したがって、幼稚園の目的、目標に向かって、教育を行う場である。さらに、個々の幼稚園が、目的や目標に向かって、どのような道筋を辿っていくかを明らかに捉え、幼児期に必要な教育内容を検討吟味して、行き当たりばったりではなく幼児期の発達に応じ、日々充実した生活が展開できるような、全体計画を必要とするのである。このように幼稚園における全教育期を見通した、教育内容の全体計画が教育課程である。 つまり教育課程の編成は、幼稚園教育の内容・方法、そして幼児期の発達と生活について十分に理解するとともに
- 環境 幼児 発達 子ども 地域 生活 教育課程 人間 幼稚園 幼児期
 550 販売中 2009/03/19
550 販売中 2009/03/19- 閲覧(4,553)
-
 教育の現場を見て〜教育実習を終えて〜
教育の現場を見て〜教育実習を終えて〜
- 教育実習は大きく分けて2つのタイプに分類される。教員免許の取得のために単位が必要で教育実習を行う人と、教員になりたくて教育実習を行う人だ。私は明らかに後者だった。しかし教育実習を行い、教師に幻滅した部分もある。すべての教師に対して言えるわけではないし、教師による犯罪もどこか別次元で、つまり自分の見回りでは起こりえないこととして考えていたのだが、感じたことを以下に書きたいと思う。 教育実習に行く前に私は家庭教師や塾の講師など、たくさんの経験をつんだ。いろいろなことがあったけれど、信頼できる人に相談したり、塾長などと直接話すことで問題に取り組んできた。それが過信になっていたのかもしれないが、教育にすばらしさを感じていた私は初心で初授業を迎えた。そして一番初めの授業は「学級活動」だった。学級担任の先生のところへいくと、なんと出張で休んでいるという。どうすればいいのかわからなかったが、隣のクラスの先生に「体育館で自由行動」といわれた。体育館に行ってみると生徒が思い思いの球技をしている。もしくは見学している。とりあえず私は生徒の輪の中に入ろうと思った。全校生徒の前では挨拶をしたが、クラスではまだ自己紹介もしていないのだ。昔やっていた部活の球技だったため、「先生うまい」と言われながら楽しく生徒と遊んだ。しばらくして輪に入れない生徒がいることに気づき、「疲れた」といってそちらに行った。監督の先生がいないことに不安はあったが自分の力がいきなり試され、自由にできたのでとても充実していた。
- レポート 教育実習 感想 体験
 550 販売中 2006/04/13
550 販売中 2006/04/13- 閲覧(2,873)
 1
1
-
 幼児教育と学校教育のあり方の違い
幼児教育と学校教育のあり方の違い
- 幼稚園教育は、「環境を通して行う教育」である。 環境とは、物的環境と人的環境、さらには幼児が接する自然や過ごす時間などをさす。物的環境は設備、遊具などのことで、人的環境は保育者や仲間の幼児たちのことである。保育者は、幼児の発達のために地域や園の状態をふまえた指導計画を立て、それに基づいて物的環境を用意しなければならない。そして自身も人的環境として幼児に接しなければならない。 そこで、どのように指導計画を立てるかが重要になってくる。幼稚園の目的は、学校教育法第77条に次のように定められている。
- レポート 教育学 幼児教育 学校教育 物的環境 人的環境
 550 販売中 2006/04/19
550 販売中 2006/04/19- 閲覧(5,574)
-
 宗教教育なしに道徳教育は可能か?
宗教教育なしに道徳教育は可能か?
- 「なぜ人殺しをしてはいけないか?」あるいは、「なぜいじめをしてはいけないか?」と生徒に聞かれたら、その生徒が納得できるように答えることができますか? …世の中の大切なことのほとんどが論理では説明できないのだと思います。 先日、友人のイギリス人と話していて、どの宗教を信仰しているかという話題になったとき、私を含む現代の日本人の多くは無宗教だ、と言ったら大変驚かれた。なぜなら、イギリスや他の多くの欧米諸国は宗教によって子供に道徳やモラルなどの規範を教えるからだ。だから彼は、宗教なしに道徳的な規範を教えることが可能なのか、と思ったのだろう。 同じような話が、新渡戸稲造の「武士道」の序文にもあったことを思い出した。「あなたがたの学校では、宗教教育というものがないのか?」と尋ねるベルギーの法学者ラブレーに対して、新渡戸が「ありません」と返事をすると、ラブレー氏は驚きのあまり突然歩みをとめ、「宗教がないとは、一体あなたがたはどのようにして子孫に道徳教育を授けるのですか」と繰り返した、といったことが書かれている。
- レポート 教育学 道徳 宗教 教育
 660 販売中 2006/11/04
660 販売中 2006/11/04- 閲覧(3,058)
-
 人権教育と同和教育の関連について論ぜよ
人権教育と同和教育の関連について論ぜよ
- 人権 同和 教師
 660 販売中 2009/11/27
660 販売中 2009/11/27- 閲覧(2,068)
-
 【教育方法学】教育思想の歴史
【教育方法学】教育思想の歴史
- 教育思想の歴史から、我が国の教育が近代化するときの教育理念とポストモダンにおける教育での理念とを比較してその違いを述べよ。 まず最初に教育思想の歴史の流れに合わせて、モダニズムとポストモダニズムの教育理念を概説することとしたい。 我が国の教育が近代化を見たのは、明治5年に国民教育制度が確立した時にさかのぼる。この時の教育理念は、国民に広く知識を教授することで、立身出世意欲を呼び覚まし、社会に資する人材を育てるというものであった。つまり、学習することと、社会的な達成との間に、合理的な結合が見られたのである。 そうした理念に基づき、学校においては、いかに効率的に知識を与えるかが至上命題となり、効率性重視の教育がなされた。具体的には、読み書き算数の初歩的な技能や実用的な知識の教授がなされた。そして、時が進むにつれ、その体制は一律、中央集権的なものとなり、学校制度は巨大な国家的教育機関となった。 しかし、社会状況が変化することで、学校に求められる役割も次第に変化していった。人々の価値観は多様化し、一元的な教育目標に向かって教育を行うといったことは、人々の教育理念の対立と混乱を誘発すること
- 教育 教授法
 550 販売中 2009/10/01
550 販売中 2009/10/01- 閲覧(2,755)
-
 教育行財政(教育行政の基本原理について)
教育行財政(教育行政の基本原理について)
- 教育行政の基本原理について述べよ。 今日わが国では、地方教育行政において、変化が激しい環境のせいか特色がそれぞれにある。そんななかで学校現場では、学校の自主性の確立が最重要課題の一~ 教育委員会の事務局としては、教育行政や学校運営を担当するにあたって法律に精通するだけではなく、教育行政の大きな流れを把握し、自ら分析し教~ ~教育行政の基本原理を概観してみるために概説書の内容を読んでみると、基本原理の第一原理は、「法律主義」であり、第二原理では「地方自治」「専門性」「自主性」の三つが肩を並べている。このような状態を見ると、教育行政の基本原理としては、~地方分権主義が最もポピュラーであるが、最も重点が置かれている原理は、教育行政の法律主義だということになる。 教育行政の基本原理の中で、第一、第二原理に注目が~
- 憲法 日本 行政 宗教 法律 学校 教育行政 政治 原理 指導 教育行財政 東京福祉大学 地方自治 自主性
 550 販売中 2009/05/28
550 販売中 2009/05/28- 閲覧(3,595)
-
 教育課程が学校の教育に対してはたしている機能
教育課程が学校の教育に対してはたしている機能
- 教育課程の定義を明らかにした上で、教育課程が学校の教育に対してどのような機能をはたしているのか。 まず教育課程の定義とは何か。様々な解釈があるが、教育課程とは教育上の目的を達成するための教育内容に関する計画であることは各解釈に共通している。そして、「いついつまでに、これくらいのことをできるようにする」などと、順序や枠組を決める形式的側面と、児童の実態を調査し、理解できているかなどの内容的側面の二つが関連しあって教育課程が作られている。教育課程の定義とは、教育の目的を効果的に達成するために、教育的に価値の認められる教育内容を、時間との関係で学習者の状態に対応し系統的に編成した教育の計画である。
- レポート 教育学 教育課程 学校 教育 進路指導
 550 販売中 2007/06/22
550 販売中 2007/06/22- 閲覧(2,139)