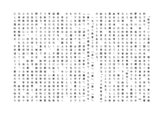連関資料 :: 教育
資料:11,675件
-
 道徳教育の研究 人権(同和)教育レポートセット(人権(同和)教育はC評価です)
道徳教育の研究 人権(同和)教育レポートセット(人権(同和)教育はC評価です)
- <道徳教育の研究> 『「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ』 1996年7月に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、これまでの戦後教育を振り返りつつ、今後の教育の基本的枠組みを提示した。そこで子どもたちを取り巻く現状において、社会の変化や地域・家庭の状況の変化に伴い「ゆとりのない生活」「社会性の不足や倫理感の問題」「自立の遅れ」を指摘し、学校生活においても「いじめ」「登校拒否」「自殺」など憂慮すべき状態が発生していることを指摘した。よって、このような事態に対処するために従来の学校教育の方針である「知識偏重の教育」から脱却し、新たな教育方針を提示する必要があった。そこで新たに提示されたのが生徒児童における「生きる力」の育成である。 中教審第一次答申によると、「生きる力」の育成には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」といった3要素をバランス良く育成することが欠かせないとある。ここでいう「確かな学力」とは「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」のことを指し、「豊かな人間性」とは「自らを律しつつ、他人とともに協調
- 生きる力 道徳教育 道徳教育の研究 人権(同和)教育 同和教育 佛教大学 通信教育 A評価
 550 販売中 2009/04/08
550 販売中 2009/04/08- 閲覧(2,741)
-
 学校での道徳教育はどのような教育目的をもって行われているのか。
学校での道徳教育はどのような教育目的をもって行われているのか。
- 「小学校学習指導要領・道徳編」が述べている目標は平成10年改訂学習指導要領「第1章・総則」第1の2に示されている。さらに、学習指導要領「第3章・道徳」の第1において、「学校生活全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うことにする。」と述べられている。 この道徳教育の目標は、学校における全体的な道徳の時間も、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間などの指導を通じて行う道徳教育も、常にこの目標の達成を目指して行われなければならない。 このような従来の方針に加えて、さらに、学校が家庭や地域社会と連携して、ボランティア活動や自然体験学習などを通じて道徳性が育成されなければなら
- 道徳教育 レポート 創価大学
 550 販売中 2008/04/23
550 販売中 2008/04/23- 閲覧(2,535)
-
 教育学概論(ヘルバルトの道徳的教育)
教育学概論(ヘルバルトの道徳的教育)
- スクーリングの事前課題で「ヘルバルトの道徳的教育」についてのレポートです。
- 玉川大学 通信教育 教育学概論 ヘルバルト 道徳的教育 スクーリングレポート
 550 販売中 2024/01/04
550 販売中 2024/01/04- 閲覧(603)
-
 ペスタロッチーの教育学・教育言論・佛大通信
ペスタロッチーの教育学・教育言論・佛大通信
- 教育言論 教育学
 550 販売中 2011/06/17
550 販売中 2011/06/17- 閲覧(1,612)
-
 全人教育における自然尊重の教育的意義
全人教育における自然尊重の教育的意義
- 「自然」という言葉には、様々な意味がある。実に多義的であり、それが人間の本来あるべき姿、何からも影響されない真の姿としての内的自然を意味する場合や、山、野原、川、海などの美しい地球環境そのものとしての外的自然を意味する場合がある。その中でも、小原國芳のいう、全人教育における自然尊重の「自然」とは、今述べた後者の外的自然の方を意味する。そして自然尊重の教育とは、次のような考え方に基づく。雄大な自然はそれ自体が偉大な教育をしてくれる存在であり、またこの貴重な自然環境を私たちが守らなければならないことを教えることも、また大切な教育だということである。この自然尊重の教育は、小原國芳の掲げる「12の教育信条」の一つとしても含まれている。 一方「全人教育」とは、「真」、「善」、「美」、「聖」、「健」、「富」の、6つの価値の創造にあり、それらはすなわち、「学問」、「道徳」、「芸術」、「宗教」、「健康」、「生活」の6方面の人間文化を調和的に豊かに形成することをいうのである。従って、全人教育における自然尊重の教育でも、これらの価値を創造することを目的とし、それがどのような方法によるものかを述べていくこと
- レポート 教育学 自然尊重 宗教教教育 道徳教育 学問教育 芸術教育
 550 販売中 2007/10/18
550 販売中 2007/10/18- 閲覧(3,005)
-
 教育原理設題1~教育に関する今日的課題~
教育原理設題1~教育に関する今日的課題~
- 令和2年度の豊岡短期大学通信課程の『教育原理』のレポート設題1です。 教育に関する今日的課題を選ぶということで、小1プロブレムについて選択し、自らの意見もまとめています。 テキストや参考書をまとめる系のものは普通は簡単(例えば教育心理学の物とか)なのですが、この設題に関してはテキストの内容がどうしても薄いため、複数の参考書やサイトからまとめなければならず、難易度は普通といったところでしょうか。 一発合格ですが、改善点はあります。 丸写しはトラブルの元となりますので、お控えください。
- 通信 豊岡 豊岡短期大学 教育 教育原理 今日的課題 小1プロブレム 令和2年度
 770 販売中 2020/06/03
770 販売中 2020/06/03- 閲覧(5,844)
-
 教育情報機器演習「情報教育の内容と方法について」
教育情報機器演習「情報教育の内容と方法について」
- 「情報教育の内容と方法について」 現在、情報化社会が進み、いたるところに情報機器が普及している。また、情報機器を使いこなせることが当り前となり、学校で情報教育を行うことが求められている。そこで、普通教科「情報」の目標を理解するには、小学校、中学校、高等学校を通した情報教育全体の目標の、「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する態度」を理解しておく必要がある。 では、普通教科「情報」における、情報A、情報B、情報Cについて述べていきたい。 この3科目のいずれも、「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する態度」の3つを育成できるように構成して
 550 販売中 2009/01/28
550 販売中 2009/01/28- 閲覧(1,095)