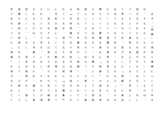連関資料 :: 課題2
資料:1,469件
-
 聖徳大学 教育課程論 第2課題
聖徳大学 教育課程論 第2課題
- 教育課程論 第2課題 『A判定』 学習指導書の各章に記載されている【演習例題】の中からひとつを選んでレポートしてください。その際、選んだ章と例題の番号と例題名も書いてください。 参考文献:斉藤新冶『教育課程論』 (聖徳大学通信教育部) 第Ⅰ章 演習例題 (2)「総合的な学習の時間」とイギリス教育改革の関連について説明しなさい。 1967年イギリスで「プラウデン報告書」が公刊されると、世界中からイギリスの初等学校における児童中心主義への関心が高まった。
- 教育課程論 聖徳大学 レポート
 550 販売中 2012/08/08
550 販売中 2012/08/08- 閲覧(3,873)
-
 教職課程 第二課題第一設題
教職課程 第二課題第一設題
- 第二課題 第一設題 第Ⅱ章 演習例題(2) 学習指導要領の法的拘束力と専門職としての教師の自由について論述せよ。 学習指導要領は1945年(第二次世界大戦で日本が敗戦した)以降に、議会において審議、採択された法律として成立した。教育に関する法律によってその法的拘束力を持つものと解釈されている。わが国の義務教育学校での教育課程は学校教育法により定められた学校で行われ、文部科学省の学習指導要領に基づいて計画されていなければならない原則がある。学習指導要領では「各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童(生徒)の人間としての調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童(生徒
- 小学校 学校 宗教 教師 学習指導要領 道徳 法律 科学 教育課程 学習
 550 販売中 2009/09/30
550 販売中 2009/09/30- 閲覧(1,534)
-
 聖徳大学 教育基礎論 第2課題
聖徳大学 教育基礎論 第2課題
- 聖徳大学 教育基礎論 第1課題 「A判定」 参考文献:『学校経営の基礎・基本』 牧 昌見 (教育開発研究所) 『教育経営』 白石祐編 (協同出版) テーマⅦの「学習課題」の1を選ぶ モラールとは学校の教職員が、その成員であることに誇りを持って結束し、学校の教育目標及び、分掌校務組織の目的の達成に向かって積極的に努力しようとする感情ないし態度である。
- 教育基礎論 聖徳大学 レポート
 550 販売中 2012/08/08
550 販売中 2012/08/08- 閲覧(2,826)
-
 NPO論Ⅱ 第2課題 評価S
NPO論Ⅱ 第2課題 評価S
- ・課題 学習指導書の第6回講義から出題する。日本における企業の社会的責任の隆起を時代の流れに沿って、5段階で論じなさい。 ・講評 出題に対する答えの説明が明快になされています。 ・参考文献 『NPO論Ⅰ・Ⅱ 学習指導書』 羽生和夫 聖徳大学通信教育部 2008.4.1 『NPO基礎講座(新版)』 山岡義典 ㈱ぎょうせい 2008.7.30
- 聖徳 通信
 550 販売中 2014/02/10
550 販売中 2014/02/10- 閲覧(1,744)
-
 聖徳 通信 ストレス心理学 第2課題
聖徳 通信 ストレス心理学 第2課題
- 【評価】A 合格レポート 文末に参考文献を記載してあります。 (書名、著者・編者名、出版社名、発行年月日、全て詳しく記載) 課題名: 2つの設問とも答えなさい。 (各800字程度、本文の書き始めに1、2を明記すること) 1.ストレスとソーシャル・スキルおよびソーシャル・サポートとの関連についてまとめなさい。 2.ストレスと心身症の関連についてまとめなさい。
- 聖徳 通信 ストレス心理学
 660 販売中 2018/03/16
660 販売中 2018/03/16- 閲覧(2,573)