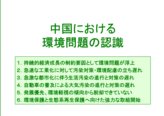連関資料 :: 問題
資料:1,331件
-
 日本経済の問題点
日本経済の問題点
- 日本経済の問題点 フリーターが及ぼす日本経済への影響 はじめに 景気回復を受けて、雇用環境が改善されつつある。しかし、その一方で、フリーターでいる期間が長く、そこから抜け出せずにそのままフリーターであり続ける者も多く、雇用改善の影で二極化が進行している。フリーターはいまや400万人に及び、その職業訓練の困難や、社会保障などの待遇面、フリーター経験者の正社員化の困難などのフリーター自身の問題や、日本経済への悪影響が危惧されている。またこれと同じくして、深刻な問題が起こっている。それはニートの増加である。52万人(厚生労働省、2003)と推計されるニートは、学校を卒業した後、フリーターのようなアルバイトすらもせず、専門学校等で職業訓練も行わずにいる状態の人を指し、そのような人々が若者を中心に増加している。 フリーターの多くは、専門知識をあまり必要としない単純作業に従事しているか、失業中であり、ニートは働く意思がない者とされている。このため、平均的にみると所得の低いフリーターとニートは、納める税金も、支払う保険料も、消費も、
- 日本経済 フリーター レポート 雇用問題 ニート 雇用環境 正社員 アルバイト
 770 販売中 2009/01/02
770 販売中 2009/01/02- 閲覧(5,523)
-
 中国における 環境問題の認識
中国における 環境問題の認識
- 中国における 環境問題の認識 1.持続的経済成長の制約要因として環境問題が浮上 2.急速な工業化に対して汚染対策・環境配慮の立ち遅れ 3.急激な都市化に伴う生活汚染の進行と対策の遅れ 4.自動車の普及による大気汚染の進行と対策の遅れ 5.発展優先、環境軽視の傾向から脱却できていない 6.環境保護と生態系再生保護へ向けた強力な取組開始 中国の環境問題の現状 1.環境保護の全体状況 (中国・国家環境保護総局の資料より) 中国における都市化の進展 都 市 数:2004 年にて661都市。都市面積は全国土のわずか6%を占める 都 市 人 口:2004 年にて5.24億人,全人口の41.7% 都市人口比率:1993 年:28%、2004 年41.7%11年で13.7%の増加 都市は人類社会の政治・経済・文化・科学と教育の中心であり、経済活動と人口密度が 高く、巨大な資源と環境の圧力に直面している。 2004年における都市の比率 6% 41.7% 64% 86%86% 65.5% 86% 64% 6% 41.7% 65.5% 中国の都市の発展と環境問題 都市GDP成長率 •都市人口の急激な膨張、
- 環境 中国 問題
 全体公開 2009/04/16
全体公開 2009/04/16- 閲覧(3,978)
-
 スペイン語問題文集
スペイン語問題文集
- 復習テスト14 次の質問に、カッコ内の語と必要ならば代名詞を使って答えなさい。 Puedes quitarme el abrigo? (si) Me llamas por telefono?(si) Usted me da un te con limon?(si) Puedes esperarme un momento?(no) A mis abuelos les abre la puerta usted?(si) Me traduces los documentos en japones?(si) Que les ensena a los estudiantes usted ?(un video) Ves la tele hoy?(no) Piensas comprar un regalo a juan?(si) Que me recomienda usted?(el bife al caballo) 復習テスト15 次の質問に、カッコ内の語と必要ならば代名詞を使って答えなさい。 Usted puede traerme un te con leche? (si) Me llamas
- スペイン 問題
 1,100 販売中 2008/08/03
1,100 販売中 2008/08/03- 閲覧(1,455)
-
 【教職】問題行動とその指導
【教職】問題行動とその指導
- 第1節 問題行動の意味 1)用語の曖昧さ 今日、情報や刺激の氾濫・価値観の混乱・家庭や地域社会の教育慣行の変化などに伴い、社会状況は変化し、同時に子供達の示す行動の問題性や危険性が深まり、多様化してきた。こうした状況の中、子供達の問題行動への関心が高まっている。 ●留意点● 「問題行動」の意味することが曖昧で多義的であるが故に、問題視する人間の考え・判断の基準に大きな幅がある。例)発達上必要な反抗期でさえ、問題行動に思えてしまう。 よって、親や教師の手を焼かせる子供の行動を全て問題行動とみなす事は出来ない。 また、教育現場で使う問題行動の用語は表面的であるということからもそういえるだろう。医学的疾病の名称とは違い、問題行動の対象は非常に幅広く複雑で、単純な定義や図式化を拒むものであるということを忘れてはならない。 2)問題行動の複雑さと多様化――問題行動のパターン ?危険信号のサインである問題行動 ある子供の行動が、さらなる深刻な問題行動を引き起こす前兆のサインとなるパターン。 我々に理解と援助を求めて発信されている。 ?より深刻な問題への発展を防ぐ、問題行動 ある問題行動により、ストレスや内に溜まるものが発散され、さらなる重大な問題行動に発展していく事を防ぐことパターン。その場合、表面的な行動や状態だけの安易な解消は返って困難な事態を導く事があるので、注意する。 ?我々に向けられたサインである問題行動 その問題行動が、親や教師の誤った対応や姿勢に対する抵抗や警告として発されているパターン。この場合、我々大人がそれまでの姿勢を変えることなく接し続けると、子供の内面世界にまで悪影響を及ぼすことがある。 ●第1節・まとめ● 問題行動の意味も、その言葉が指し示そうとする子供達の行動そのものの意味も非常に複雑で多様である。
- 論文 教育・心理学 教職 生徒指導 登校拒否 思春期 問題行動
 770 販売中 2005/12/03
770 販売中 2005/12/03- 閲覧(2,830)
-
 文化財保護の諸問題
文化財保護の諸問題
- ? 文化財とはなにか。そして文化財保護はされるべきなのか。 一言で文化財と言っても様々な文化財がある。有形文化財や無形文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群。それを更に詳しく分類すると、建造物、絵画、彫刻、工芸品、考古資料、歴史資料、音楽、工業技術、無形民俗文化財に用いられる家具、器具、衣服、進行年中行事の風俗習慣、貝塚、古墳、庭園、動物、植物、地質鉱物…等、日頃よく耳にするものもたくさんある。では、現在私が飼っている犬や使っている机や椅子、着ているユニクロの服、よく聞くCD等も文化財として存在するのか。答えは「NO」です。なぜかというと、それらには歴史上の価値が認められないからである。広辞苑を開けて文化財という語句を調べてみた。すると、「文化価値の客観的所産としての諸事象または諸事物で文化価値を有するもの…」と載っていた。少し硬い言い方なので私なりに言い換えると、文化財とは、私達人間がこの地球上に生まれて以来、長い年月をかけて創り上げられ、守られ、伝えられてきた歴史上の財産のことである。そして一度失ってしまうと二度とよみがえらないもの。これが文化財だと私は思う。 では、その歴史上の財産である文化財は保護されるべきなのか。これには保護する派という人と保護しない派という人の二つの意見があると思う。先に私の意見を述べておくと、どちらかと言えば私は保護する派の人間であるし、保護されるべきだと思う。 しかしそうは思わない人間もいるはずである。その後者の意見として考えられるのは、文化財などなくても生活には何の支障もないだとか、文化財があるせいで地域開発の妨げになるだとか、日本に関して言えば、ただでさえ人口の割に土地が狭くて道路も狭く交通量も多い国なのに、文化財があるせいで道路が広げられないから文化財など無くなってしまえばいいと考える人もいるでしょう。
- レポート 史学 文化財 世界遺産 保護制度
 550 販売中 2005/12/13
550 販売中 2005/12/13- 閲覧(3,640)
-
 少子・高齢化問題
少子・高齢化問題
- 政府がまとめた人口動態統計で、日本は2005年、出生数が死亡数を下回るという「自然減」となることが分かった。2006年の1億2774万人をピークに2050年には約1億人になるといわれ「人口減少社会」へとなりつつある。幕末・明治から大正、昭和、そして今の平成を向かえ人口が増えることを前提として作られてきた制度・組織・経営・生活スタイルが今、人口減少時代の到来に直面してその転換を迫られてきている。この少子高齢化、人口減少による社会面、経済面の問題点とは何か。地方自治体への影響、そして対策について考えていきたいと思う。 (1) 少子化 「*合計特殊出生率」が平成15年には1.29人となった。2人の男女で1.3人しか生まないということになる。人口を維持していくには合計特殊出生率が2.08以上にならなければならない。昭和30〜40年代は2.0〜2.2人前後で安定し昭和50年代以降に急激に低下し今の1.29という数字になっている。このままでは日本民族はどんどん減少していくことになり、大げさにいったら日本民族存続の危機である。 この理由としては女性の高学歴化・就職率の向上、価値観の変化、経済状況などが考えられ、他に理由としては数字として分かりやすいのが「晩婚化」つまり遅くなった結婚に1つの原因がある。94年の平均初婚年齢が妻26.2歳、夫28.5歳であるが、妻の年齢は一貫して高くなってきており晩婚化の傾向は進んできている。それとともに「非婚化」つまり結婚しない女性の人が増えたこともあり、たとえば女性の未婚率は30〜34歳では、70年から90年の20年間で7.7%から13.9%に大きく上昇している。理由としてはやはり昔と今の環境や価値観の変化や経済状況などから結婚しない女性や結婚しても1人、2人で子供は十分という考えが多いのであろう。
- レポート 社会学 少子化 高齢化 少子高齢化
 550 販売中 2007/01/31
550 販売中 2007/01/31- 閲覧(18,838)
-
 中国の変身におけるエネルギー問題
中国の変身におけるエネルギー問題
- 中国の変身におけるエネルギー問題 中国の古典文学A 1ページ 36行×40字=1440字 中国はここ数年において急激な変化を遂げている。まず政治の面では、2002年2月の党大会、2003年3月の全国人民代表大会(全人代)という大きな会議を経て、党首脳部と国家人事が大きく変動し、党・政府とも新しい体制が発足した。対外的には、2001年12月に、WTO(世界貿易機関)に加盟し、同時期に2008年の北京オリンピックの開催が決定した。さらに2002年12月には、2010年の上海万国博覧会も決定した。経済の面でも、世界的な不況をよそに中国の高度成長は続き、二つの国際的イベント、オリンピックと万博を控えて、今後さらに成長が期待される。 産業において世界では、IT革命の時代に突入し、携帯電話、電子商取引、インターネットなどの普及が経済・社会、人々の生活を激変させている。中国においても例外ではないどころか
- レポート 国際関係学 中国 エネルギー 中国の成長
 550 販売中 2007/07/22
550 販売中 2007/07/22- 閲覧(1,439)
-
 還元論の問題点について
還元論の問題点について
- 「還元論の問題点について」 還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。 私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。 そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われることは自然なことであり、その上位者(強者)が群の統制をとることとなる。そして、生物が同種であっても群同士で争うことを考えれば、群全体の目的は群そのもの、または群を支配する上位者(上位者の子孫を含む)の存続ということになるのではないだろうか。この群(上位者)の存続のためには、群内の下位者(弱者)の生命が疎かにされることも当然に起こりえよう。つまり、個の生命よりも群自体が重く見られることとなる。しかし、人(人に限らず生物)は本能的に生命に対する畏怖の念を持っている。ここで、個としての存在と群を成す存在としての間に矛盾が生じることとなる。一般の群を成す生物は、種の存続のために群としての論理に本能的に従っていると考える。だが、人は考える知性を持ち、その知性によって生命維持に必要な環境を整え、その矛盾に向かい合うことができるようになった。そして、群の存続を前提としながら個としての存在を保護するシステム(法)を作り出し、法を持つ社会が出来たのではないだろうか。人の社会は本来の群の形からは矛盾を持った歪んだものである。そのように考えたとき、私は法や社会システム自体が自然な状態から「歪んだもの」ではないかと考える。 以上を踏まえて、社会法益と個人法益について考えることとする。生物の群を考えた場合、そこには社会法益しか存在しない。そして、そこから生まれた人の社会も群の存続を前提にしている以上、保護される個人法益は必要最小限のものにとどまると考える。これは、憲法にて人権について考えたときに明らかであろう。私は法律を学ぶまでは「人権」とはなにものにも侵されることのない広い意味を持つものと漠然と考えていた。しかし、憲法で保障されている人権は限られたものであり、最小限は保障しているが、個が逆に持つ権利(本来の人権)に枠をはめて抑制しているものであることに気がついた。公共の福祉の考えもこの現れであると考える。これらも前提に社会法益の保護(群の存続)があると考えれば納得がいく。つまり、法が保護する個人法益とは社会法益の中にしか存在しないのである。(当然に法の中で矛盾が生じるであろう。)そして、憲法が保障しているのが最小限の個人法益であるならば、刑法や民法はさらに細かく法益の保護内容を定めることにより、社会法益を個人法益へ拡張していくシステムと考えることも出来る。そのために、個々の条文を見たときに
- レポート 法学 法哲学 刑法 憲法 個人 社会システム
 550 販売中 2006/12/26
550 販売中 2006/12/26- 閲覧(1,928)
-
 メディア社会の問題性
メディア社会の問題性
- 現在の日本の社会は、新聞、テレビ、ラジオ、週刊誌等によって多重支配されています。日本に在住している人であれば。なんらかの方法によって必ずといっていいほどメディアから発信される情報に接しているのではないでしょうか。私も、テレビや新聞等と日常生活で接する事が多いです。むしろ、それによってほとんどの情報を得ている気がします。このように、メディア社会は色々な形での“窓”を持っていますが、週刊誌はともかくあとの“窓”から来る情報がどれだけ操作されたものかを私たちは想像もできません。特に、メディアといえばほとんどの人の中で、最初に浮かんでくるものは“テレビ”なのではないでしょうか。昔は、テレビといえばすごい娯楽だったようですが、今となっては、テレビは一般市民の生活にとても密着したものだと思います。朝、会社や学校に出る前に、なにげなしにテレビをつけたり、部屋にいるときに、真剣に見ているわけではないけれども、電気をつける感覚でテレビをつける人もいるのではないでしょうか。ワイドショーなどを見てみると、芸能人のよくないうわさや交際のうわさ等がさも本当かのように、語られています。もちろん、本当の事もあると思
- レポート メディア 問題 気持ちの操作
 550 販売中 2007/01/10
550 販売中 2007/01/10- 閲覧(3,227)
-
 同和(部落)問題について述べよ
同和(部落)問題について述べよ
- 同和 教師 人権
 660 販売中 2009/11/27
660 販売中 2009/11/27- 閲覧(1,132)
-
 白川郷の現状と問題点
白川郷の現状と問題点
- 白川郷の現状と問題点 白川郷は、1995年12月9日に、万里の長城やアンコール・ワットと並ぶ、ユネスコの世界文化遺産として登録された。その結果、合掌造りによって建てられた集落をはじめ、ダムや林道までが観光地となり、観光客による収入や国からの補助金によって村の経済も発展し、遺産の保護や雇用の増加、海外との交流が可能になり、さらには地元の知名度を上げ、地元に対するプライドを持って伝統を伝え、残していくこともできるようになった。 しかし、白川郷と他の文化遺産との大きな違いは、「現在もなおそこに人が住んでいる事」である。実際に村民の住んでいる住居を観光地として開放する事によって、住民たちのプライバシ
- レポート 白川郷 観光 世界遺産
 550 販売中 2006/12/07
550 販売中 2006/12/07- 閲覧(4,987)