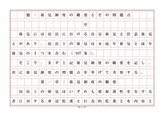連関資料 :: 問題
資料:1,331件
-
 サブプライム問題 まとめ
サブプライム問題 まとめ
- サブプライム問題が私たちの財テクにも波及?? アメリカでおこっているサブプライム住宅ローン問題。皆さんニュースでよく耳にしていると思いますが、これはアメリカだけの問題ではありません。日本の金融機関への影響は先日発表になりましたが個人にどこまで影響が及ぶかは現時点では見えていないのです。もしかすると、あなたが買った投資信託の中にもサブプライムローンが投資先として含まれているかも。。。。。 また、投資信託だけでなく、株価も下落。年明けは世界同時株安が起こり驚愕(ひどく驚く)した人もいるのではないでしょうか 引き金はアメリカの金融機関がサブプライム問題によって被った巨額の損失が発表されたこと、予想以上のリスクの広がりにアメリカ経済全体が打撃を受けられるのでは・・・と考えられたからです。 そもそもサブプライム問題って? 「サブプライムローン」とは、所得が低いなど返済力に問題がある人たちを対象にした住宅ローンのこと。このローンの大半が最初は金利が安く数年後に金利があがるというシステムでした。最初の数年は少ない返済額で済むため、本来ならば借金を背負えないような人々が「家が買える!」とこのローンに飛
- 日本 アメリカ 経済 問題 金融 国家 投資 リスク 影響 政府
 550 販売中 2009/07/22
550 販売中 2009/07/22- 閲覧(1,901)
-
 地球環境「ゴミ問題」
地球環境「ゴミ問題」
- 現状、問題発生のメカニズム、背景 人間が生活していく上で、必ずゴミは出る。本当にすべてがゴミなのだろうか。 現代社会ではゴミが出すぎているのではないのだろうか。例えばスーパーで買い物したとする。野菜・お菓子・魚・肉類、何を購入してもすべて綺麗に包装されている。そして、中には、綺麗に個別包装されているものまである。確かに、衛生的で手も汚れないそして見た目にも美しい。しかし、その生活に伴ってゴミの量は増えている。 日本のゴミ総量は年間約5000万トンを超えている。これは東京ドーム約136杯分に換算することが出来る。国民一人当たりに換算すると1日あたり約1100グラムになる。身近な大阪の問題を挙げてみる。大阪府が一年間に排出するゴミの総量は約430万トン。これは東京都の約520万トンに続き日本で2番目にゴミの多い都市であることを表す。しかし、この量を人口から見ると、東京都の人口は約1,180万人に対して、大阪府の人口は約880万人。これを1日1人あたりが出すゴミの量に換算すると、東京都約1200グラム大阪府約1350グラムである。全国第1位のゴミの都市である。
- ゴミ問題 地球環境 エコ
 550 販売中 2008/07/14
550 販売中 2008/07/14- 閲覧(4,326)
-
 マーケティングの基礎試験問題
マーケティングの基礎試験問題
- マーケティング テスト問題
 550 販売中 2010/04/26
550 販売中 2010/04/26- 閲覧(1,694)
-
 還元論の問題点について
還元論の問題点について
- 「還元論の問題点について」 還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。 私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。 そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われることは自然なことであり、その上位者(強者)が群の統制をとることとなる。そして、生物が同種であっても群同士で争うことを考えれば、群全体の目的は群そのもの、または群を支配する上位者(上位者の子孫を含む)の存続ということになるのではないだろうか。この群(上位者)の存続のためには、群内の下位者(弱者)の生命が疎かにされることも当然に起こりえよう。つまり、個の生命よりも群自体が重く見られることとなる。しかし、人(人に限らず生物)は本能的に生命に対する畏怖の念を持っている。ここで、個としての存在と群を成す存在としての間に矛盾が生じることとなる。一般の群を成す生物は、種の存続のために群としての論理に本能的に従っていると考える。だが、人は考える知性を持ち、その知性によって生命維持に必要な環境を整え、その矛盾に向かい合うことができるようになった。そして、群の存続を前提としながら個としての存在を保護するシステム(法)を作り出し、法を持つ社会が出来たのではないだろうか。人の社会は本来の群の形からは矛盾を持った歪んだものである。そのように考えたとき、私は法や社会システム自体が自然な状態から「歪んだもの」ではないかと考える。 以上を踏まえて、社会法益と個人法益について考えることとする。生物の群を考えた場合、そこには社会法益しか存在しない。そして、そこから生まれた人の社会も群の存続を前提にしている以上、保護される個人法益は必要最小限のものにとどまると考える。これは、憲法にて人権について考えたときに明らかであろう。私は法律を学ぶまでは「人権」とはなにものにも侵されることのない広い意味を持つものと漠然と考えていた。しかし、憲法で保障されている人権は限られたものであり、最小限は保障しているが、個が逆に持つ権利(本来の人権)に枠をはめて抑制しているものであることに気がついた。公共の福祉の考えもこの現れであると考える。これらも前提に社会法益の保護(群の存続)があると考えれば納得がいく。つまり、法が保護する個人法益とは社会法益の中にしか存在しないのである。(当然に法の中で矛盾が生じるであろう。)そして、憲法が保障しているのが最小限の個人法益であるならば、刑法や民法はさらに細かく法益の保護内容を定めることにより、社会法益を個人法益へ拡張していくシステムと考えることも出来る。そのために、個々の条文を見たときに
- レポート 法学 法哲学 刑法 憲法 個人 社会システム
 550 販売中 2006/12/26
550 販売中 2006/12/26- 閲覧(1,927)
-
 メディア社会の問題性
メディア社会の問題性
- 現在の日本の社会は、新聞、テレビ、ラジオ、週刊誌等によって多重支配されています。日本に在住している人であれば。なんらかの方法によって必ずといっていいほどメディアから発信される情報に接しているのではないでしょうか。私も、テレビや新聞等と日常生活で接する事が多いです。むしろ、それによってほとんどの情報を得ている気がします。このように、メディア社会は色々な形での“窓”を持っていますが、週刊誌はともかくあとの“窓”から来る情報がどれだけ操作されたものかを私たちは想像もできません。特に、メディアといえばほとんどの人の中で、最初に浮かんでくるものは“テレビ”なのではないでしょうか。昔は、テレビといえばすごい娯楽だったようですが、今となっては、テレビは一般市民の生活にとても密着したものだと思います。朝、会社や学校に出る前に、なにげなしにテレビをつけたり、部屋にいるときに、真剣に見ているわけではないけれども、電気をつける感覚でテレビをつける人もいるのではないでしょうか。ワイドショーなどを見てみると、芸能人のよくないうわさや交際のうわさ等がさも本当かのように、語られています。もちろん、本当の事もあると思
- レポート メディア 問題 気持ちの操作
 550 販売中 2007/01/10
550 販売中 2007/01/10- 閲覧(3,226)
-
 高齢者の虐待問題について
高齢者の虐待問題について
- 最近の老‐老介護の現場で起こった殺人事件にも見られるように、高齢者の虐待が大きな社会問題となっている。虐待の対象となるのは高齢者の中でも 特に女性が多い。また、理解力・判断力の低下、足腰の虚弱化などで抵抗・反論ができない介護度のより高い人ほど、より高齢である人ほど、虐待の対象となりやすい傾向がある。このように、虐待の対象となる高齢者は社会的弱者がほとんどである。社会的弱者とは、経済弱者、人権侵害弱者、情報化社会に付いていけず情報に乏しい情報弱者、地域・社会との繋がりが絶たれた社会関係弱者のことを指す。 虐待の種類には、主に次の5つがある。?殴る・つねるなどの身体的虐待、?不安・恐怖心を与えるような言動をする心理的虐待、?年金や貯金を勝手に使う経済的虐待、?性的虐待、?世話・介護を放棄するネグレクト(放置・放任)である。
- レポート 福祉学 高齢者 虐待 老-老介護 社会的弱者 女性
 550 販売中 2006/03/15
550 販売中 2006/03/15- 閲覧(2,556)
-
 開発・環境問題の事例
開発・環境問題の事例
- <はじめに> 現在、この地球上には多くのダムが設置されている。日本にも多くのダムが存在しているが、このダムを造るにあたり、ほとんどの場合さまざまな問題が議論される。では、人々はそもそもなぜダムを造るのであろうか。その目的は地域によっていくつかある。 基本的な目的としては、第一に、「水位調節」があげられる。大雨により川の水位が急激に上昇し、川が氾濫すると、下流にある川沿いの家や田畑や道路までもが、浸水もしくは水没してしまうことがある。このような事態を防ぐため、ダムは作られる。ダムによって大量の雨を貯水池に貯め、水量を調節し下流に流すことにより、下流の地域に被害を出さないように水を処理できるのである。逆に渇水が起こった場合でも、ダムに貯めてあった水を川に流し、渇いた河川に水を供給することができる。このように、ダムは川に流れる水量を調節し、川の流れを安定させる役割を果たしている。次に、水道水や工業用水、農業用水としての利用がある。さらには、水力発電も行われている。この場合、火力発電のようにCO2が発生することもなく、原子力発電のような危険性も低いだろう。
- レポート 社会学 ダム問題 緑のダム クマタカ
 550 販売中 2006/04/26
550 販売中 2006/04/26- 閲覧(1,597)
-
 地球温暖化問題
地球温暖化問題
- 地球温暖化は非常に深刻な問題である。温暖化が進む原因としては化石燃料による大気汚染の影響が大きい。そのためにはクリーンなエネルギーが求められているといえる。太陽エネルギーはクリーンかつ、無限にあるエネルギーとしてさまざまな分野から期待されている。化石燃料が限りあるのならばいずれ化石燃料はなくなってしまう。産業革命以来、人類の科学技術の歴史を支えてきた化石燃料の依存からの脱却が今、求められているのである。 そこで、われわれが今できることはなんであろうか。例えば、NPO法人グリーンピースジャパンではサポーターを募集している。グリーンピースは、個人からのみの財政的支援によって活動していて、活動の独立性を保つため、政府・企業からの財政的支援は一切受けていない団体である。現在世界280万人のサポーターが既に環境問題に対してアクションを起こしている。具体的にはボランティアとして事務作業、翻訳、イベントなどの活動に参加することやパンフレットを通して広報活動に協力する、またweb上でのサイバーアクション、つまりWeb上で自分の主張を政治家や、企業にメールで送るサイバーアクションを呼びかけるといった方法もある。いま一例として、グリーンピースを挙げたが、こうした環境問題に取り組んでいるNGO・NPO団体は今多く存在する。中には学生が主体なものある。一人一人の声の影響力は小さくとも、こうして地に足のついた活動を続けていくことで、大きな地球規模の問題に立ち向かっていけるのではないだろうか。
- レポート 環境 地球温暖化 グリーンピース
 550 販売中 2005/07/30
550 販売中 2005/07/30- 閲覧(2,834)