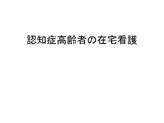連関資料 :: 認知について
資料:207件
-
 認知心理学 科目修得試験【評価B】
認知心理学 科目修得試験【評価B】
- 単位認定を正式に頂いたレポートです。私の作成したレポートは、全体的に表や図などを使って作成している事が多いです。ご購入なさったお客様が、今後のレポート作成において、何かしらのお力添えができればうれしいなと思い、投稿しました。どうぞ、ご活用下さい。
- 星槎大学 レポート
 660 販売中 2025/07/25
660 販売中 2025/07/25- 閲覧(272)
-
 人体の構造と機能および疾病―認知症の原因と症状について
人体の構造と機能および疾病―認知症の原因と症状について
- 社会福祉士養成講座 レポート評価 A 絶対に模写しないでください
- 福祉
 660 販売中 2018/07/09
660 販売中 2018/07/09- 閲覧(2,785)
-
 認知主義/行動主義 学習諸理論の特徴
認知主義/行動主義 学習諸理論の特徴
- 認知主義の学習諸理論を概括したうえで、行動主義の学習諸理論と対比させ、その特徴を説明せよ。 「認知主義」とは、客観的に観察のできない心の内面(主に記憶)を研究する事で、学習過程を明らかにしようとする立場である。これに対し「行動主義」の研究対象は、行動に限定する立場である。 我々は、認知機能―つまり、人間が外部からの情報をどのように解釈したり判断したりするかの仕組み―を直接観察する事ができない。それまでも直接観察できない心のしくみを研究する科学者はいたが、これらは科学的でないと考えられた。その為、いつしか心理学は、外部からの観察が可能な「行動」の科学に限定され、客観的なデータのみが絶対視されるようになった。このような立場は行動主義と呼ばれ、1920年頃から1950年頃まで、心理学で最も優勢な立場であった。ただその間、認知機能の研究が全く行われなかったわけではない。ただし、この時代の認知主義における学習理論は、行動主義と基本的には同じ範疇に属する捉え方であった。人によっては、この時代の認知主義を「新行動主義」と呼ぶ。 現代においてのいわゆる「認知心理学」の始まりは、1960年頃であるとされ
- レポート 心理学 SR理論 認知主義 行動主義
 550 販売中 2007/02/24
550 販売中 2007/02/24- 閲覧(21,589)
-
 認知心理学実験 文章の聞き取りとノートテイキングの効果
認知心理学実験 文章の聞き取りとノートテイキングの効果
- 文章聞き取りにおけるノートテイキング方略の効果に関する研究 ―試験に対する動機づけとノートテイキング方略の関係から― 【問題と目的】 ノートテイキングは、講義場面や試験勉強などの場面で多くの学習者が利用する学習方略の一つである。岸・塚田・野嶋(2004)は、大学の講義形式の授業でノートテイキングの有無と事後テストとの関係を分析し、ノートテイキング量とテスト得点との間に強い相関があることを示した。では、ノートテイキングにはどのような方略があるのだろうか。斎藤・源田(2008)は、ノートテイキングの方略の使用が学習内容の理解に与える効果について検討し、ノートテイキングの6つの方略(①箇条書き②文字の強調―太さ、大きさ③図表④下線⑤囲み⑥矢印)を抽出し、方略を多く使用した者の方が学習内容の理解も高いという結果を示した。しかし、ノートテイキングの個々の方略の比較についての検討はされていない。私達はノートテイキング方略として箇条書きや記号を多く用いるが、どの方略が効果的なのか分かっておらず、また、動機に注目した研究も行われていない。 そこで本研究ではまず、音声のみの講義場面におけるノートテイキン
- 実験 学習 分析 大学 試験 理解 動機 文章 アンケート 研究
 550 販売中 2009/07/27
550 販売中 2009/07/27- 閲覧(3,293)
-
 子どもの心理入門 「乳幼児における認知機能の発達について述べよ」
子どもの心理入門 「乳幼児における認知機能の発達について述べよ」
- 「乳幼児における認知機能の発達について述べよ」
- 保育 社会 教育
 550 販売中 2011/11/16
550 販売中 2011/11/16- 閲覧(1,892)
-
 行動主義と認知主義が学習の相違について論述せよ
行動主義と認知主義が学習の相違について論述せよ
- 学習理論は二つの主な立場に分類する事が出来る。一つは行動主義心理学に基づく「刺激―反応説」であり、もう一つは認知心理学に基づく「認知説」の立場である。反応説とは、生徒が環境刺激に対して新しい反応を学ぶ事を学習と考える立場であり、一定の刺激と一定の反応との直接的な結合で学習を問題とする。これに対し認知説は、環境刺激が持つ構造やそれが持つ要素の内的関係を認知する事が学習の重要な要因であると考える立場である。 刺激―反応説は学習の成立に必須の要因は、一定の反応を生じさせる為に一定の刺激を与える事ではなく、むしろ反応の結果に対する励ましや報酬などの強化であり、どのような反応に対してどの様な強化を与えるかによって好ましい行動を習慣化し学習を成立させる事が出来るとしたのである。ここで重要な事は、学習者自身が環境に働きかけるという、学習者の能動性が重要な意味を持っている事と、学習者が期待される反応を示すと、その反応の直後にその反応を強化する強化刺激が随伴しているという仕組みであるとし、学習は刺激と反応との関係の変化・・・
- レポート 教育学 行動主義 認知主義 刺激 学習 心理学
 550 販売中 2008/09/16
550 販売中 2008/09/16- 閲覧(14,368)
-
 心理学基礎実験 認知的コンフリクトの研究実験
心理学基礎実験 認知的コンフリクトの研究実験
- 目的と問題 心理学的意味のコンフリクト(葛藤)という言葉をご存知だろうか。葛藤(コンフリクト) とは、2つ以上の欲求が同時に存在し、いずれを選択するか迷う状態をいう。年齢や生きた環境、経験が違えば、人間の価値観、考え方は十人十色。そんな人間同士がチームを組めば、コンフリクト(葛藤・意見の対立)は間違いなく発生する。コンフリクトが感情の対立にまで発展すると、もはやチームは機能しなくなる。コンフリクトが発生した場合の適切な対処方法が課題となる。 レヴィンによると、葛藤には次の3つの類型がある。 1.接近−接近型 2つの魅力的なもののどちらかを選ばなくてはならないとき。複数の要求の対象が、ともに正の誘因性を持ち、いずれも満足させたいが、同時にはかなえさせることができない状況。 2.回避−回避型 2つの避けたいもののどちらかを選ばなくてはならないとき。複数の要求の対象が、ともに負の誘因性を持ち、どちらも避けたいが、それができない状況。 3.接近-回避型 魅力的なものと避けたいものが同時に存在している状態。要求の対象が、同時に正と負の誘因性を持つ場合。あるいは負の領域を通過しなければ、正の領域に到達できない場合。 最後に複合型についても記しておこう。 複合型のコンフリクト 複数の目標(選択肢)があって、それぞれが正あるいは負、または両方の誘因性を持つ場合。現実の多くの問題はこれに該当する。 人間の脳は右半分(右脳)と左半分(左脳)に分かれていて、それぞれがちがう働きを持っている
- レポート 心理学 心理学基礎実験 認知的コンフリクトの研究実験 葛藤(コンフリクト) 右脳と左脳の処理機能 精神的健康調査票
 550 販売中 2006/05/18
550 販売中 2006/05/18- 閲覧(7,638)
-
 【聖徳大学】知覚・認知心理学1-1② 【評価S】
【聖徳大学】知覚・認知心理学1-1② 【評価S】
- 東京聖徳大学通信教育学部心理学科の知覚認知心理学の課題1設題1の2つ目のレポートです。あくまでもご参考程度にお願いいたします。必ずしもS評価がとれるとは限らないことをご承知おき下さい。 【課題名】 ② 感性認知のメカニズムについて、適切な具体例を挙げながら、知性処理と感性処理それぞれの働きと関わりを踏まえながら説明せよ。 ※参考文献 ・行場次郎・箱田祐司編著『新・知性と感性の心理-認知心理学最前線-』(福村出版)
- 聖徳大学 心理学 知覚認知心理学
 440 販売中 2025/04/24
440 販売中 2025/04/24- 閲覧(864)
-
 医学概論 「認知症について述べよ。」 課題レポートA判定
医学概論 「認知症について述べよ。」 課題レポートA判定
- 認知症とは、脳の病気によって起こる症状であり「脳の後天的な障害によって、知能が持続的かつ比較的短時間のうちに低下し、日常生活に支障をきたすようになること」をいうが、認知症かどうかのポイントは、①記憶の低下、②認知の障害、③生活の支障の3つがあるかどうかという事である。この事を踏まえ、年相応の物忘れとの違いについて詳しく述べていく。 認知症と年相応の物忘れの鑑別は難しく困難である。認知症の初期症状に物忘れがあるが、物忘れのある人がすべての認知症というわけではなく、老化現象としての物忘れ(最近では、これを軽度認知障害と呼び、認知症の前段階と考えて、予防の試みが行われている)もあり、見分けが難しい。ただ、認知症と年相応の物忘れを比較すると、認知症は、特徴として体験した全体を忘れてしまう・進行する、見当識障害がある・自覚しない・生活機能に障害がでる・問題行動がある。
- 環境 福祉 日本 社会福祉 認知 認知症 社会 介護 心理 障害
 1,650 販売中 2010/09/24
1,650 販売中 2010/09/24- 閲覧(5,496)
-
 整形外科レポート 高齢者の転倒骨折と認知症
整形外科レポート 高齢者の転倒骨折と認知症
- 『高齢者の転倒骨折と痴呆』 【はじめに】 今回、高齢者の骨折にアプローチしていく中で、痴呆が問題点の回復の遅延を起こしている要因であると考えたために高齢者の転倒骨折と痴呆の関係を調べ以下に報告する。 【高齢者の転倒骨折の特殊性】 高齢者では、転倒経験が身体的及び精神的な影響を及ぼす。転倒は、時には明らかなに歩行能力の低下をきたし、約5%に骨折を招来する。 高齢者はささいな転倒で骨折する。高齢者の転倒には内的要因と外的要因がある。内的要因には末梢神経障害、坐骨神経障害、姿勢異常、注意障害などがある。葛原は、転倒の理由は、加齢によって視力、聴力、平衡感覚、位置覚、四肢筋力、瞬発力、機敏動作などが低下して転倒しやすい状態にあるためであり、これらに何らかの疾患が加わると、さらに転倒しやすくなると述べている。これらに加えてCummingsらは、痴呆、鎮痛剤・睡眠剤の内服、パーキンソン病の既往など具体的な疾患や薬剤の影響をあげている。外的要因には段差、敷居など家屋構造の問題、スロープ、コード、ジュ-タンのつまずき、床面の滑りなどである。 高齢者の場合、骨折が治っても再び別の骨折を引き起こすこ・・・ 【転倒予防策】
- 環境 高齢者 問題 障害 自立 能力 リスク 生命 合併 リハビリテーション 看護 看護学 転倒予防 合併症 予後 歩行 精神疾患
 550 販売中 2009/04/27
550 販売中 2009/04/27- 閲覧(4,847)