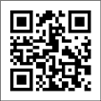連関資料 :: 科学とは
資料:334件
-
 「観察の理論負荷性」「科学革命」「全体論」
「観察の理論負荷性」「科学革命」「全体論」
- まずはハンソンの「観察の理論負荷性」から説明する。 授業や参考資料とした本では「アヒルウサギ図」を例に、観察の際にどうしても使用してしまう理論(アヒルの理論・ウサギの理論)がある、としていた。ぱっと見て、アヒルをあらわしているようにもウサギをあらわしているようにも見える、と言う事実が、われわれの観察は身に着けた理論を通して行われていることを示しているのだそうだ。この観察の性質を「観察の理論負荷性」と言う。ハンソンの言うのはこのような内容である。 ところで、私がこの「アヒルウサギ図」を観察した時に思ったのは「アヒルをあらわしている」「ウサギをあらわしている」に加えて「アヒルウサギ図である」ということであった。「『アヒルウサギ図』の理論」をすでに持っていた私は、ハンソン以前よりもひとつ余分(?)な認識を得たのである。これも「観察の理論負荷性」と言えるだろう。 ところでこのことは、クーンの「科学革命」の考え方にもつながっているのではないか。 この「科学革命」は知識の進歩に関するひとつのモデルである。 これとは別の「ホイッグ主義的な進歩観」では「知識は少しずつ蓄積され、進歩している」と言う。しかし、蓄積された知識ではつじつまの合わない例が多々発見されたとき、これらを総合して説明できるような新しい理論、いわゆるパラダイムによって化学は次のステップに進む。つまりホイッグ主義的な進歩の仕方で行きlまったときに「科学革命」が起こるというのがクーンの示す進歩のモデルである。 さて、これがさっきの理論負荷性とどうつながっているのか。 パラダイムも観察を行う際の理論の一つと言えるだろう。ホイッグ主義的な進歩で行き詰まることは、すなわち、理論を持っていないために観察できない状態に陥ることに言いなおせる。
- レポート 哲学 科学哲学 理論負荷性 パラダイム 全体論 アヒルとウサギ
 550 販売中 2005/12/16
550 販売中 2005/12/16- 閲覧(13,759)
-
 行動科学的管理論における動機付けとリーダーシップ
行動科学的管理論における動機付けとリーダーシップ
- 「リーダーシップ」について考えていくに当たり、そもそもの言葉の意味を考えるところからはじめたい。「大辞林」によれば「指導者としての素質・能力、統率力。」と定義されている。特に企業において言えば部下や関係する部署の人たちに対し、動機付けを行えるような影響力のことを言う。 では、リーダーとしての人は、どのようにリーダーシップを発揮して、部下や関係する部署の人たちを動機付けて効率的に働かせるのか?この問題を答える前に、まず、人は何に動機付けられて行動するのかを考えたい。 人の行動は欲求を満足させようという気持ちであるモチベーションによって引き起こされるのである。
- 企業 リーダー 人間 組織 指導 影響 リーダーシップ 行動 動機
 550 販売中 2011/07/06
550 販売中 2011/07/06- 閲覧(3,065)
-
 【玉川大学】(コア)地球科学入門「大陸移動」
【玉川大学】(コア)地球科学入門「大陸移動」
- ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「(コア)地球科学入門」平成22年度課題の合格済レポートです。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> A(合格) <批評> 大陸移動説からプレートテクトニクスへの流れ、その発想の根拠となる事実・現象を要領よくまとめられた良いレポートです。 最新のプレートテクトニクスについての根拠、考えについてもまとめられればよかったですが。 ____________________________ 今まで様々な人たちが地球はどのような構造になっていて、どのように動いているのかという疑問に取り組んできた。その中で有力な説として後世まで語り継がれてきたのが、大陸移動説をはじめ、海洋底拡大説、プレートテクトニクスである。 このレポートでは、これらの内容を理解するために、まず、歴史の流れに沿って諸説を概観する。次に、各説の内容と説の根拠となる現象や事実を詳しく述べる。 まず、時系列で諸説を概観する。すなわち、大陸移動説、海洋底拡大説、プレートテクトニクスの順である。 1910年代、ドイツの地球物理学者ウェゲナーは、大西洋を挟むアフリカ大陸と南アメリカ大陸の海岸線の類似から、大陸移動説を唱えた。ウェゲナーは地質構造の連続性、化石分布、氷河の痕跡などの有力な証拠を提示し、一定の支持を得たが大陸移動の原動力を説明できず、この説は徐々に衰退していった。しかし、1950年代に入り、各大陸の岩石に記録されている残留磁気から求められる磁北移動曲線が異なることが明らかとなり、大陸移動説が復活した。 海底地形、熱流量などの研究成果からヘス、ディーツらが1960年代前半に海洋底拡大説を唱え、さらに海底岩石の古地磁気磁化方位が海嶺をはさんで対称の縞模様となることが発見されたことで、海嶺でマントル物質が沸き上がり海洋底をつくってそれが両脇に動いていくと言う海洋底拡大説が多くの地球科学者に受け入れられるようになった。 1960年代後半、マッケンジー,モーガン,ルピションらが地震の起こり方,トランスフォーム断層の走向,地磁気縞模様から推定される海洋底拡大速度などのデータを用いて、地球表面を剛体として移動するプレートという概念を導入し、主要なプレートの運動を決定した。これが海洋底拡大説、大陸移動説を取り込んだプレートテクトニクスである。 このように、地球の仕組みが少しずつ解明されてきた。現在ではプレートテクトニクスの考えを乗り越えたプルームテクトニクスという考え方も出てきており、さらに細かくより詳細に地球を捉えてきている。 次に、各説の内容や、その説の根拠となる現象や事実について詳しく述べる。 大陸移動説とは、現在の大陸はかつて全てひとつにまとまっていたとする説である。ドイツ…
- アメリカ 科学 ドイツ 物理 地球 運動 地震 調査 研究 記録 玉川 通信
 990 販売中 2015/07/07
990 販売中 2015/07/07- 閲覧(3,831)
-
 (コア)情報科学入門 科目試験 解答例
(コア)情報科学入門 科目試験 解答例
- 平成23~26年度の4年間で出題された設問、及び教科書の章末問題を、内容の重複を避けて全て抽出しました。計100問強になります。ハード・ソフト・ネットワーク・マルチメディア・モバイル・情報システム・セキュリティの7つの分野に整理し、「解答例」及び、「回答時のキーワード」を載せています。 難攻不落と呼び声高いこの科目試験ですが、私はこれをまとめて突破しました。少しでも皆様の勉強の足しになれば幸いです。
- 情報 レポート 記憶 国際 科学 コンピュータ 問題 ネットワーク プログラム 通信 玉川 科目試験
 550 販売中 2015/08/10
550 販売中 2015/08/10- 閲覧(2,611)
-
 科学とは何か--「二つの文化」論から「知のモード」論へ
科学とは何か--「二つの文化」論から「知のモード」論へ
- 科学とは何か--「二つの文化」論から「知のモード」論へ 科学の独立と科学者の誕生 英語のscientist(科学者)という言葉が創られたのは1830年代のことであった。すでにscienceという言葉はあったが、philosophyとほぼ同義語として用いられており、ともに広い意味での知的探求(哲学)とその成果としての知識を意味していた。したがって、自然を対象とした知的探求は哲学の一部としての自然哲学(natural philosophy)であり、例えば、ニュートン(1642-1727)は、自然哲学者(natural philosopher)と呼ばれたのである。しかし、19世紀になると、philosophy(哲学)から、自然を対象とし実験や観察を方法とする固有の学問分野としてのscience(科学)が独立し、科学を探究する専門家としての科学者が誕生したのである。 「科学の独立」と「科学者の誕生」は、教育・研究の場としての大学の発展拡大と時期を同じくしていた。中世以来の伝統を有するヨーロッパの大学では、(自然)科学を教え研究する部門はなかったのだが、19世紀を通じて自然科学の教育・研究が次第に拡充強化され、科学者が養成されるようになった。従来の人文的伝統を中心とした大学・知識社会の中に、新しく科学的伝統が加わったったのである。科学は次々に新しい専門分野を開拓して勢力を拡大するとともに、20世紀に入ると技術と深く結びつき、「科学技術」として経済社会や政治に大きな影響を及ぼすに至った。 スノーの「二つの文化」論とクーンの科学論 科学の専門細分化と科学技術の影響力の拡大の結果、深刻な文化的危機が生じつつあるのではないかとの懸念が表明された。1959年、イギリスの著作家C.P.スノー(1905-1980)は「二つの文化と科学革命」と題された講演で、科学革命(20世紀前半における科学技術の発展をスノーは「科学革命」と呼んだ)の結果、西欧の知識人社会に大きな亀裂が生じつつあると論じたのである。すなわち、スノーは人文的文化(その代表としての文学者)と科学的文化(その代表としての物理学者)の間には越えがたい亀裂=溝があり、両者は互いに理解しあうことができず、言葉さえ通じなくなってしまっていると論じ、これは西欧文化における危機だと警鐘を鳴らしたのである。スノー自身、物理学者としての経験をもつ評論家・小説家という特異なキャリアの持ち主であり、文化の分裂に深刻な懸念を抱いたのであった。文化の分裂という危機に対するスノーの処方箋は、科学革命という現実を踏まえて、文系知識人が科学技術に対する基本的な認識と理解をもつよう努力すべきではないか、というものであった。 スノーの講演の数年後、クーンの『科学革命の構造』が出版された(1962年)。物理学者から科学史家に転じたT.S.クーン(1922-1996)は、科学研究は「一般に認められた科学的業績で、一時期の間、専門家に対して問い方や答え方のモデルを与える」パラダイム(paradigm)を基盤に遂行されると論じ、科学の歴史を「パラダイム・チェンジ=科学革命」の歴史と捉えた。クーンの科学論は従来の累積的・連続的な科学史観を根底からくつがえすとともに、自然科学(の各専門分野)には明確なパラダイムがあるが、人文・社会科学にはパラダイムがみてとれないと論じて、自然科学と人文・社会科学の差異を浮き彫りにし、「二つの文化」の存在を科学論の立場から裏付けた。 総合科学の試み このように、1960年代には、事態を憂慮するかどうかは
 全体公開 2007/12/24
全体公開 2007/12/24- 閲覧(2,309)
-
 「健康を維持するための食事について述べよ」(健康科学)A判定
「健康を維持するための食事について述べよ」(健康科学)A判定
- 健康科学、A判定です。あまり自信の無かったレポートでしたがA判定を頂いたので、5大栄養素さえきっちり書けていればなんとかなるかと思います。A判定でしたが、少々直しというか、間違いを指摘された箇所もありますが、あえてレポート内容には手を加えてません。糖質のところで、「効率よく代謝するためには豚肉や穀物に含まれるビタミンB1が必要だ。」とありますが、ビタミンB1は関係ないとの添削がありました。研究の成果からなのかこの手の科学的な科目は、参考文献は出来るだけ新しいものを使う事と、インターネットで最新情報を確認することをお勧めします。
- 健康科学 日本 健康 エネルギー 生活習慣病 生活 栄養 生活習慣 組織 ストレス 運動 東京福祉大学 A判定
 550 販売中 2011/10/04
550 販売中 2011/10/04- 閲覧(3,818)