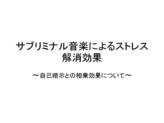連関資料 :: 音楽
資料:330件
-
 P2Pによる音楽業界への影響
P2Pによる音楽業界への影響
- 一、はじめに 最近では音楽業界の売り上げが激減している。日本のCD総生産額は1998年の6075億円をピークに、年々減少している。音楽業界はこれを違法コピーとPeer to peer、つまりファイル交換ソフトのせいだと批判している。だが本当にそうであろうか。 これから先、iPodなどの普及によりインターネットの音楽配信が進むであろう。これによりファイル交換ソフトも形態を変え、様々な方法で普及していくと予想される。 そこで、ファイル交換ソフトが実際に音楽業界のCD売り上げに与えた影響と、それを踏まえてこれより先音楽業界はどう変化していくかを考えていく。 二、P2Pとはなにか P2Pとは大まかに説明すると、不特定多数の個人間で直接情報のやり取りを行なうインターネットの利用形態、また、それを可能にする「Napster」などのアプリケーションソフトの総称である。多数のコンピュータを相互につないで、ファイルなどの情報資源を共有するシステムである。1999年1月にNapsterが出てきてから、「音楽を無料で手に入れられるソフト」として若者を中心に爆発的に広まった。それからGnutellaやWinmx、Winny、など数多くのファイル交換ソフトが普及し、現在では百種類以上あるといわれている。 一言にP2Pといっても、種類によって様々な特徴がある。例えばNapsterでは、各コンピュータは中央サーバに接続し、ユーザのパソコンに保存されている音声ファイルのリストを送信する。そしてこれを、世界中のユーザが共有する。中央サーバはファイル検索データベースの提供とユーザの接続管理のみを行っており、音楽データ自体のやり取りはユーザ間の直接接続によって行われている。Gnutellaは、Napsterと違って中央サーバを必要とせず、すべてのデータが各ユーザ間でやり取りされている。 三、批判の立場 四、賛成の立場 五、まとめ
- レポート 経済学 P2P peer to peer ファイル交換 音楽業界 違法コピー
 550 販売中 2005/11/12
550 販売中 2005/11/12- 閲覧(2,705)
-
 S5521 初等教育内容音楽
S5521 初等教育内容音楽
- S5521初等教育内容音楽の合格済みレポートです。 〈設題〉 平成29年版小学校学習指導要領における各学年(どの学年を選んでもよい)の「2 内容」の4つの活動(歌唱の活動・器楽の活動・音楽づくりの活動・鑑賞の活動)を確認し、それぞれの活動に1つずつ「指導する事項」(合計4つの指導する事項)を任意に選ぶ。それぞれの「指導する事項」に適した具体的な指導方法と,その指導を行うために教師が備えておくべき音楽的能力(「指導方法」と勘違いしないこと。あくまでも教師の「音楽的能力」そのものをあげる)について,テキストの内容と私見を織り交ぜて具体的に論述せよ。 *後に述べる「第1設題の留意点」に必ず従うこと。従っていない場合は受理を認めない。 佛教大学は添削が厳しいので、そのまま扱うことはやめてください。あくまでも、参考程度にご利用ください。
- 教師 小学校 子ども コミュニケーション 学校 音楽 学習指導要領 児童 指導 学習
 880 販売中 2021/04/28
880 販売中 2021/04/28- 閲覧(4,555)
-
 聖徳大学 音楽科教育法
聖徳大学 音楽科教育法
- 第1課題 第1設題 リコーダーは、3年生から習い始める学校が多いが、1年間の指導で演奏技術の基礎がほぼすべて決まってしまうともいえる。つまり、その最初の指導が、後々までずっと響いていくのである。 次に挙げる導入時の指導が重要となる。 (1)事前指導 リコーダーという名前の由来を知らせる、中身を確認する、記名の仕方を確認する、やってはいけないことを分からせる、リコーダーの秘密を探る課題を出すなど。興味・関心を持たせる為に実際に教師が吹いてみせることも大切である。その時、リコーダーの名前の由来が鳥の鳴き声ということもあるので、「かっこう」などの曲を選択し、実際に鳥が鳴いているように冒頭の部分を2小節ほど吹いてみせることで、子どもたちは早く自分のリコーダーにさわりたくて仕方がなくなってくる。 (2)持ち方 一番、最初に子どもにリコーダーを持たせる時、「シ・ラ・ソ」の運指も兼ねさせる意味合いで、左手から持たせることが多い。それが、そもそもの間違いの始まりになる。演奏をする時、リコーダーを支えているのは、唇(下唇)と右手の親指の2点である。つまり、右手の親指が、リコーダーの中部管のどこにあるか
- 子ども 教師 課題 指導 姿勢 自分 意味
 550 販売中 2009/02/12
550 販売中 2009/02/12- 閲覧(2,208)
-
 音楽と近代市民社会について- ベートーヴェンの生涯
音楽と近代市民社会について- ベートーヴェンの生涯
- 音楽と近代市民社会について ― ベートヴェンの生涯を追って ― 1770年、フランスにほど近いライン川左岸のボンに生まれたベートーヴェンは、幼少期における思想形成をその地理的条件から、ドイツよりもむしろフランス寄りのものとして形成させる。これはベートーヴェンが生涯に渡って貫くドイツ体制批判・フランス志向の根幹となる。 時代は18世紀末、近代の黎明期であった。近代以前の完全に階級・身分制度に規定された社会から、フランス革命は市民を解き放った。自由主義が台頭し、個人の能力規定型社会へと世は変貌を遂げた。 音楽史に関してみてみると、それまでの音楽は教会や宮廷と密接に関係し、芸術家達は経済的には安定を得ていた反面、作品の主義や目的はその絶対的パトロンである支配階層のイデオロギーを反映したものであった。それに対し、古典派と呼ばれる時代にはいった芸術家たちは、近代市民社会の基本原理である市場経済に目を向けた。そして、ブルジョワ達の趣味に合わせることにより、教会や宮廷からの自立を果たしたのである。これは同時に芸術の市民階級への開放をも意味していた。ベートーヴェンにとってもその自立は大きな意味をなしていた。 500
- 経済 倫理 社会 文化 政治 ドイツ 音楽 芸術 思想 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
 550 販売中 2010/01/26
550 販売中 2010/01/26- 閲覧(3,488)
-
 初等音楽科教育法 2
初等音楽科教育法 2
- 明星大学(2013年入学)
 550 販売中 2014/09/16
550 販売中 2014/09/16- 閲覧(1,438)
-
 日本音楽の歴史と理論 提出課題
日本音楽の歴史と理論 提出課題
- 大阪芸術大学通信教育課程に在籍中です。「日本音楽の歴史と理論」で評価「B」をいただきました。
- 大阪芸術大学 日本音楽の歴史と理論 歌舞伎
 550 販売中 2015/07/28
550 販売中 2015/07/28- 閲覧(3,140)
-
 デジタル音楽市場におけるアップルの開発戦略
デジタル音楽市場におけるアップルの開発戦略
- アップルのデジタル音楽市場における戦略を概観すると、開発段階からの念入りなマーケティングが功を奏していることがうかがえる。すなわち、従来はソフトとハード、そしてサービスがばらばらに提供されていたデジタル音楽市場において、アップルは統合されたデジタル音楽ソリューションを提示したのである。 アップルの戦略によって、消費者のデジタル音楽シーンは大きく変化したと一般的に言われている。これまでは、音楽データを携帯する場合、MDにせよCDにせよ、あるいはMP3などの圧縮ファイルにせよ、あらかじめ出先で聴く音楽を選び、それを持ち出す必要があった。アップルの開発したiPodは当初から5GBのハードディスクを搭載しており、「手持ちの音楽をすべて携帯する」というまったく新しいデジタル音楽の利用方法を可能にしたのである。 これはアップルの製品が結果的にそのような利用シーンを生み出したのではなく、アップルのスティーブ・ジョブズCEOのマーケティング手腕によるものだとアップルは述べている。 今後、2005年には前出のiTMSが日本でもサービスを開始する予定で、すでにソニーなど主要レーベルが提供している同様のサービスMoraとどのように競争していくかが注目されている。 諸外国のようにデジタル音楽市場が今後ますます拡大するのは確実だが、それに伴い既存の店舗ベースの音楽市場が縮小するかどうかは、CDというメディアを生かした新しい製品を開発できるかどうかにかかっていると言える。
- レポート 経営学 アップル iPod デジタル音楽
 550 販売中 2006/02/13
550 販売中 2006/02/13- 閲覧(2,828)
-
 音楽Ⅰ 「クラシックの代表的作曲家と、クラシック音楽の保育・教育等の現場での活用方法について述べよ。」
音楽Ⅰ 「クラシックの代表的作曲家と、クラシック音楽の保育・教育等の現場での活用方法について述べよ。」
- 保育 社会福祉
 550 販売中 2011/02/14
550 販売中 2011/02/14- 閲覧(2,895)