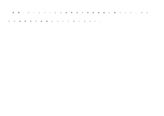連関資料 :: 教育学
資料:2,235件
-
 教育方法学1
教育方法学1
- 従来の知識伝達を重視した授業の設計と評価に対して主体的な学習を基本とする授業について設計と評価の特徴を比較し、その比較の視点毎にまとめて授業設計ならびに評価についての留意点を述べよ。 はじめに 学校教育は、国が全国一律の基準を定めて、どの地域の学校でも同じような内容と、同じようなレベルの教育を実施してきた。この系統性が高い教育課程は、順番に理解することができれば、短時間のうちにたくさん内容を習得させられ効率が良い。また、これが国全体で行われているので、国内ならどこへ転校しても学習内容が学年を超えて異なることはないという標準化の機能もある。しかし、系統性の高さゆえ、ある時点である内容を理解できないと、その後の内容の習得全体に大きな影響を与えるというデメリットもある。このような問題をふまえ、
- 子ども 教師 学習 学校 社会 学習指導要領 生きる力 評価 地域 授業
 550 販売中 2010/11/24
550 販売中 2010/11/24- 閲覧(2,057)
-
 教育方法学①
教育方法学①
- 「教育方法学」 第1設題 4枚(横書き) 従来の知識伝達を重視した授業の設計と評価に対して主体的な学習を基本とする授業について設計と評価の特徴を比較し、その比較の視点毎にまとめて授業設計ならびに評価について留意点を述べよ。 ゆとり教育が叫ばれる今日の学習形態が構築される以前は、多くの受験戦争が生徒たちの人間性を圧迫し、成長の段階で必要な多くのものが学び得ず成長しているといわれてきた。確かに、毎日勉強勉強と言われ続け尻を叩かれていた者たちからすると、ゆとり教育とは理想的な教育方法であったかもしれない。だが、いざふたを開けてみると余計な混乱が生じているようにしか思えない。学校での授業数が減少し教える時間数が足りないからといって、従来教えられていたものを教えなくなった。当然、学校の授業だけでは良い学校には進学できないからということで、余計に塾へのウェイトが増して遊ぶ時間が増えてくる。学校でも授業時間確保のため学芸会や社会見学などの行事がなくなる。本末転倒ではないかと思われる。では、新教育課程で述べられている「課題習得型学習」と「課題発見型学習」とは、以前に比べてどう変化したのか比較してみたい
- 佛教大学 教育方法学1
 550 販売中 2008/08/06
550 販売中 2008/08/06- 閲覧(2,188)
-
 教育哲学歴史学
教育哲学歴史学
- 私は不登校を「教育の二律背反問題」として考えました。多くの人は不登校という言葉に対してマイナスのイメージを持っていると思います。私自身も、不登校は絶対によくないから、がんばって学校に行かなくてはいけない、と考えていました。自分が高校生のとき学校に行くのがすごくいやでしたが、学校に行かなくては自分のこの先の人生はどうなってしまうのだろう、と不安になり、我慢をして学校に行きました。そして今はあの時がんばって学校に行ってよかったと思っています。しかし、「東京シューレ物語」という奥地圭子さんの本を読んで、不登校について肯定的に考えることもできるということを感じました。これから、不登校という問題に対する肯定派と否定派のそれぞれの意見を考えていきたいと思います。 まず、否定派の意見について考えていきたいと思います。不登校になるということは勉強などの能力が学校へ行っている子に比べて劣ってしまい、進学などの道が閉ざされてしまうので学校へ行かなければ行けないという考えがあります。また、不登校というのはただ怠けているだけだという考えもあります。社会不適応者として病気のように扱われてしまうこともあります。不登校の子どもを何とか登校させたいと思った親が精神科医などの専門家に相談すると、「それでもあなたは父親か!父として男としてだらしないから、息子が不登校になるのだ。殴っても蹴ってもいいから学校に行かせろ!」などと言われ、親は専門家の言うことだからと、自分を納得させて、先生の意見に従うことなどもあるそうです。
- レポート 教育学 不登校 二律背反 登校拒否
 550 販売中 2006/06/21
550 販売中 2006/06/21- 閲覧(1,417)
-
 教育心理学 2
教育心理学 2
- 明星大学(2013年入学・レポート) 教育学 コールバーク
 550 販売中 2014/09/08
550 販売中 2014/09/08- 閲覧(2,911)