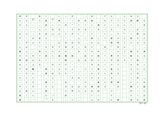連関資料 :: 文学1
資料:474件
-
 漢文学Ⅰ 分冊1
漢文学Ⅰ 分冊1
-
平成29-30年度の日本大学における漢文学Ⅰ 分冊1の合格レポートです。オールA評価をいただきました。
拙い文ですが、お役にたてば幸いです。
-
日本大学
日大
漢文学Ⅰ
漢文
教職
国語
 1,100 販売中 2018/12/04
1,100 販売中 2018/12/04- 閲覧(2,635)
-
-
 アメリカ文学史 分冊1
アメリカ文学史 分冊1
-
合格リポートです。
課題 前半でchapter 3の概要をリポートをまとめ 後半でIrvingとCooperの作品をそれぞれ実際に読んだ作品感想をまとめる 【あくまで課題は考察解釈等ではなく個人の感想なので、本レポートでは後半の内容を割愛しています】
-
日本大学
日大通信
通教
通信教育
アメリカ文学史
合格
 550 販売中 2012/03/29
550 販売中 2012/03/29- 閲覧(2,564)
-
-
 漢文学 第一設題
漢文学 第一設題
-
2019年度に合格した第一設題のリポートです。
「参考文献・引用注の記載も適切になされている。」と評価していただいたので、書き方の参考にどうぞ。
「『漢文』とはどのような文体か、古代の中国で書かれたものが現代の日本で学ばれていることも視野に入れてその定義を述べよ。」
-
佛教大学
漢文学
M5117
第一設題
 550 販売中 2020/07/28
550 販売中 2020/07/28- 閲覧(2,762)
-
-
 【日大通信】漢文学1_分冊1
【日大通信】漢文学1_分冊1
-
【日大通信】漢文学1 分冊1 合格レポートです。
H25-26年度課題「訓点および書き下し文(訓読)・漢文の基本文型について、実際の例文を挙げながら簡潔に説明しなさい」
「積極的に学習に取り組んでいることがわかるリポートです」との講評をいただきました。
参考用にお使いください。
なお、wordへの打ち込み上、漢文にレ点・一二点などはつけておりません。参考書等を確認の上、レポート作成の際は書き加えていただければと思います。
-
日本
中国
日本語
現代
古典
読書
漢文
語句
方法
意味
 550 販売中 2015/03/16
550 販売中 2015/03/16- 閲覧(2,199)
-
-
 Keith Thomas 『歴史と文学』第1章歴史と文学の要約
Keith Thomas 『歴史と文学』第1章歴史と文学の要約
-
現代、歴史研究と文学研究には深い溝がある。その歴史と文学という、ふたつの中心的な学問分野の歩み寄り、あるいは和解の提示がこの論文のテーマとなっている。
歴史学者は、文学を想像の産物だと定義付け、文学から時代のあるがままの姿を知ることは不可能に近いと主張してきた。また社会学者も、状況の真偽のわからない文学史料など歴史学者にとって無用の長物に過ぎないと主張している。さらに、文学史料は降服不可能なほどサンプリングが難しいため、文学史料にあらわれた証拠は簡単に計量化できないという経済学者の主張も存在する。このように、歴史学をより「科学的」なものにしようと努力している今世紀の歴史家は、想像の産物である文学に対して非常に冷淡な態度を表明していて、文学史料を史実として歴史に援用することなどは杜撰極まりない方法であると信じて疑わないのである。
一方現代の文学学者も、歴史の援用には好意的ではない。最近の文学批評は、作品出版当時の状況や作者の生活、読者とその反応を採りあげるいわば伝統的な研究から、現代の読者と文学作品との直接的なつながりを重視し、文学の自立性を確立する方向に傾いている。そして、文学の自立性の確立とは、文学の歴史からの開放にほかならない。20世紀初頭のロシアフォルマニストは、文学とはいわゆる外界の「現実」からではなく、文学作品間から生まれるインターテクストであり、「現実」は文学作品を理解するうえで何の役にも立たないと主張した。現代の作者と文学作品との直接的な関係を重視した彼らからすれば、文学を歴史的手法で研究することなど軽蔑の対象でしかなかった。その後、ロシアフォルマニストの後継者である「新批評派」は、文学作品とは、時代とはもちろんのこと、書いた当の本人からも独立したものであるとし、使われている形式や技法を中心に掘り下げていく手法を用いた。
-
レポート
史学
歴史
文学
フォルマリズム
 550 販売中 2005/11/13
550 販売中 2005/11/13- 閲覧(3,997)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。
 比較文学 第1設題
比較文学 第1設題
 550 販売中 2013/06/14
550 販売中 2013/06/14 Keith Thomas 『歴史と文学』第1章歴史と文学の要約
Keith Thomas 『歴史と文学』第1章歴史と文学の要約
 550 販売中 2005/11/13
550 販売中 2005/11/13 文学 第1課題 樋口一葉について
文学 第1課題 樋口一葉について
 550 販売中 2010/08/23
550 販売中 2010/08/23