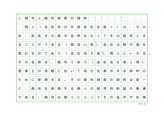連関資料 :: 商法
資料:200件
-
 寄託物の保管(商法、商行為)
寄託物の保管(商法、商行為)
- 商人が営業の範囲内で預かった品物(寄託物)の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。 商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人(商人)側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任(受領の事実だけで法律関係画当然に発生する)を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される
- レポート 法学 寄託 ホテル 場屋営業 商法
 1,210 販売中 2006/11/26
1,210 販売中 2006/11/26- 閲覧(4,018)
-
 名板貸しとテナント(商法総則)
名板貸しとテナント(商法総則)
- 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。 まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。 誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
- レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
 1,100 販売中 2006/11/26
1,100 販売中 2006/11/26- 閲覧(4,556)
-
 商人、商行為の意義と商法の特色
商人、商行為の意義と商法の特色
- 1-1 商人の意義 商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。 固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。 自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。 商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。 絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。 営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。 業とするとは、営業目的とすると同義である。 擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。 その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。 その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。 農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。 医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 1-2 商行為の意義 わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。 商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。 企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。 わが国の商法は折衷主義を採用している。 それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条) とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。 これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
- レポート 法学 商法 商法総則 商行為
 550 販売中 2006/01/25
550 販売中 2006/01/25- 閲覧(14,105)
-
 2015年日大通信教育部 商法I(商法総則・商行為法) 分冊1
2015年日大通信教育部 商法I(商法総則・商行為法) 分冊1
- 日大通信の商法I(商法総則・商行為法)分冊1合格レポートです。参考程度にとどめおきください。剽窃は厳禁です。
- 日大通信 商法I 分冊1
 550 販売中 2016/02/02
550 販売中 2016/02/02- 閲覧(1,873)
-
 商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
- 商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
- 日本 民法 企業 法律 安全 責任 権利 集団 商法
 660 販売中 2009/02/19
660 販売中 2009/02/19- 閲覧(15,335)
-
 商法・会社法 新株発行と第三者責任
商法・会社法 新株発行と第三者責任
- 第1 論点に対する判例の立場 1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。 取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。 これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。 2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。 この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。 本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
- レポート 法学 商法 会社法 新株
 550 販売中 2005/11/05
550 販売中 2005/11/05- 閲覧(1,937)
-
 日本大学通信教育 商法分冊2
日本大学通信教育 商法分冊2
- 日本大学通信教育 商法分冊2 合格レポート 取締役,監査,法律,会社法,取締役会,株式,株式会社,会計,商法
- 日本大学通信教育 商法分冊2 合格レポート
 1,100 販売中 2010/10/11
1,100 販売中 2010/10/11- 閲覧(2,774)




![[近畿大学通信教育]海<strong>商法</strong> [近畿大学通信教育]海<strong>商法</strong>](/docs/923932486193@hc20/141770/thmb.jpg?s=b&r=1599226391&t=)