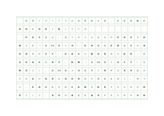連関資料 :: 商法
資料:200件
-
 日大通信 商法 分冊2
日大通信 商法 分冊2
- ご利用は自己責任でお願い致します。
- 日大通信 日大 商法
 550 販売中 2015/04/09
550 販売中 2015/04/09- 閲覧(1,493)
-
 海商法-02_(20 条の 2)
海商法-02_(20 条の 2)
- 海商法 国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。 --------------------- はじめに 国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問 題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、 19842月14日に発効している。 わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海 運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
- 海商法 国際海上物品運送法 ハーグ・ルール ウィスビー・ルール ウィスビー ハーグ 国際海上物品運送法 20 条の2
 550 販売中 2009/09/24
550 販売中 2009/09/24- 閲覧(2,451)
-
 豊田商事の金の現物まがい商法について
豊田商事の金の現物まがい商法について
- 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
- 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
 550 販売中 2008/12/29
550 販売中 2008/12/29- 閲覧(1,954)
-
 取締役と第三者−商法266条ノ3
取締役と第三者−商法266条ノ3
- 不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。 ?検討 法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
- レポート 法学 取締役の責任 損害賠償義務 善意の第三者 表見代表取締役
 550 販売中 2005/07/14
550 販売中 2005/07/14- 閲覧(4,638)