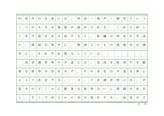連関資料 :: 国語
資料:872件
-
 国語音声学【分冊2】
国語音声学【分冊2】
- 【日大通信】国語音声学(M31400)課題2 2019~2022年度 「国語音声学」分冊2の合格リポートでございます。 「日本語の方言アクセントについて、適切な記述がなされています。」との講評を頂戴し、S評価を頂きました。 課題:以下の(1)~(5)について,番号順に記述しなさい。 (1 )日本語の方言アクセントは,大きく 4 つのタイプに分類される。どのような分類か。 (2 )自分自身の生育地(5 歳~ 15 歳の間の主たる居住地)を都道府県市区町村レベルで記し,(1)の分類ではどのタイプに分類されているか示しなさい。5 歳~ 15 歳の居住地が複数の場合,もっとも長いところを仮に生育地とすること。 (3 )生育地の伝統的な方言アクセントを,文献を用いて記述しなさい。 (4 )自分自身と,親世代あるいは子世代の 2 拍名詞のアクセントを金田一語類(Ⅰ類~Ⅴ類)に従い,記述しなさい。自分自身と親世代・子世代の年代をそれぞれ示すこと。アクセントの記述には,単語単独・助詞(格助詞ガ)付きで発音したものを用いること。 (5 )(4)において調べた親世代あるいは子世代のアクセントと自分のアクセントを比較し,そこから分かることを述べなさい。 (6)末尾の一覧に使用文献を示すこと 少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。 レポート執筆がんばって下さいね!
- 日大通信 日大通教 日大 通信 通教 リポート レポート 合格 国語音声学 M31400 分冊2 2019~2022 日本大学
 660 販売中 2020/06/26
660 販売中 2020/06/26- 閲覧(2,474)
-
 国語音声学【分冊1】
国語音声学【分冊1】
- 【日大通信】国語音声学(M31400)課題1 2019~2022年度 「国語音声学」分冊1の合格リポートでございます。 「日本語の母音と子音について、適切な記述がなされています。」との講評を頂戴し、S評価を頂きました。 課題:以下の(1)~(5)について,番号順に記述しなさい。 (1 )調音的観点に基づくと,日本語には母音とも子音とも分類しがたい音声がある。 それはどのような音声か該当するものを音声記号で示し,その理由を示しなさい。 (2 )機能的観点からみた場合,(2)で取り上げた音声は母音あるいは子音のいずれかに分類される。機能的観点の説明と,母音または子音と分類される根拠について説明しなさい。 (3 )一方,(3)の観点を導入すると,日本語には都合のよくない例がある。その具体例を,音素記号で示しなさい。 (4 )(3)の例を音声記号ではなく,音素記号で示すよう指示された理由は何か。 具体例を挙げながら,説明しなさい。なお,具体例は音声記号とともに記し,教科書に掲載されていない単語を挙げること。 (5)使用した参考文献を末尾の一覧に示すこと。 少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。 レポート執筆がんばって下さいね!
- 日大通信 日大通教 日大 通信 通教 リポート レポート 合格 M31400 分冊1 2019~2022 日本大学 国語音声学
 660 販売中 2020/06/26
660 販売中 2020/06/26- 閲覧(2,252)
-
 国語科学習指導案
国語科学習指導案
- 教育実習の公開授業、初任者の公開授業、大学・大学院の指導案提出 教科;国語 (現代文) 教科主任による、添削済み 作成者の経歴:国立の教育大学大学院終了 所有免許:中学の国語(専修免許)、高校の国語(専修免許)、他 教育実習で公開授業をされる方、初任者で公開授業をされる方、大学や大学院の講義で指導案を提出される方に向けての資料です。 ご活用ください。 国語科(科目現代文)学習指導案 <指導者> 氏名 捺印 <授業日> 平成○○年△月□日(金) 第○限 <学級> 3年3組 男子16名 女子17名 <使用教室> 3年3組 <資料> ワークシート
- 教育実習 指導案 佛教大学 玉川 玉大 通信教育 佛大
 550 販売中 2012/01/16
550 販売中 2012/01/16- 閲覧(8,256)
 1
1
-
 (教科)国語 第1分冊
(教科)国語 第1分冊
- ~漢字の成立~ 漢字は、中国語を書き表すために漢民族によって創案された文字である。現存する最古の漢字は、殷の時代後期(紀元前14~紀元前11世紀頃)のもので、甲骨文字と呼ばれる亀の甲や獣の骨に刻んだ絵文字に近いものである。甲骨文字は、次の周の時代(紀元前11~紀元前3世紀頃)で、形がほぼ一定した。周の宣王以前(前782)のものを古文といい、宣王の時に古文を一層文字化して大篆が作られた。やがて、秦(前3世紀)の始皇帝の時に、大篆を少し簡略にした字体の小篆(篆書)が作られ、また実務的な文字としてより簡略化された隷書が作られた。 さらに後漢の時(紀元後1~2世紀)に、文字を早く記するために草書が作られ、魏・晋の時代(3~4世紀頃)には隷書に基づいて楷書が作られ、また楷書を少し簡便に書いたものとして行書が作られた。 宋の時代(10~13世紀)以後は、主として楷書・行書・草書の三体が行われるようになり、日本にはこうした字体が同時的に招来され、この三字体が場面に応じて使い分けられ、現代に至っている。 紀元前一世紀に著された許慎の説文解字では、漢字の組み立てを、象形・指示・会意・形声・転..
- 国語 玉川 通信 レポート 玉川大学 第1分冊
 550 販売中 2009/11/27
550 販売中 2009/11/27- 閲覧(2,467)
-
 (教科)国語 第2分冊
(教科)国語 第2分冊
- 本レポートでは、用言のはたらきについて、分類と活用についてまとめ、その働きについて具体的に考察する。 1.用言の分類について 語の中で、自立語で活用があり、単独で述語となることができ、事物の動作・存在・性質・状態などを叙述するものを用言という。体言や副用語に対する。品詞より上位の概念で、動詞・形容詞・形容動詞がこれに属する。 動詞は、文中における位置・用法や後に続く語との関係で語形が一定の型をもって変化し、それ自体述語になるという特徴を持っている。この点は形容詞・形容動詞と共通する。 形容詞は、事物の状態・性質を現す活用語で、単独で述語や連体修飾語になる。連体形が体言と同資格で用いられる点などは、ほぼ動詞と同じ機能を持つ。 形容詞と動詞の違いは、活用の違うこと、形容詞の語幹が単独で用いられること、形容詞の連用形に副詞法があること、形容詞に接続する助動詞は動詞に比べて限られていることなどが挙げられる。 形容動詞は、機能としては形容詞と動詞との性質を兼ね備えているが、形態は異なる。この種類の語は、活用や働きは動詞的であるが、意味や職能については形容詞的であり、語幹の独立性は形..
- 玉川 通信 レポート 玉川大学 国語 第2分冊
 550 販売中 2009/12/07
550 販売中 2009/12/07- 閲覧(2,020)