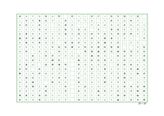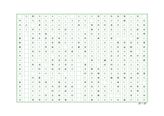連関資料 :: 日本史
資料:423件
-
 R0715 日本仏教史
R0715 日本仏教史
- 第一設題と第二設題のセット(B評価) テキスト:日本仏教史 思想史としてのアブローチ(このテキストは、まとめにくかったですね。)
- 佛教大学 歴史 佛教
 770 販売中 2011/12/05
770 販売中 2011/12/05- 閲覧(2,243)
-
 日本史 第二設題
日本史 第二設題
- 「初期会議から日清戦争にかけての政党について。」 政党とは、政治において政策や主張に共通点のある者同志が集まって、意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体のことを指す言葉である。 それでは、初期会議から日清戦争にかけての政党について考えてみたいと思う。 元来、日本に置いては、党とは、私党を意味するものであった。 また児玉党や村上党などというように武士団を呼ぶ用語であったとも考えられている。 幕末から明治維新にかけて、国内的には、「土佐勤王党」などの公論を主張した党派の誕生、対外的には欧米列強の政治体制に触れる中で議会政治における政党システムに着目するようになり、党という用語の意味が変貌を遂げる。 安政6年(1859年)福澤諭吉が英国議会を傍聴した際には、議会内では激しく論戦合戦を繰り広げていた与野党の議員が、議場の外では、和やかに談笑していることに驚いたことを紹介しており、議会政治と政党に触れた当時の日本人の視点を良くあらわしていると考えられている。 明治7年(1874年)征韓
- 憲法 日本 戦争 政治 政党 自由 政策 思想 明治 日本史 第二設題 仏教大学 初期会議から日清戦争にかけての政党について
 550 販売中 2009/02/10
550 販売中 2009/02/10- 閲覧(2,465)
-
 日本史概論分冊2
日本史概論分冊2
- 次の二問について、すべて答えなさい。 一、徳川綱吉が将軍に就任した時から寛政改革までの幕府政治の動向を概観しなさい。 二、自由民権運動の生成とその推移、明治政府の態度と憲法制定にいたる経緯についてのべなさい。
- 日大 通信 日本大学 日本史概論 日本史概説 分冊2 合格
 1,650 販売中 2014/11/18
1,650 販売中 2014/11/18- 閲覧(3,067)
-
 日本経済史 分冊1
日本経済史 分冊1
- 明治時代から第一次世界大戦までの日本はまさに、経済の見事な成長を遂げた期間であった。ヨーロッパ諸国のGNPを上回り、開国して間もない、アジアの小国にしてこれだけの成長の背景には「産業化」が挙げられる。これは、単に「工業化」だけではなく、農業や産業化に携わる人々の労働力や量産、効率化を図るとともに、会社制度への発展等の様々な分野から形成された「産業化」と言うことができるであろう。その中でも、今回は徳川時代からの伝統的な産業から大規模な明治時代以降に繁栄した産業に重点を置き、論じていきたく思う。 産業化というと、まず第一に思い浮かべるのは蒸気機関であるが明治四二年の工場通覧からは無動力のものは72%であり、日本型水車をもつものは77%であった。つまり、蒸気機関や、ガス、電気等の近代的エネルギーを動源とする工場は25%にも満たなかった。以上より、これらは在来産業に属していたと考えられる。在来産業とは明治一〇年代後に使用された言葉であるが、中村隆英によると、「原則として、広義には農林産業性を含み、狭義には農林水産業を除いた、近世以来の伝統的な商品の生産価値ないし、サービスの提供にたずさわる
- 日本大学 通信 分冊1 日本経済史
 2,200 販売中 2008/02/11
2,200 販売中 2008/02/11- 閲覧(2,124)
-
 日本文学史 設題2
日本文学史 設題2
- 明治、大正、昭和の文学の特質を、それぞれの時代の特性をふまえつつ、下記の各文学思潮を例にして説明せよ。<写実主義・擬古典主義・浪漫主義・自然主義・余裕派(高踏派)・耽美派・白樺派・新思潮派・プロレタリア文学・モダニズムの文学> Ⅰ 明治時代 「写実主義」…明治十年代の後半には、旧文学の持つ功利性を脱し、西欧近代の実情に照らした新文学を創造しようとする動きが現れた。坪内逍遥『小説神髄』を書き、文学を倫理的に規制する勧善懲悪的文学感を排して文学の独自性を掲げ、世帯人情の写実に小説の本質を求めた。逍遥の主張に感銘を受けた二葉亭四迷は『小説総論』を書き、これらの評論をもとに逍遥は『当世書生気質』を書いたが、戯作の風情調であり、自身の理論が徹底されていなかった。それらを克服して発表された四迷の『浮雲』は、最初の近代日本文学とされる。また言文一致体である。未完ではあるが、真の近代文学の起点としての史的価値は高い。さらに、四迷は『あひゞき』『めぐりあひ』といったロシア文学の翻訳をし、大きな影響を与えた。 「擬古典主義」…明治二十年代は写実主義的な近代リアリズム小説が充実し始める一方、政治における国粋
- 通信 佛教大学 日本文学史
 550 販売中 2009/02/05
550 販売中 2009/02/05- 閲覧(2,614)
-
 日本史概論 分冊1
日本史概論 分冊1
- 一 平安初期に造籍・班田は次第に困難になり、実施が試みられるも失敗に終わり、やがては全く行われなくなった。農民は、労働力として有力者に吸収され、階層化が深化していくことになった。彼等は納税を拒否し、田宅や調、庸を奪い、国司・郡司を介さずに在地社会へ介入していった。これにより、郡司による在地支配秩序を崩壊させることになり、班田農民の偽籍、逃亡による戸籍の形骸化によってもはや郡司によって行われていた地方支配機構の維持は不可能になっていた。 こうした律令的地方支配体制が変貌を遂げ始めた九世紀後半以降、中央政府は国司の権限と責任を強化することを進めた。これにより、国司の官長は一定の租税を中央政府へ納入することを義務づけられたが、地方行政に関わる全権を委譲され、前任者から国務の全権を委譲したことから受領と呼ばれることになった。これより、任国内で強大な力を持つことになった受領は中央政府の指示が無くてもその地域社会の実情に合わせて実施できた。 受領は律令的な郡司による租税収拾方式が無くなったため、新たなシステムの構築を余儀なくされた。すでに班田も行われず、形骸化した戸籍であったため、彼等は公田
- 日本大学 通信 分冊1 日本史概説 日本史概論
 2,200 販売中 2008/02/11
2,200 販売中 2008/02/11- 閲覧(2,247)