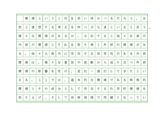連関資料 :: 保健
資料:933件
-
 精神保健学1 B
精神保健学1 B
- ライフサイクルにおける精神保健について ライフルサイクルとは、人間の誕生から死に至るまでの一生の過程をいう。 近年、人間の一生についてこのような立場で、論を展開したものがいくつか見られるが、このような考え方のきっかけを作ったのは、エリクソンであった。エリクソンは下記のような、人間の誕生から死に至る人生のサイクル段階にわけて説明した。 【第1段階】乳児期(口唇・感覚期) この時期の精神保健の課題として、母親の精神保健を健全に保つことがあげられる。つまり、母子保健が極めて重要なのである。さまざまな精神障害は妊娠末期に再発しやすくなる。軽い場合には産後10日ほどでほとんどが軽快する。出産後よく耳にする、マタニティーブルーとは、一過性の軽い抑うつ状態であり、涙もろさ、抑うつ気分、不安、軽度の知的能力低下が特徴である。原因としては、出産直後のホルモンバランスの不安定さに起因すると考えられている。このことからも、妊娠、出産、産褥は、生物学的には全く正常な営みではあるが、心理面でも、また家庭の暮らしという面でも、母親に大きなストレスとなっているといえる。 人生の最早期の発達課題は、「基本的信頼対
- 精神保健学
 550 販売中 2008/07/19
550 販売中 2008/07/19- 閲覧(2,012)
-
 母子保健の現状と今後の対策
母子保健の現状と今後の対策
- 健やか親子21の現状と今後の取り組み (1)はじめに 母子感染は、この6年間で着実に増加していることがわかった。特に、エイズウイルス、B型肝炎ウイルスが多くの関心をひいており、母子感染率としてはC型肝炎ウイルスがかなり高頻度のようだ。このウイルスは37%で垂直感染が成立しているという。垂直感染は、大部分は母子感染であり、母子感染は感染している母体から胎児は切り離すことができないので、予防が大変困難である。また、胎児や新生児は免疫力が未熟なので、ウイルスを排除することがしにくく、成人に比べ感染の影響を大きく受け、持続感染につながりやすい。 理論上水平感染に分類すべき産後の感染も見かけ上は垂直感染の様相をしている。これは全身的なケースだが、以後は歯科に関する感染について述べていくことにする。 (2)歯科に関わる感染 生まれてきたばかりの乳児の口腔内には、う蝕原因菌であるミュータンス菌は全くないと言っていいほど無菌状態である。ではなぜ、ミュータンス菌が住み着くのだろうか。実は母親の口から間接的にうつるのだ。つまり垂直感染といえる。最も母子感染しやすい時期は、乳臼歯が生えてくる頃の1歳7ヶ月~2歳7ヶ月であり、この歯には永久歯よりも深い裂溝があり、特にその部位にミュータンス菌が溜まりやすくなってしまう。また、生まれた頃にもっていた体の免疫力も低下してくる時期で、口腔内も免疫力の弱い時期となる。 Kohler B.et al,1968の調査によると、母親のミュータンス菌数と子供への感染率として約10の4乗個までは感染率は20%以下と低いが、10の5乗以上になると、約60%という高い率を出している。このデータから、母親の口腔内の管理は大事なものとなってくることがわかる。 しかし妊娠時の女性にはつわりや女性ホルモンの影響により口腔内のバランスが保てないことが多い。例えば、妊娠性歯肉炎という疾病がある。妊娠中の歯肉炎の原因は、月経時の歯肉炎とほぼ同様であり、性ホルモンの不均衡と増加が悪化させる因子として働いている。また、つわりにより歯磨きが十分にできないことも歯肉炎が出やすい原因になっている。特に前歯の歯肉が腫れる傾向にある。他にも、妊娠性エプーリスがあり、これは良性腫瘍のひとつで、歯茎が大きく膨らみコブのようになる。原因は歯肉炎の場合と同様に性ホルモンの不均衡や増加によるものと考えられている。出産後に自然となくなることがあるので、妊娠中に無理に外科的に取り除く必要はないが、出産後にも残っている場合、妊娠中であってもどうしても邪魔で仕方のない場合は外科的に切除する。妊娠時に外科的処置が必要な場合は慎重に行う必要がある。 ただこれらの症状は自覚症状がない場合がほとんどであるため、その症状を伝えてくれ、予防法や治療を推進してくれる制度が必要である。例えば、妊娠時のブラッシング指導や、どの時期に歯科治療を受けるのがよいのかなどだ。また妊婦のみの指導ではなく、生まれたばかりの乳児の歯科に関しても直接的な指導が必要であろう。それが母子保健法である。 (3)母子保健法について 母子保健法に基づく母子保健施策として、第12.13条に健康診査として妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、1歳6ヶ月児健康診査、3歳児健康診査が行われている。これは市町村単位で行われているが、都道府県単位で行われていることとして乳幼児のスクリーニング検査がある。これは先天性代謝異常がないか、またB型肝炎を患っていないかを検査するものである。 他にも第10.11.15-19条に渡って保健指導
- レポート 福祉学 健康日本21 母子保健法 感染
 550 販売中 2007/02/05
550 販売中 2007/02/05- 閲覧(4,631)
-
 精神保健福祉士 スクーリング
精神保健福祉士 スクーリング
- 精神保健福祉士 社会福祉士
 550 販売中 2011/08/22
550 販売中 2011/08/22- 閲覧(1,379)
-
 精神保健福祉士 各論
精神保健福祉士 各論
- 精神保健福祉士 社会福祉士
 550 販売中 2011/08/22
550 販売中 2011/08/22- 閲覧(1,441)
-
 精神保健福祉援助演習
精神保健福祉援助演習
- 福祉 精神 入院 退院
 550 販売中 2011/12/09
550 販売中 2011/12/09- 閲覧(2,081)
-
 保健・医療・福祉の地域ネットワーク
保健・医療・福祉の地域ネットワーク
- 今日、医療の領域では、「地域医療」という事が強調されている。これは、地域を基盤とした医療及び保健を意味しており、医療・保健を地域で進めることの重要性が再認識されている。プライマリーケアの推進、救急医療やへき地医療の確保などの地域に根ざした医療が求められている。さらに在宅ケア、在宅リハビリテーション、また医療機関、福祉機関・団体との連携・協力など、地域特性を踏まえる事が重要とされている。地域で生活している患者のための医療という観点から、早期発見、早期治療、特に高齢者の慢性疾患に対するケアや健康作りも含め、保健・医療・福祉施策の総合的な展開が重要である。 老人保健法では、「疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的」としている。老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられなければならない。 高齢者や障害者、または慢性疾患をもった人達が出来るだけ自宅や地域で療養するためには、長期的なケアを必要とし、そのためのシステムが必要となる。特に障害をもった高齢者は、ニーズが複雑化し複合的であり、問題解決が容易ではなく、各分野からの手厚い処遇を必要とする。また、ニーズは長期化するため、在宅ケアの発展、施設ケアと自宅ケアに一体化が必要となる。今後、市町村をベースにした保健・医療サービスと福祉サービスの連携によって、高齢者・障害者に対する包括的な地域在宅ケア実現のためのサービス給付体制を実現させなければならない。
- レポート 福祉学 地域福祉 福祉ネットワーク 地域医療 医療 老人保健法
 550 販売中 2005/07/27
550 販売中 2005/07/27- 閲覧(5,078)
-
 思春期精神保健対策について
思春期精神保健対策について
- 思春期精神保健対策について 思春期とは、人間の生殖機能·生理機能が成熟し、心身ともに大人になりかける時期とされており、医学的には「第二次性徴の始まりから成長の終わりまで」と定義されている。英語の「puberty」は、陰部に恥毛が生え始める時期から由来している。細かい定義は多々あるが、こうした発育の時期は、栄養状態や運動量などからも何歳あたりからとは必ずしも一定しない。個人差にもかなり左右される。そのため、生涯発達の発達段階の中には思春期は組み込まれていない。 さて、急速な身体的成長と第2次性徴の発現が認められる思春期は、異性への関心が高まり、同時に自我の確立が求められ、反抗期などが生まれ
- 発達 思春期 東京福祉大学 精神保健 第二次性徴
 550 販売中 2009/07/28
550 販売中 2009/07/28- 閲覧(2,822)
-
 職場における精神保健活動の実際について
職場における精神保健活動の実際について
- 職場における精神保健活動の実際について 現代社会において、人々は多くのストレスを抱えている。何に対してもやる気がない、興味が持てなくなった、会社や学校でうまくやっていけない、身体的に不定愁訴がある、などといった経験は誰にでもあり、多くの心の問題となっている。そこで、人々が社会の中で健康的に生活できるよう、精神保健活動が注目されるようになってきている。では、職場における精神保健の活動とはどのような立場にあるかについて考えてみたい。 働くということは、生活費を得ると同時に、人としての存在を保証する手段でもあり、人間の発達を保障する基本的条件でもある。労働なしには生活はあり得ないし、労働によって人間は自己を変革し発達することができる。 しかしその反面、近年の長引く不況、大量リストラ、終身雇用制の崩壊、急速な技術革新の進歩等に伴う労働条件の変化により、過度のストレスが加わり、職場不適応症として就業への不安、緊張、恐怖、焦燥感、抑うつ感やうつ病などの心の病が出現するなど、精神的な面で大きな影響が出ている。そこで職場における精神保健活動は、そのような精神的健康の病気を予防・治療し、人々が健
- 東京福祉大学 精神保健 現代社会 ストレス
 550 販売中 2009/07/28
550 販売中 2009/07/28- 閲覧(2,483)