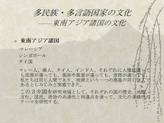連関資料 :: 民族について
資料:37件
-
 多民族・多言語国家の文化
多民族・多言語国家の文化
- マレーシア、シンガポール、タイ国。 マレー人、華人、タイ人、インド人、それぞれに人種は違っても民族が違っても、風俗や風習が違っても、言語が違っても、私たちは同じ人間であり、地球という一つの惑星の同じ住人であるとしみじみと実感できた。 文化とは、社会構造と対比する場合は、生活の様式や行為のパターンを統御するものと考えられている。文化は、必ずしも見えない文化、意味の体系、経験を秩序づける枠組みの類を指すものではないと思われる。ここでは、文化というカテゴリー自体が曖昧であり、表象化された文化に何を含ませるかは、必ずしも社会の合意はないようだ。 私がこの論文であげた文化とは、いわゆる芸術などの、見える文化ではなく、庶民の日常的にこびりついた彼らの概念とか文化に潜む構造・動態を主眼とした。私は東南アジアのマレーシア、シンガポールそしてタイを例にしたが果たしてこの東南アジアに共通基層文化が存在していたのだろうか。言語的な類縁関係をたどっていても、共通祖語を考えることは不可能とされている。東南アジアの種族分布はモザイクのように入り混じり、種族の多様性からみても、東南アジアに共通する文化があり得るとは考えない考えないのが普通であろうか。東南アジアの歴史からみても、移民文化の宝庫とも言える地域性をもっているが、移民たちは移住した土地に根付いた既存の文化より移民がすてた自分らが生まれ育った土地の伝統社会や伝統文化にこだわりを持っていた。いや、けっして捨てがたい存在であったはずである。それは、伝統社会を支えてきた先祖伝来の規範であるからだ。 この3カ国を研究地域として、それぞれの国の歴史、地理、文化、国民、政治の共通性と相違点を通って、文化の多様性のテーマを研究する。
- 論文 国際関係学 異文化 多民族 タイ国 シンガポール マレーシア
 550 販売中 2005/07/19
550 販売中 2005/07/19- 閲覧(2,940)
-
 多民族文化アメリカ試験答案
多民族文化アメリカ試験答案
- 文化 社会
 550 販売中 2011/02/09
550 販売中 2011/02/09- 閲覧(1,058)
-
 中国少数民族と漢族における共通話について
中国少数民族と漢族における共通話について
- 中国は漢族と55個の少数民族からなる多民族国家である。朝鮮族はその55個の少数民族の中の一つである。朝鮮族は中国国内で独自の言語(朝鮮語)を持っていながら漢族との接触を求めて「普通話」を習っている。つまり朝鮮族と漢族の接触における共通語は北京語(関話)を基準とする「普通話」である。ここでは、朝鮮族の起源、少数民族地域における言語教育、今日の共通語使用に至るまでの変容などを踏まえながら、朝鮮族自治州における共通語(普通話)の実態について述べていく。 1.朝鮮族の起源と今日 朝鮮族は元々中国に居住していた民族ではない。清の時代、朝鮮では農村が疲弊して多くの農民が豆満江を越えて満州(現在の東北地区)に入り込んだ。その後、朝鮮は日本に殖民地化され、土地を失った朝鮮農民が満州に流亡し始めた。1932年満州国が成立すると新天地を求めて満州に渡る朝鮮人がさらに急増した。このように生計を維持するために中国に入り込んだ朝鮮人が当時は300万人もいたと言われている。満州国の崩壊と朝鮮の解放によって多くの朝鮮人が帰国し、約100万人が中国に残留したが、これが今日の朝鮮族の起源となった。 中国共産党は建国後、1952年民族区域自治実施要綱を発表し、55の少数民族に自治権を付与した。このような民族保護政策があって、現在中国国内には朝鮮族が約200万人も住んでいる。居住分布を見ると、東北地区(旧満州)に集中しており、中でも吉林省に約120万人が住んでいる。吉林省南部には延辺朝鮮族自治州が誕生されており、首府延吉市には中国語と朝鮮語で教育する延辺大学も設置されている。 ここまで朝鮮族の起源と今日について述べてきたが、そもそも朝鮮人が中国に入り込む当時は「普通話」という共通語がなかっただろう。共通語がない当時はどうやって現地の漢人たちに自分の意思を伝達しただろう。
- レポート 語学 共通語 民族接触 同化 朝鮮族 中国少数民族
 550 販売中 2005/07/27
550 販売中 2005/07/27- 閲覧(2,368)
-
 近代国家とは何か 立憲主義から民族国家の成立まで
近代国家とは何か 立憲主義から民族国家の成立まで
- タイトル:立憲主義から民族国家の成立まで はじめに このレポートでは、立憲主義の考え方を機軸として、民族国家(nation-state)について近代国家論の立場から考察する。具体的には、立憲主義を概略し、民族国家が成立するまでの過程を簡単に整理する。 立憲主義から何が出てくるか 立憲主義(constitutionalism)とは、憲法によって何らかの統治を行おうとする立場である。この立憲主義には、一般に基本的人権の尊重や権力の分立が含まれている。立憲主義の成立については、さまざまな説明が可能であるが、近代以前の身分制社会における限界を克服する手段として出てきた、あるいは、ホッブズの言うような自然状態を仮定することにより、その自然状態における「万人の万人に対する闘争」を解消する手段として出てきたと考えることができるだろう。以下では、このような立憲主義の理解に基づき考察を進めていくことにする。 さて、このような立憲主義の考え方からはどのようなもの結果として出てくるであろうか。たとえば、特定の身分や民族が優遇されるような憲法典について考えてみよう。このような憲法を制定することは、階級闘争や
- レポート 哲学 近代 国家 歴史 民族 立憲
 550 販売中 2007/10/12
550 販売中 2007/10/12- 閲覧(2,885)
-
 「単一民族神話の起源」に見る人類学者と植民地の関係
「単一民族神話の起源」に見る人類学者と植民地の関係
- 第1章 はじめに 「単一民族神話の起源」の中に書かれていた日本の人類学者と植民地との関係を日清戦争から日韓併合までの時期と日韓併合から後の時期の二段階に分け、優生学者の思想についても取り上げながら述べていきたい。 第2章 混合民族論の発達 まず人類学者が植民地支配と関わってくるのは日清戦争から日韓併合までの時期である。この時期に講義でも取り上げられた坪井正五郎をはじめとする人類学者が混合民族論の発達の基礎を作った。まだ人類学が草創期であったため単純な容貌判定が根拠とされることもあったが、人類学者の日本民族起源論は半島を通ってきた大陸系、南方から渡来したマレー系、そして在来のアイヌ系などの混合が日本民族であるという混合民族論でほぼ一致していた。鳥居龍蔵も容貌判定を根拠に学説を立てた一人だが、彼にとって日本民族のルーツ探しでもあって度々行われた遼東半島や台湾、韓国などでのフィールドワークは調査地とその時期が大日本帝国の膨張と一致しており、また依頼者や渡航手段の面でも軍や朝鮮総督府と関係があり、政治との深い結びつきが見られた。 また坪井も新興学問である人類学の社会における理解や人材そして予算を獲得するために、人類学が国家の政治にも役立つということを強調する必要があり、混合民族論の政治的応用法を次々と生み出していった。坪井は大日本帝国内の異民族の存在にも自覚的で北海道でのアイヌの調査などを行い、日本を単一民族国家として日本民族の統一と純潔を主張する国体論者の加藤弘之らとは対立した。坪井は文明の発達や進歩は異なる者どうしの競争や交流によってこそ生じるものであって日本は多民族国家であるがゆえに発展するのだと述べた。また、純血を守るためには異民族を隔離するしかないと主張し、それに反対してアイヌや台湾の人々を共に日本人として共存させようと唱えた。しかしアイヌや台湾の人々は自らの意思ではなく強制的に編入されたのであって、坪井が寛容さと多様さを説くことも結局は併合状態の追認であった。
- レポート 日本の人類学者 植民地政策 民族起源論
 550 販売中 2005/10/19
550 販売中 2005/10/19- 閲覧(2,101)
-
 東西交流の観点から見る日本における国名・民族名の受容史
東西交流の観点から見る日本における国名・民族名の受容史
- 国際関係研究I / II 6 Feb 2007 東西交流の観点から見る日本における国名・民族名の受容史 I. ペルシャ・イラン ペルシャという国の存在は、日本では古くから認識されていた。 最古の可能性としては、 親王(676-735)の執筆になる「日本書紀」巻第二十六において、斉明天皇(594-661)のころに「 」という外国人が再来日を約束して帰国したという内容のことが書かれているものがあげられる。イラン学者・伊藤義教はこの外国人を、イラン奪回作戦の援助を乞いに来たペルシャ人の王ダーラーイであると主張している。 また「宇津保物語」(平安中期)俊蔭巻には、「波斯国」に漂着した俊蔭という人物の冒険物語を描いているが、これは「波斯」をそのまま「ハシ」と音読みしたと考えられている。中国の「梁書」には「波斯」伝があり、日本にも中国からその知識とともに「波斯」の表記が伝えられたらしい。 近世になってハルシャという風に呼ばれるようになる。「増補華夷通商考」(1708)四には「ハルシャ 百爾斉亜(ハルシャ)婆羅遮国 日本より海上五千五百里。南天竺の西辺也」などという記録が残されている。また、朱子学者・新井白石(1657-1725)の「西洋紀聞」(1725頃)中には、「ハルシャ、〈漢に巴爾斉亜、また巴皃西と訳す。我俗にハルシャといふ、此也〉インデヤの西、アフリカ地方の東につらなれり」とある。 さらに19世紀になって、「ペルシャ」の表記が登場する。渡辺崋山(1793-1841)の「外国事情書」(1839)には「右は皇国・唐土・天竺・ 〈略〉等の国に御坐候」との記述があり、「異人恐怖伝」(1850)序には「 ハルシャなり」という説明が見られる。 「日本国語大辞典」はこれらの「ハルシャ」の読みは、オランダ語Persiaから来ているとする。 「波斯」や「ペルシャ」の語源は、現在のイランのことが古ペルシア語(OP)でPārsaと呼ばれていたことにさかのぼるだろう。現在のペルシア語では
- 日本 日本語 英語 イギリス ドイツ インド 言語 問題 ギリシャ 思想 言語学 国際関係学
 全体公開 2007/12/05
全体公開 2007/12/05- 閲覧(2,265)
-
 アメリカ合衆国の移民の流入過程を説明し、最近の民族構成の変化について述べなさい。
アメリカ合衆国の移民の流入過程を説明し、最近の民族構成の変化について述べなさい。
- アメリカ合衆国の移民の流入過程を説明し、最近の民族構成の変化について述べなさい。 アメリカは国民のほとんどが移民とその子孫から成り立つ他民族国家であるが、はるか昔は先住民が狩猟や農耕生活を営んでいた。そこに、16世紀以来、西ヨーロッパから人々が移住し、またアフリカからカリブ海地域を経由して大勢の黒人が連れてこられ、南部のプランテーションに労働力として輸入された。この強制労働は1863年の奴隷解放宣言によって停止する。19世紀後半からは、ヨーロッパ東部や南部からの移住者が増え、また中国人や日本人の移住もはじまった。20世紀以降、中南米やフィリピンの移住者、戦争などによる難民も加わり、人種的・民
- アメリカ 社会 差別 問題 ヨーロッパ 労働 運動 民族 移民 黒人 民族構成 佛教大学 佛大 科目最終試験
 550 販売中 2009/05/10
550 販売中 2009/05/10- 閲覧(2,688)
-
 ニュ-ジーランドとアメリカ合衆国の開発の歴史、民族構成、政治・経済状況について共通点と相違点を比較しつつ説明しなさい。
ニュ-ジーランドとアメリカ合衆国の開発の歴史、民族構成、政治・経済状況について共通点と相違点を比較しつつ説明しなさい。
- ニュ-ジーランドとアメリカ合衆国の開発の歴史、民族構成、政治・経済状況について説明しなさい。 ニュ-ジーランドとアメリカは、それぞれイギリス植民地として出発した。両国はイギリスの市場となり、かつ支配と搾取を受け、農産品をヨーロッパ市場へ輸出することによって経済力を強めた。アメリカではその政策に対する不満が噴出し、13州の結束と独立戦争の勝利によって自立国家への道を歩むこととなる。一方、ニュ-ジーランドはイギリスへの忠誠心が厚く、貿易の多くを依存していたため抵抗運動はなく、1907年に国内自治権を得、1947年にはイギリス連邦内の独立国家となった。 両国とも白人の入植以前、先住民は土地を共同
- 歴史 アメリカ 経済 イギリス 国家 アジア 運動 民族 権利 市場 佛教大学 佛大 科目最終試験 ニュ-ジーランド 共通点 相違点
 550 販売中 2009/05/10
550 販売中 2009/05/10- 閲覧(2,421)