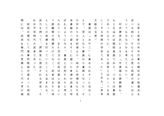代表キーワード :: 日本文学
資料:184件
-
 夏目漱石のこころを読んで
夏目漱石のこころを読んで
- 『こころ』は、「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」の三部にわかれて、1つの作品を構成している。「先生と私」では「私」が一人称であり、私は「先生」と出会い、先生の思想や暗い部分に触れることによって、先生の過去などの謎を提起する部分である。先生の思想や発言にはた...
 550 販売中 2006/03/13
550 販売中 2006/03/13- 閲覧(9,311) コメント(1)
-
 粋・格好よさ・美しさ
粋・格好よさ・美しさ
- まず、今回の課題の一つである「粋」とはどのような言葉で、どのような時に使うのだろうか。「粋」という言葉を聞くと、江戸っ子というイメージが強い。時代劇を見ていると、粋という言葉が何回か出てきた記憶がある。それは、「め」と背中に書かれた半纏をはおり、ねじり鉢巻をし...
 550 販売中 2006/06/28
550 販売中 2006/06/28- 閲覧(1,808)
-
 阿部公房『砂の女』存在を模索する男
阿部公房『砂の女』存在を模索する男
- 「存在を模索する男」 ―阿部公房『砂の女』を読んで― 【1】文体の特質 まず目に付くのが、丁寧な描写である。非現実的な世界では特にその必要性がある。読者に砂の部落のことを伝えるために丹念に描かれている。それに加え、例えも多用していることでより綿密な世界を創ってい...
 550 販売中 2006/11/29
550 販売中 2006/11/29- 閲覧(2,725)
-
 芥川龍之介の『神神の微笑』をキリスト教的視点から考察する。
芥川龍之介の『神神の微笑』をキリスト教的視点から考察する。
- 芥川龍之介『神神の微笑』とキリスト教 初めに、『神神の微笑』は日本文化に根付いている”微妙で曖昧な”内的側面が見事に表現されている素晴らしい作品だと思い、感心しました。少なくとも私は芥川氏の宗教観を受け容れます。 この物語は、布教のためにポルトガルから単身で渡来...
 550 販売中 2007/09/26
550 販売中 2007/09/26- 閲覧(4,976)
-
 ゲッティンゲン大学7教授事件と第一回ゲルマニスト会議の報告と主張
ゲッティンゲン大学7教授事件と第一回ゲルマニスト会議の報告と主張
- 時を経て1830年、グリム兄弟は共にハノーヴァー王国のゲッティンゲン大学の教授となっていた。 1837年、ハノーヴァー王国を支配していたヴィルヘルム4世が死去すると、代わってその弟のアウグスト2世が国を支配することとなる。しかし、アウグストは1833年に兄ヴィ...
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03- 閲覧(1,313)
-
 公家と武家の年中行事の類似点と相違点
公家と武家の年中行事の類似点と相違点
- 公家と武家の年中行事の類似点と相違点を述べる前に、そもそも公家と武家の違いはどういうものなのかを考えてみたい。 村井康彦氏によると「平清盛も源頼朝も、もとを辿れば賜姓皇族であり、つまりは貴族であったように、公家と武家とはルーツを同じくする同根の存在であった」と...
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03- 閲覧(1,320)
-
 高杉 良著 「あざやかな退任」
高杉 良著 「あざやかな退任」
- この本は、一流パーツメーカーの東京電子工業のワンマン社長石原が朝の常勤役員会になっても来なくて、心臓麻痺で急死していた場面からはじまる。社長が急死したので、次の社長が誰になるかを決めなければいけない。社内外からは、長年に亘り石原を支えてきた宮元副社長が後継と目...
 550 販売中 2005/11/09
550 販売中 2005/11/09- 閲覧(2,099)