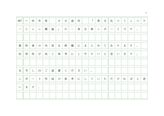連関資料 :: コミュニケーションについて
資料:260件
-
 「コミュニケーションと表現 期末レポート」
「コミュニケーションと表現 期末レポート」
- 私がこの授業をとったきっかけは、ちょうどこの時間が空いていたことと、後輩に誘われたという、きわめて単純なものでした。コミュニケーションということに関しては、とりたてて周囲の人たちとのやりとりに困ることはなかったですし、初対面の人と話をするのは緊張するという程度でした。4月や5月頃の授業では、ボール遊びなどをしていて、これがどういうふうにコミュニケーションと関わってくるのかよくわかりませんでした。しかし、ドミンゴの先生がアメリカからいらっしゃったときは、失敗を恐れずにいること、また、失敗は恐れるようなものではないということを教わったような気がします。ことコミュニケーションということに関してはこれが大事なのではないかという気もしました。この授業では他の授業とは違って、同じ授業をとっている人と話す機会が多かったので、失敗を恐れずにもっと知らない人と仲良くなる努力をしておけばよかったというのは、いま思っていることです。
- レポート コミュニケーション 表現 対話
 550 販売中 2006/01/31
550 販売中 2006/01/31- 閲覧(1,470)
-
 インターネット上での言語コミュニケーション
インターネット上での言語コミュニケーション
- インターネット上での言語コミュニケーション はじめに 本稿は、近年のインターネット上での特殊な言語コミュニケーション現象について、分析し、インターネット上でのコミュニケーションにおける言語表現がどのような意味や側面を持つのか、ということをコミュニケーション研究の視点から考察する。本稿での言語表現とは、2chなどの掲示板、ブログやmixiなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、メール(携帯電話でのメールも含む)の中で使用されている特殊な言語表現を扱うものである。これらの言語表現は新聞や書物のような堅い文章ではないため、日常生活の会話をそのまま文字として打ち込んだ口語と言えるだろう。次に、私が注目した言語表現を例を列挙していく。 表現例 語尾に何らかの記号などを付与し感情を示す。 ex) …(笑)、…(汗)、…(爆)、…(泣)、…w、など 顔文字、絵文字を使用し、感情などを表す。 ex) (;´∀`) (/Д`)~゚。 ( ・∀・)ノ など 同じ集団に属する者にしか理解できない表現を使用する。 ex) 「半年くらいROMってから来い」 Read Only Member(リー
- コミュニケーション 社会学 言語 インターネット
 550 販売中 2007/12/21
550 販売中 2007/12/21- 閲覧(2,048)
-
 社員のコミュニケーションから生まれる作用について
社員のコミュニケーションから生まれる作用について
- 最近では、ナレッジ・マネジメントが多くの企業で導入されています。しかし、このナレッジ・マネジメントが企業に導入された後に起こる問題として,社員がこのシステムをあまり活用しきれていない、というのが現状です。この原因には、導入された後にある、社員の持っている知識を登録するという作業が困難になってしまっている、という事が挙げられます。この作業が軽減される事になれば、今まで以上にナレッジ・マネジメントを利用していく企業が増える、ということに繋がっていくのではないか、と考えられています。
- レポート 社会学 社員 知識 経営方針 情報継承
 550 販売中 2006/07/19
550 販売中 2006/07/19- 閲覧(1,190)
-
 コミュニケーションを阻む9つの壁
コミュニケーションを阻む9つの壁
- コミュニケーションを阻む9つの壁を示し、それぞれについて概説しなさい。 生活背景・経験が大きく異なることからくる壁 年代、生活経験、生活歴などによる違いにより、相手の立場から物事を見ることができず、それが壁となりコミュニケーションを阻む。 人間を枠にはめてみることからくる壁 “ハロー効果”によって相手を“思いこみ“の枠にはめてみることによって自分の中の偏見に気付くことができず、それが壁となりコミュニケーションを阻む。 ※ ハロー効果:ある人の一面で優れている(劣っている)と、その人が他の面でも優れている(劣っている)とみなす傾向。 シンボル的用語理解の相違 「送り手」と「受け手」の使っているシンボル的用語の意味に違いが起きることによって、同じことを話しているつもりが全く別のことを話しているというというようなことが起き、それが壁となりコミュニケーションを阻む。 一般用語と専門用語 専門用語を使うことによって素人が自分の理解にとどまり、誤解が生じ、コミュニケーションを阻む。 言葉以外の非言語的なシンボル 自分では気づいていない“癖”によって思いがけない誤解を招くことがあり、それが壁となりコミュニケーションを阻む。 一方通行のみのコミュニケーション 一方的な指示や忠告だけになってしまいがちになることによって、相手の理解が不十分になってしまい、コミュニケーションを阻む。 狭くて柔軟性のない見方 分からないことを分からないままにしてしまう“柔軟性のなさ”は思いこみにつながり、コミュニケーションを阻む。 早とちり、早合点 一人でさっさと結論を出すと、相手の言うことをよく聞かずに返事をすることとなり、コミュニケーションを阻む。 注意散漫の時 コミュニケーション能力が互いに落ちていたり、身体的に不快であったりして集中できていないと、相手の話がきちんと聞けないので、コミュニケーションを阻む。 患者と看護師の人間関係はどのように構築されるのか説明しなさい。 患者と看護師の人間関係は①関係確立の段階②関係発展の段階③関係終焉の段階というプロセスをたどり構築される。これら患者と看護師の人間関係はある状況・場所・時間の中で築かれる。 ①関係確立の段階では、例えば、心地よい看護行為を提供することによって患者は安心し、対話の中で傾聴・共感・肯定的な配慮・看護師の暖かい気持ちに触れることによって患者は一人の価値ある存在として受け止められると感じ、信頼の心を看護師に向け、患者は緊張や不安が緩和される。このような関係性のなかで、看護師と患者が互いに相手を知り合おうとし、患者と看護師の人間関係は構築されていく。 ②関係発展の段階では、看護師は患者が可能な限り高いレベルの健康を獲得できるよう、患者が自信の問題に関心を寄せ、どのような問題か明らかにできるよう援助し、問題の明確化をすることで、目的の共有をし、お互いの信頼を高めていく。 ③関係終焉の段階では、患者が問題解決に向けて主体的な行動をとっていく見通しを描くなかで、援助の終焉を演じる。 このように患者と看護師のコミュニケーションには、友人や家族とのコミュニケーション以上のものが要求さる。上記のような信頼関係を互いに結び、患者が自分自身を一人のかけがえのない存在とみることができ、看護師が一人の人として患者と接することができたとき、治療的人間関係は構築され始めるのだと思う。 自己効力感について説明しなさい。 自己効力感とは、何らかの課題を達成するために必要とされる技能が効果的であるという信念を持ち、実際に自分がその技能を実施することがで
- レポート 医・薬学 成人看護学概論 コミュニケーション 自己効力感
 550 販売中 2006/12/26
550 販売中 2006/12/26- 閲覧(5,195)
-
 英語コミュニケーション 第一設題
英語コミュニケーション 第一設題
- 佛教 佛教大学 リポート レポート
 550 販売中 2012/11/12
550 販売中 2012/11/12- 閲覧(1,494)
-
 英語コミュニケーション第二分冊
英語コミュニケーション第二分冊
- 玉大 玉川大学 通信 教育 教員
 990 販売中 2010/10/19
990 販売中 2010/10/19- 閲覧(1,055)
-
 英語コミュニケーション 第1設題
英語コミュニケーション 第1設題
- (1)『テキストの第一章“The Americans”から第六章“The Chinese”までを読んで、それぞれの内容に関する自分の意見を日本語で述べなさい。』 ★第1章「THE AMERICAN」★ 多くの人々がアメリカに行きたいと思ったり、アメリカの真似をしたいと思ったりするのは、それだけアメリカが魅力的であるからだろう。「アメリカンドリーム」という言葉があるように、アメリカには沢山の可能性が溢れているような気がする。 アメリカは個人主義の国である。周りに流されることなく自分の考えを表現できる点が個人主義の素晴らしいところであると思う。日本のように周りの雰囲気を大事にする風潮があると、
- 英語 英語コミュニケーション アメリカ イギリス フランス イタリア ドイツ 中国 people are funny 佛大 佛教 佛教大学
 550 販売中 2008/01/08
550 販売中 2008/01/08- 閲覧(2,170)
-
 ひとりひとりのマインドを大切にする組織コミュニケーションとは
ひとりひとりのマインドを大切にする組織コミュニケーションとは
- 1. 序論 従来企業は組織の目標のために個人を職制上のオーダーで管理し、雇用された者はそのオーダーに忠実であればあるほど、優等とされた。そのため、管理者は組織内のばらけた思想や考えを持つ個人を、組織の組織目標達成・生産性向上などの目標のために変容させる仕組み、いわゆるマインドセットなどを試みた。たとえそのオーダーの中身に社会性がなかろうとも、職制秩序に従うことが正しいとされてきたのである。 しかし今求められているのは、このような企業組織のために個人を犠牲にする「自己犠牲」⁽¹⁾タイプではなく、個人個人の主体性を尊重した、「自己充足」⁽¹⁾のための企業である。藤江俊彦氏は著書で次のように述べる。 「『自己犠牲』から『自己充足』ということは、経済的単一価値の企業人から生活市民の自覚にめざめ、個人の多元的価値を活かしていくということである。企業というのは、そうした個人の個性や持ち味を発揮する場であり、今後はこれからの個の自由な力をうまく収束し、質的な成長を期すべき存在になりつつある」⁽¹⁾ そして企業はこのために、人を雇用するだけでなく、ひとりひとりの個性をいかに発揮しやすいように条件づくるか、という役割を担っていくのだ。 2. コミュニケーションの活性化 このためにある方策が、社内コミュニケーションの活性化である。 2.1. コミュニケーションとは そもそもコミュニケーションとは、「一連の共通ルールに従い情報を分かち合うプロセス」⁽²⁾である。ここで言う共通ルールとは、両者が意味の共有をするための基底にあるもので、例えば同業者同士の話し合いの場合はその業界で用いられる専門用語や学術用語を用いることなどである。そしてここで何より重要なのは、コミュニケーションが「分かち合うプロセス」であるということであり、それでこそ上記の「自己充足」の手段として用いるに値する。
- レポート 総合政策学 組織 企業 コミュニケーション
 550 販売中 2006/03/15
550 販売中 2006/03/15- 閲覧(2,001)
-
 英語コミュニケーション本文和訳①
英語コミュニケーション本文和訳①
 550 販売中 2009/11/26
550 販売中 2009/11/26- 閲覧(895)
-
 英語コミュニケーション本文和訳②
英語コミュニケーション本文和訳②
 550 販売中 2009/11/26
550 販売中 2009/11/26- 閲覧(901)