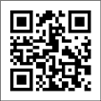連関資料 :: 国際関係
資料:42件
-
 国際関係学レポート
国際関係学レポート
- 国際関係学 レポート 吉田 茂-尊皇の政治家- 第1章 人生草創-維新の激流に生る- 明治11(1878)年9月22日に吉田茂は生を受けた。その年は西南戦争終結1周年であった。前年(明治10年)2月から7ヶ月にわたって世上を漬乱し、維新政権を震撼させたあの西南戦争は、西郷隆盛の自刃をもって終わった。その4年前の明治6年、参議西郷隆盛らの征韓論が、欧米訪問から帰国したばかりの岩倉具視(右大臣)、大久保利通(参議)らの猛反対に遭って敗北、これを機に西郷はじめ板垣退助、後藤象二郎、江藤新平ら政府中枢の人びとが下野した。この政権分裂の一大事こそ、まさに西南戦争に連なる歴史のひとこまとなるのである。 吉田茂が現し世に生まれ落ちたその日は、新生日本がまさに西南戦争の余燼にまみれつつ国家と天皇の守護を旧特権階級の武士層にではなく、農工商を含む「天下万民」に託そうとしたその秋でもあった。国家近代化の波に洗われて急速に没落していく旧武士層の経済的窮状はもの哀しくもあった。士族が妻子を飢えさずに生計を立てる道があるとすれば、彼らの軽蔑する商人、工人、農民になるほかはなかった。 吉田茂は、竹内綱を父とし瀧子を母とする7男7女の5男として東京に産している。茂が竹内姓から吉田に改姓されたのは、茂が生まれて間もなく綱の親友吉田健三の養子として転籍したからである。つまり吉田茂にはそもそも2人の父親がいたことになる。いや、後年茂の岳父となる牧野伸顕を加えれば、吉田の父は3人を数えることになる。しかも、これら3人の父親が吉田の人生に落としたその影は、長くそして濃密である。実父竹内綱が吉田にその血脈と天賦の資質を与えたとすれば、養父吉田健三は茂に訓育と莫大な資産を給した。そして、明治の元勲大久保利通の次男すなわち牧野伸顕は、女婿吉田茂にいわば栄達の閨閥と権力の強縁を供した。 竹内13代目の当主竹内綱は、土佐藩重臣伊賀家の家臣であった。綱は伊賀家歩兵の伍長から始まって弱冠20歳で重役になり、文久2年、23歳で目付役を命ぜられている。版籍奉還(明治2年)とそれに続く廃藩置県(明治4年)を経て明治国家体制はいよいよその起点を固めていくが、それとともに竹内の活躍舞台が大きく広がったことは事実である。とくに実業家としての彼の行動は際立っている。後藤象二郎主宰の蓬莱社から高島炭坑(長崎県)の経営を任されたのが明治7年、竹内の事業欲は何も炭坑開発に限られてはいなかった。鉄道経営には彼のビジネスの最たるものであったといってよい。明治27年、竹内は朝鮮視察後、尾崎三郎らとともに政府に対して京釜・京仁の2つの鉄道敷設計画を提議している。ここで重要なのは竹内のこうした実業家としての行動が、実は彼の政治的な行動と蜜に絡んでいたということである。例えば前記京釜鉄道の経営権を竹内が得ることについては、彼らなりの国家的使命感とともに、利権にかかわる種々の政治的配慮が蠢いていたといってよい。竹内のこうした政商的な顔は、彼のすべてを語っているわけではない。実業家竹内のキャリアは、彼のいま1つの顔、すなわち国家揺藍期にあって「国のかたち」を追い求める政治家竹内綱の面目と重ねてみる必要がある。竹内が江戸最末期の若い頃から国の行く末を案じ、政治に並々ならぬ関心を抱いていたことは間違いない。彼は攘夷論渦巻く文久3年、24歳のときに高知で後藤象二郎と初対面し、たちまち彼とは心腹の友となる。両人が攘夷反対、朝廷・幕府間の「調和」、国内物産開発と貿易振興、ボルネオ・スマトラなど南洋未開地への
- 国際関係学 吉田 茂-尊皇の政治家-の要約
 1,650 販売中 2007/12/12
1,650 販売中 2007/12/12- 閲覧(2,391)
-
 国際関係論の変化
国際関係論の変化
- 1.はじめに 近現代の国際関係を説明する理論には、様々なものがある。それらの中でも現在主要なパラダイムとして用いられている(ネオ)リアリズム、(ネオ)リベラリズム、コンストラクティヴィズムの三つの理論・考えに着目し、それぞれの概要と変化の流れ、問題点をまとめた。 2.リアリズム【現実主義】:概要と背景 リアリズムとは、「国益を追求する複数の国家が、安全保障のため絶えず権力をめぐって対立するのが国際社会である」という前提の下成り立っている考えである。この前提の根拠は、ツキディデスの歴史的実証、マキャベリやホッブズの理論展開にある。 リアリズムでは国際関係のアクター(行為者)を、絶対的自立性・同質性を持った「(主権)国家」としている。こうした国家間の国際関係は、諸国家の上位に立ち権力でまとめあげる存在のいない無政府状態、ホッブズの言葉を借りると「万人の万人による闘争」状態である。そこで、各国家は安全保障のため、勢力均衡(Balance of power:国家間の勢力の釣り合った状態)の原理に従って国際関係におけるパワー(軍事力)を調整する。 リアリズムが主要なパラダイムとして台頭してきた
- レポート 国際関係論 リアリズム リベラリズム コンストラクティヴィズム 構成主義 constructivism
 550 販売中 2008/11/18
550 販売中 2008/11/18- 閲覧(5,224)
-
 国際私法 養親子関係
国際私法 養親子関係
 2,200 販売中 2010/12/07
2,200 販売中 2010/12/07- 閲覧(1,488)
-
 安全保障をめぐる国際関係
安全保障をめぐる国際関係
- 序論 安全保障とは、一般的に「国家が外敵からの侵略に対して、軍事力を持って自国の領土を守ること」と定義できる。しかし、国家が守るべきものは領土だけではなく、国益や国民の利益におよぶのもでなければならない。そこで、安全保障をもっと広義に定義すると「国家などが国益や国民の利益を、何らかの方法で、それを侵害する脅威から守る」となるが、これでは実態としてなにが安全保障なのか理解しづらい。これから説明していくことは、まず安全保障の概念を知る上での国際関係、次に安全保障のあり方、三番目に現実の安全保障政策、四番目に日本における安全保障政策、そして最後にそれらを踏まえての結論である。 第一章 ここでは安全保障を考える上で最も重要だと考えられるリアリズムとリベラリズムについて述べていく。リアリズムとは、簡単にいえば性悪説のことである。十\七世紀のイギリスの政治哲学者ホッブズは、人間は本質的に利己的であり充足されておらず、自己の生存を確立するために他者の物を奪おうとする結果、人間同士に論争が生じると考えた。この考え方に立ってみると、国家もまた人間のように、自給自足の状態ではなく利己的であり、自らを充足させるために他国の富や領土を求め、奪い合いをすることになる。リアリズム的世界観とは、国際関係の基本を国家間の生存をかけた闘争ととらえるものであるといえる。 一方のリベラリズムは、リアリズムと対照的に性善説をとる。つまり、国家は闘争するのではなく、平和的な共同体を作り上げていくものと考えるのである。政治哲学者グロティウスによれば、人類には理想や価値を共有し法律や慣例をつくり、一つの共同体を形成していく傾向が本質として与えられているという。そうした人類から成り立つ国家は、お互いの間に法律や制度を作り上げて、それを守ることによって平和的な人類共同体を形成する。リベラリズム的世界観とはこのことである。
- レポート 国際関係学 安全保障 国際関係 リアリズム リベラリズム
 550 販売中 2005/10/17
550 販売中 2005/10/17- 閲覧(4,015)
-
 国際関係2経済外交
国際関係2経済外交
- 玉大 玉川大学 通信 教育 教員
 990 販売中 2010/10/19
990 販売中 2010/10/19- 閲覧(1,240)
-
 国際関係論レポート課題
国際関係論レポート課題
- 国際関係論レポート(「ヨーロッパ国際関係史」) 私の読んだ「ヨーロッパ国際関係史」は、ヨーロッパにおける国際関係がどのように変化してきたのかを近代西洋国家の歴史にまで遡って考察している。ヨーロッパを文学や思想を通して見るだけでなく、多角的にその姿を捉えている。この本は、序章に加え、1章から6章で構成されている。 序章では、ヨーロッパを捉えるためのキーワードを三つ(「ヨーロッパ概念」「ヨーロッパ国際体系の行動様式」「ハイアラーキーな国際関係構造」)提示している。ヨーロッパという概念は大航海時代をきっかけとする地理上の発見とヨーロッパに侵略してくる外敵の存在によって意識されるようになった。ヨーロッパ諸国は権謀術数の中で、各々が自己の利益を追求しつつ、他方である国を完全に弱体化させてヨーロッパ全体の秩序を崩壊させないように行動している。この行動様式は現在でも見られる。また、紛争解決について、ヨーロッパの中でも大国が定期的に会議を開いて、その課題の解決を図った。そこでは、小国の意見は無視された。このことから中心-周辺的な関係の構造が見えてくる。
- アメリカ 経済 ヨーロッパ 政治 国際 平和 国際関係 問題 統合 通信 レポート
 550 販売中 2009/01/28
550 販売中 2009/01/28- 閲覧(8,464)
-
 国際関係総合研究Ⅲ
国際関係総合研究Ⅲ
- 映像を通しての平和教育の重要性 とかく巷にあふれる過去の戦争体験の回想を見ていくと、二通りの回想に分かれる。主に過去の戦争を自衛目的や白人からの解放といった大きな大儀を唱える人々は、快進撃を続ける軍が主体となりその回想も賛美されるものである。一方、世間的に左翼的と呼ばれる側は軍関係者ではなく、戦時下の下での国民の困窮と悲惨な戦争体験を回想する。このように回想の中に登場する主体も中身も過去の戦争をいかに位置づけるかで大きく性質が異なる。それぞれの主張も回想も両者にとってはなかなか直視しにくく、なおかつ批判が難しいものであろう。それぞれは水と油のような関係のように思える。しかしながらその時代を生きたことのない私が言えることは、そのどれもがかつては実際にあったことであるのだろう、という一種日和見的意見だけである。1つの大きな戦争という共通体験対する体験と記憶は、各個人がおかれたまさしく運命と呼ぶべき個人差によって大きく異なる。ましてやそこからの回想を人に伝えるという行いは、ある意味で実際個人的経験よりも千差万別であるだろう。我々は、それらの中にある、確実にある共通した核を感じ取らねばならないのである。それが懸命な過去の回想への姿勢であると私は考えている。 授業で見た『陸軍残虐物語』のように軍隊内部での人間の尊厳を扱い、なおかつ映画という表現手法で描き出したものはなかなかなかったように思える。今後確実に軍隊生活を実体験として語れる世代が減っていく。ならばなおのこと、この映画の異種性は濃くなっていくと思われる。参考として、日中戦争に一平卒として従軍した経験を持つ人物が書いた回顧録を一読してみた。映画の中で描かれたしごきの方法も詳細(両手を二つのベッドの端において、足を浮かせて自転車をこぐもの)も書いてあり、映画と照らし合わせることによって、より当時の兵士の教育状況が理解できた。意識的かどうか、その兵士の能力の問題かは判断できないが、教育中はこのしごきの対象として沖縄出身の兵士が槍玉にあげられていたらしい。映画の登場人物の犬丸も純朴な田舎の百姓であったが、しごきと差別意識の関連性も考慮して映画を見るとまた新しい発見があるかもしれない。 この映画のテーマとは一体何であったのかということを考えてみると、当然のことながら軍隊という特殊な組織の性質への問いかけではなかっただろうか。軍隊とは階級制度が人間関係の全てである。その組織において人間とは階級的存在である。徹底した上から下への統制と確実な行動、それこそが軍隊である。当然のことながらそのような中では人間の感情の矛盾も起こる。しかし、矛盾を起こしてはならないということこそが軍隊の矛盾である。そうような環境であるからこそ、物語のようなことが発生したのではないか。 軍隊とは、国民と国家の間を取り持つ存在である。実態の見えない存在である国家に対して、軍隊というものは確実に国民の目の前に存在する。国民が国家との関係を実際的に感じることができるのは、軍隊=皇軍という存在があるためである。国へ報いるためには軍隊に入隊して戦場で活躍しなければならない。しかし皇軍は国民のための軍隊ではなかった。皇軍の矢印は国民から天皇へは向かっては行っても、天皇から国民へは向かなかったのである。徴兵制を採る近代的な軍隊制度を持ちながらの皇軍の矛盾、そして矛盾は閉塞感を生み出す。この作品は軍隊の持つ性質と矛盾を通して、当時の時代というものの持つ矛盾と閉塞感をも描き出したかったのだと考える。 私はこの授業を通して、映画などの映像を通した平和教育は重
- 平和 戦争 映画
 全体公開 2008/01/18
全体公開 2008/01/18- 閲覧(1,261)
-
 国際関係論 主権国家システム
国際関係論 主権国家システム
- 近代以降の主権国家システム 近代以前には、古代の帝国秩序である「ローマ帝国」、中世なりの秩序である「キリスト教共同体」が存在していた。 1648年のウェストファリア講和会議で主要国がお互いを主権国家であるとみなし、こうして、主権国家から構成される近代以降の国際システムができた。このシステムを「西欧国家体系(多極)」とよぶ。 17世紀から、WWⅠまでの約270年間、ナポレオン戦争を例外として大きな戦争はなく、5つくらいの主要な大国が勢力を均衡させるような外交政策をとったことから、この国際システムは勢力均衡体系(BOP)とも呼ばれる。 勢力均衡体系の欠陥は、国家間の相互不信から、軍拡競争に陥る可能性が大きいことである。(=安全保障のジレンマ) しかし、この時代になぜ勢力均衡が安定的に維持されたのかという理由は何点かある。 5つの大国である、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、ロシアの国力がほぼ等しかったことと。島国イギリスがヨーロッパ大陸に領土的野心をまたず、バランサーとしての役割を担ったこと。 戦争の被害が限定的であったこと等があげられる。 主要な行為(ACTOR)は主権国家で、
- 国際関係論 主権国家システム 主権国家 国際関係 西欧国家体系 安全保障のジレンマ 無政府状態 アナーキー 双極 冷戦 リアリズム 現実主義 勢力均衡 リベラリズム 国際的相互依存 グローバルガヴァナンス 国際レジーム 構成主義 バランスオブパワー BOP 国際紛争 ジョセフ・S・ナイ・ジュニア 理論と歴史 国際政治経済 グローバリゼーション Joseph Samuel Nye Jr.
 550 販売中 2009/01/19
550 販売中 2009/01/19- 閲覧(7,846)
-
 国際関係と日本外交政策の進行
国際関係と日本外交政策の進行
- 国際関係と日本の政冶外交 政冶外交における「戦後」 冷戦時期米ソ2つ超大国同士間が政冶の役割かなり占められたが、多極化が誕生後軍事力依然として米ソ核大国に占められた。 米国が少々下降気味、ソ連は崩壊後少々増大傾向になった。 冷戦期と言う戦後は国際組織の設立から国同士の距離を縮小し、経済面の相互依存関係が生じた。更に、各国の文化面と軍事面もかなり変化を訪れた。 プロの外交官が誕生し、情報収集と資料伝達能力が上昇した為、19世紀のような各国完全独占という形を崩壊した。 日本は敗戦前後を境にし、戦前と戦後時期分けられ、戦後の日本外交が戦前より進歩と言える。 憲法と講和・安保条約 戦後日本政府が外交面について2つの文書を締結した。 ⅰ日本国憲法である。敗戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の管理の下で、民主化と非軍事化を基づき、一連の改革により、1946年(昭和21年)日本国憲法を公布した。 ⅱ憲法の第9条の中で、「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」という所から陸海空軍を保つ事が出来ず、国の交戦権を認めない。まだ、GHQ側が天皇制の廃止を要求しながら、日本にとって天皇の存続が必要となり、マッカ
- 日本 憲法 中国 経済 戦争 社会 政治 アジア 国際 地域 憲法9条 平和憲法 国連 自衛隊 軍隊 日米同盟 GHQ 天皇 安全保障 共産主義 自由主義 共産国家 自由国家 西 東 冷戦 第二次世界大戦 戦後 吉田茂 岡倉天心 ベトナム ベトナム戦争 国際関係 NATO 北大西洋条約機構 ASEAN 東南アジア諸国連合 アジア太平洋 地域安全
 770 販売中 2009/01/30
770 販売中 2009/01/30- 閲覧(3,549)