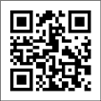連関資料 :: 密度
資料:20件
-
 磁束密度
磁束密度
- 1. 目的 円形コイルに流れる電流によって生ずる磁束密度を測定し、理論と比較する。また磁場に関するアンペール(Ampère)の法則を実験的に検証する。 2. 理論 ビオ・サバール(Biot-Savart)の法則(第1図) ・・・・・? は与えられた形状の針金を流れる電流 の微小区間 が、距離 の所にあるPに作る磁束密度 を与える。 ここで =4π× H/mは真空の透磁率、 はベクトル の長さ∣ ∣である。 一方、アンペール(Ampère)の法則(第2図) ・・・・・? は、磁束密度 をある閉区間Cに沿って積分した量はその曲線に囲まれた領域を通る電流 と透磁率 の積に等しいという式である。?、?式は、ともに磁束密度 とその原因となる電流の関係を表わしたもので、互いの等価性は証明できる。 磁束密度は、ビオ・サバールの式で求めるのが一般的であるが、その分布の対称性のよい場合はアンペールの式で求める方がずっと容易な場合が多い。 1.円形コイルによる磁束密度 円形コイルの中心軸上の磁束密度 をビオ・サバールの法則より求める。 第3図のように半径 の円形コイルに電流 が流れている。 と とは直角であるから、?式より、 図より で、 の関係があるから、 の 軸方向の成分 は である。円形コイル全体による点Pにおける磁束密度 は対称性から 軸方向を向き、その大きさは、 ・・・・・? となる。 2.サーチコイルの誘起電圧 第4図のように、磁束 が変化する場所にコイルを置く。ファラデー(Faraday)の電磁誘導の法則によれば、 ・・・・・? の関係がある。 は電場ベクトル、 はコイルの微小区間である。 点A、Bの電位をそれぞれ 、 とすれば、 となる。コイルの断面積 が小さく、コイル付近の磁束密度の大きさ が一定とみなせるとき、 より
- レポート 理工学 磁界 実験 コイル
 550 販売中 2006/01/19
550 販売中 2006/01/19- 閲覧(6,465)
-
 セメントの密度試験
セメントの密度試験
- 試験の目的 コンクリートの配合設計におけるセメントの容積計算において、使用するセメントの密度が必要である。 セメントの密度の変化によって、その風化程度を知る目安になる。 未知のセメントの種類を、セメントの密度からある程度推定することが出来る。 混合セメントの粉末度試験(ブレーン工法)を行う場合には、試料の量を決定するのに、密度の実測値が必要である。 実験方法 (1)準備 ルシャテリエ密度びん はかり(ひょう量200g、感量0.1g) 水タンク(20±0.2℃) 鉱油(JIS K 2203に規定されている灯油、あるいはJIS K 2204に規定されている軽油を完全に脱水したもので、通常、白灯油がよく用いられる) その他、鉢、乾燥した布もしくはティッシュペーパーを巻きつけた針金、ゴム板、黒色光沢紙、おもり、温度計 (2)実験手順 ルシャテリエ密度びんの目盛0~1ml.の間まで入れる 水タンク中に静置して、鉱油の液面がほとんど変化しなくなったとき、その液面の 目盛ⅴ1を読む。 試料100gをはかりとり、少しずつ静かに密度びんに入れる。 注)試料を密度びんに入れる前に、管壁に付着している油を針
- レポート 建築学 セメント 密度 実験 材料
 550 販売中 2007/02/03
550 販売中 2007/02/03- 閲覧(12,863)
-
 4-5ラグランジアン密度を使う
4-5ラグランジアン密度を使う
- ラグランジアン密度を使う 連続体の解析力学の説明の残り部分。 何だかちょっと合わないぞ 前回、前々回と、汎関数微分についてのまとめ記事を挟んだ。 これはその前の「 連続体の解析力学 」の記事中で出て来た次のような方程式を見てもたじろぐことの無いようにしたかったからである。 前回までの説明を読んで、これを具体的に解くことが出来るようになっただろうか。 少し状況の再確認をしておこう。 上の式の中の L はラグランジアンであり、それはラグランジアン密度 を使って と表されるのだった。 前に書いたときには積分範囲を表記しなかったが、汎関数微分について書いている内に定積分と不定積分に大きな意味の違いがあることに気付いたので、ここでは急遽書き足したのである。 本来こういう意味なのだった。 これまで書いた全ての記事ではあまりそのようなことを意識して来なかったが、大丈夫だっただろうか。 ひもの運動の場合には は と書けるものであり、つまり、 と との関数になっていると言える。 しかしもう少し複雑な問題を考える時には が y を直接含むこともあったりするので、将来のために少し考えを広げて、 は y と と との関数になっていると考えておこう。 汎関数微分のみに集中した前回までの特別講義では I や F (x) や f (x) という記号を使ってきた。 今回の話ではこれらに対応するのがそれぞれ、 L や や y (x) だというわけである。 ん? 何か変だ。 関数 y というのは y (x) ではなくて y ( x, t ) という形ではなかったか。 前回までの説明には t に相当するものは出て来なかった。 まぁ、それだけなら t は定数みたいなものだと考えて無視してやれば済むのだろうが、どうやらそうも行かない。 なぜなら、その t を使って微分した というものが、 の中に含まれてしまっているからだ。 このような要素が加わることで、前回までに説明した話と比べてどんな相違点が出てくることになるのか、落ち着いて考えてみよう。 汎関数微分の計算 まず (1) 式を見て、第 2 項の方が簡単そうだから、そちらから考えてみよう。 これは y が y + δy に変化する時の L の変化を考えようとしているのである。 y が変化すればそれに合わせて と も変化するので、それによる の変化は、 と書けるのだろう。 これを (2) 式に代入してやって、全ての項を δy に合わせてまとめるべく部分積分を行うというのが、これまでのテクニックであった。 しかしこの第 3 項は厄介なことに、まとめようがないのである。 しかし安心していい。 実はここで第 3 項を考えに入れる必要は元々なかったのである。 騙し討ちをしたようで少し心苦しいが、今さらながらその理由を説明しよう。 (1) 式を作ったところまでさかのぼって考えて欲しい。 この式のもとになったラグランジュ方程式は、 L の変数として y と を使っていた。 これらはそれぞれ独立な変数として扱われており、式も偏微分を使って表されていたはずだ。 つまり、y で偏微分するときには は変化しないと見なし、 で偏微分するときには y は変化しないと見なしていたのである。 実は今回の (1) 式の汎関数微分は、偏微分のように考えて計算されるべきなのだ。 (1) 式を見た限りはそんな風に計算すべきだなんてことは読み取れないのだが、式の導出の経緯の中にそのような意味が隠されているのである。 「いやいや、そん
 全体公開 2007/12/26
全体公開 2007/12/26- 閲覧(3,173)
-
 1-9確率流密度
1-9確率流密度
- 確率流密度 豆知識。 あとで役に立つ。 何に使うのか 今回の話は書くつもりは全くなかったのだが、第4部の「相対論的量子力学」を書いている途中で予備知識として必要を感じたのでここに入れることにした。 多くの教科書でこの話が出てくるが、私はこれまでそれが一体何の役に立つのか理解できず、邪魔な話だなぁ、と読み飛ばしていただけだった。 しかし、知っておいて無駄な話ではない。 いや、難しい話ではないので、知らなければ当然知っておくべきだ。 存在確率の時間微分 波動関数の絶対値の2乗は粒子の存在確率の密度を表していて、それをある範囲で積分することで存在確率が導かれるのだった。 積分範囲として、考えられる全空間を設定すると当然その値が1にならなければおかしい。 当たり前のことだが、この値は時間とともに変化されると困る。 この式の左辺が本当に変化しないのかどうか、あるいはどのような条件で常にこの関係が成り立っているのかを確かめておきたい。 時間微分して0になることが言えればいいのである。 途中まで計算してみよう。 ああ、すぐに行き詰まる。 この先はどうすればいいかと言うと、シュレーディ
 全体公開 2007/12/26
全体公開 2007/12/26- 閲覧(2,396)
-
 1-6電束密度の意味
1-6電束密度の意味
- 電束密度の意味 どうして電場と同じようなものを もう一つ定義しなくてはならないのだろう。 本質ではない量 学生時代にはこの電束密度の意味を正しく理解できていなかった。 しかし、今考えて見れば実はとても単純なことだったのである。 この「電束密度」という呼び方は歴史的な由来を持つものであって、その本質とはあまり関係ないので気をつけなければならない。 これについては後の方で説明しよう。 この電束密度という量は私が求めている「実在」ではなく、科学の発展の歴史の中で研究者に都合の良いように導入されたものに過ぎない。 それでも物性を研究する人にとっては今でも十分利用価値のある便利な量ではある。 本当はこういう本質的でない話は後回しにして早くマクスウェルの方程式を完成させたいのだが、マクスウェルの方程式を理解するためには結局この「電束密度」を理解することが必要になってくる。 それに本質でないものにはさっさとけりをつけて無視できるようにしておいた方が気持ちがいい。 少し寄り道に感じるかも知れないが、話の流れ上ここで説明しておくのが一番良いだろうと思う。 空間は電荷だらけ 我々の周りは電荷で満ち満ちている。 いくら真空ポンプで真空を作っても、なおそこには何億、何兆では言い表せないほどの原子が存在する。 (でも真空管の程度まで空気を引けば何兆で言い表せる程度にはなるか・・・) その原子の一つ一つが負の電荷を持った電子と、正の電荷を持った原子核から出来ているのだ。 普段はそのプラスとマイナスが打ち消しあって表向き0になっているように見えるけれども、電場をかけてやればプラスとマイナスは別方向へ移動するので空間に電荷がひょっこり顔を出すことになる。 身近な例を挙げてみよう。 電気を流さない固体を鉄板で挟んでやり、この両端に電圧をかけてやる。 すると固体の中の電子と原子核はズレを生じる。 電子はプラス極に引かれ、原子核はマイナス極に引かれる。 引かれるけれども原子が分解するほどではない。 だから電気は流れていかない。 流れてはいかないが、マイナス極側にはプラスの電荷が、プラス極側にはマイナスの電荷が顔を出す。 このように電圧がかかった時にプラスとマイナスに分かれることを「分極」という。 そして分極する物質を「誘電体」という。 金属の場合には電圧がかかると自由電子が流れていってしまうのでそのせいで電圧が降下し分極するどころではないが、絶縁体は誘電体として使える。 空気だって僅かだが分極する。 つまり、空気中で電磁気の実験をする時でさえこのような多数の原子の影響を考慮に入れなくてはならないわけだ。 電束密度の導入理由 空間にプラスの電荷があったとしよう。 そして周囲が誘電体に囲まれている場合を考える。 すると、プラスの電荷の周りには特に用意しなくても勝手にマイナスの電荷が姿を現すことであろう。 ここでガウスの法則を使ってみる。 プラスの電荷とその周りに現れたマイナスの電荷をすっぽり覆うような閉曲面を考えよう。 この閉曲面での電場はどうなるだろう? プラスとマイナスが中和して、極端な場合にはほとんど0になってしまう。 プラスの電荷だけを考えて計算しようとするとガウスの法則が成り立たなくなってしまうのだ!! いや、心配しなくても大丈夫。 ちゃんとプラスの電荷とその周りに勝手に現れたマイナスの電荷をすべて計算に入れればガウスの法則はいつだって問題なく成り立っているのである。 しかし実験家の立場からすれば、意図的に用意したのはプラスの電荷だけであって、
- 実験 歴史 電気 電子 密度 比較 現代 影響 定義 概念
 全体公開 2007/12/26
全体公開 2007/12/26- 閲覧(3,695)