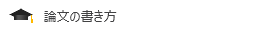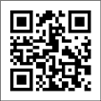資料紹介
ギブスの相律
それと三重点の話。
多成分系の平衡
前回は2成分が混じった場合の具体例を説明した。 そこでは2つの相(液相と気相)の間の平衡についてしか話さなかったが、現実には3つ以上の相が同時に存在するような状況も起こり得る。 液相と気相と固相の3つ以外にどんな相があるんだと思うかも知れないが、それは次回の相転移の話の中で説明しよう。
今回はあらゆる可能性を理論的に考えることをしたい。 α 種類の成分が β 個の相を作る状況についての話である。 ここまで話を広げると具体的な話をするのが難しいので、おおよその状況を把握する程度になるだろう。
各相にはそれぞれ α 種類の成分が含まれていると考えておこう。 前回ちょっと話した塩水の蒸発のように、気相に塩の分子が出て来ないような状況も考えられるが、必ずごく微量は出てくるはずなので全ての相に全ての成分が含まれると考える。 つまり、α β 個の化学ポテンシャルが定義されるわけだ。
他の変数としては何があるだろうか。 各相の温度 Ti と圧力 pi が重要な要素である。 つまり 2 β 個の変数が追加される。
さて、各相の間の平衡条件としてまず挙げられるのは、全ての相で温度、圧力が等しいことである。
これは ( β - 1 ) × 2 個の等式で結ばれていることから、温度、圧力にだけ関して言えば、
2 β - 2 ( β - 1 ) = 2
の計算により2つ分の自由度だけが残されていることになる。 平衡状態での各相の圧力と温度は、全て等しく p、T となっていて、2つの変数だけあれば状態が表し切れるということを表している。 以上は当たり前の話ではあるが、こんな調子で話を続けていこう。
この他の平衡条件として、各相で化学ポテンシャルが等しいという「共存条件」がある。 ただしこれは水なら水、アルコールならアルコールといった具合に各成分について別々に考えれば良くて、水とアルコールの化学ポテンシャルを比較する必要は全くない。 これは前回も説明した。 成分 k の 第 i 番目の相における化学ポテンシャルを と表すことにすると、
ということであって、これは β-1 個の等式である。 それが各成分の数だけあるのだから、合計 α(β-1) 個の束縛条件があることになる。 つまり、化学ポテンシャルについての自由度は、
α β - α ( β - 1 ) = α
だということになるだろうか。 いや、それで全てではない。 各相の化学ポテンシャルの間には、
という「ギブス・デュエムの式」が成り立っていたことを思い出そう。 このためにさらに β 個の制限が追加されることになる。
ここまで分かり易さの為に「化学ポテンシャルの自由度」「温度、圧力の自由度」などと区別して話してきたが、そもそも化学ポテンシャルは温度、圧力の関数になっているのだから、分けて考えることに大した意味はない。 それで最終的に全体でいくつの自由度が残されていることになるだろうか。 まとめると、自由度 f の数は次のようになる。
f = 2 + α β - α ( β - 1 ) - β = 2 + α - β
これが「ギブスの相律」と呼ばれる式である。
自由度について
前に「ギブス・デュエムの式は自由度に制限を加えるようなものではない」という話をしたが、上ではギブス・デュエムの式を束縛条件として使っている。 これは矛盾したことを言っているのではないかと受け取られるかも知れないので、ちゃんと言い開きをしておこう。
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
ギブスの相律
それと三重点の話。
多成分系の平衡
前回は2成分が混じった場合の具体例を説明した。 そこでは2つの相(液相と気相)の間の平衡についてしか話さなかったが、現実には3つ以上の相が同時に存在するような状況も起こり得る。 液相と気相と固相の3つ以外にどんな相があるんだと思うかも知れないが、それは次回の相転移の話の中で説明しよう。
今回はあらゆる可能性を理論的に考えることをしたい。 α 種類の成分が β 個の相を作る状況についての話である。 ここまで話を広げると具体的な話をするのが難しいので、おおよその状況を把握する程度になるだろう。
各相にはそれぞれ α 種類の成分が含まれていると考えておこう。 前回ちょっと話した塩水の蒸発のように、気相に塩の分子が出て来ないような状況も考えられるが、必ずごく微量は出てくるはずなので全ての相に全ての成分が含まれると考える。 つまり、α β 個の化学ポテンシャルが定義されるわけだ。
他の変数としては何があるだろうか。 各相の温度 Ti と圧力 pi が重要な要素である。 つまり 2 β 個の変数が追加される。
さて、各相の間の平衡条件としてまず挙げられるのは、全ての相で温度、圧力が等しいことである。
これは ( β - 1 ) × 2 個の等式で結ばれていることから、温度、圧力にだけ関して言えば、
2 β - 2 ( β - 1 ) = 2
の計算により2つ分の自由度だけが残されていることになる。 平衡状態での各相の圧力と温度は、全て等しく p、T となっていて、2つの変数だけあれば状態が表し切れるということを表している。 以上は当たり前の話ではあるが、こんな調子で話を続けていこう。
この他の平衡条件として、各相で化学ポテンシャルが等しいという「共存条件」がある。 ただしこれは水なら水、アルコールならアルコールといった具合に各成分について別々に考えれば良くて、水とアルコールの化学ポテンシャルを比較する必要は全くない。 これは前回も説明した。 成分 k の 第 i 番目の相における化学ポテンシャルを と表すことにすると、
ということであって、これは β-1 個の等式である。 それが各成分の数だけあるのだから、合計 α(β-1) 個の束縛条件があることになる。 つまり、化学ポテンシャルについての自由度は、
α β - α ( β - 1 ) = α
だということになるだろうか。 いや、それで全てではない。 各相の化学ポテンシャルの間には、
という「ギブス・デュエムの式」が成り立っていたことを思い出そう。 このためにさらに β 個の制限が追加されることになる。
ここまで分かり易さの為に「化学ポテンシャルの自由度」「温度、圧力の自由度」などと区別して話してきたが、そもそも化学ポテンシャルは温度、圧力の関数になっているのだから、分けて考えることに大した意味はない。 それで最終的に全体でいくつの自由度が残されていることになるだろうか。 まとめると、自由度 f の数は次のようになる。
f = 2 + α β - α ( β - 1 ) - β = 2 + α - β
これが「ギブスの相律」と呼ばれる式である。
自由度について
前に「ギブス・デュエムの式は自由度に制限を加えるようなものではない」という話をしたが、上ではギブス・デュエムの式を束縛条件として使っている。 これは矛盾したことを言っているのではないかと受け取られるかも知れないので、ちゃんと言い開きをしておこう。
上の議論に於いて、各相の全体のギブスのエネルギーが使われていないことに注目しよう。 この量は許された自由度の一つであって、各相の分子の全体量によって増減するが、これについて制限する式はどこにも使っていないのである。 しかしこの自由度を差し引いておかないと辻褄が合わなくなる。 これは平衡条件には関係のない量であるからだ。
化学ポテンシャルというのは一定量あたりのエネルギーを意味するから、全体量にはあまり関係がない。 つまり、多成分の平衡に必要な要素というのは各成分の割合だけであって、各相の分量は関係していないのである。
この無駄な自由度を平衡に関わる自由度から省くために、ギブスのエネルギーの全体量についての変形版であるギブス・デュエムの条件式が加えられているのである。
ではこの無理やり殺された自由度は本当に平衡条件に対して意味を持たないのだろうか。 確かに等温等圧の条件の場合には、ある一つの相の全体の分量だけが変化したところで、他に対して何の変化も引き起こさないだろう。 しかし体積が固定された容器内での事を考えると、ある一つの相の分量が変化すればその分だけ容器全体の圧力が変化して、全体の平衡条件に影響を及ぼすことになる。 ちゃんと意味がありそうではないか。
しかし仮にそのようなある相の全体量を表す変数を殺さずに残しておいたとしよう。 その場合には、ある相の分量の変化が温度や圧力に対して与える影響の度合いを定めた新たな条件式が追加されることになるだろう。 それで結局は「ギブスの相律」として求められた自由度の数と変わらない結果が導かれることになる。 今、「新たな条件式が追加されることになる」と言ったが、よく見てみればギブス・デュエムの式には圧力変化や温度変化が含まれているのであって、ギブス・デュエムの式こそ、その役割を負っている式なのである。
こういう面倒な言い訳をしなくて済むように、教科書によっては「各化学ポテンシャルの値を決めるのは各相におけるモル分率である」として、 α β 個の化学ポテンシャルを使う代わりに α β 個のモル分率を独立変数として導入し、ギブス・デュエムの式の代わりに「モル分率の合計は1である」という条件を相の数だけ使っていたりする。 暗に「各相の全体量は関係ない」と言って、ある自由度については目をつぶっているのだから結局は同じことをしているのである。
不親切な教科書だと、独立変数として化学ポテンシャルを使っておきながら、どこから沸いたか分からない「モル分率の合計は1」という条件をいきなり当てはめており、非常に統一性のない議論になっている。 また「温度、圧力が一定の場合」に限定することで、面倒な議論からうまく逃げていたりする教科書もあって、そのテクニックに感動する。 先生方の隠れた苦労がうかがえてなかなか面白いものである。
ギブスの相律というのはまぁ豆知識的な話であって、理論の根幹に関わるような使い方をされるものではないので、それほど目くじらを立てる部分ではないのだろう。 しかしまだ学問全体の雰囲気を把握しきれていない学生というのは、とにかく漏らさず完璧に理解しようと努力するわけで、こういう曖昧なことをされるとすぐに引っ掛かってしまうのである。
三重点
ギブスの相律を1成分(α = 1)の場合に当てはめてみよう。
1成分で相が1つしかない場合( α = 1 , β = 1 )を代入すると、f = 2 となる。 「1成分だけの系には自由度は2つしかない」などと考える人が出てきてしまうのはこの関係式のためである。 ちゃんと意味を考えて使わないと間違いを犯すことになる。 ギブスの相律は平衡条件を満たしながら変化するときの自由度を示しており、「全体のモル数が変化したところで平衡条件には関係ない」という理由で、本当はあるはずの自由度が省かれているだけのことである。
相が2つの場合を考えると、f = 1 になる。 自由度が一つしかなく、定められた一本の線の上でしか変化を許されないということだ。 普通は p と T を変化させた時のグラフを描くことになる。 これを共存曲線と呼ぶ。 前に出てきた「蒸気圧曲線」というのは水と水蒸気の共存曲線だ。 この他にも、水と氷の共存曲線もあるし、氷と水蒸気の共存曲線もある。 水についてはだいたい次のような図になっている。
(ここに図が入る)
β = 3 になると自由度 f は0になる。 つまり3つの相が共存する条件というのは無条件に一点だけに決まってしまうことになる。 この点を「三重点」と呼ぶ。 上の図で共存曲線がぶつかっている一点がそれだ。
自由度が負になることはないので、純粋な物質では4つ以上の相が共存するような事は決してないことになる。 共存できないだけであって、3つ以上の相が存在すること自体を禁止しているわけではない。 よく知られている「気相」「液相」「固相」の他にもいろいろな相があるのだが、これについては次回に詳しく説明しよう。
身近な物質である「水」を例に挙げれば、「水」と「氷」と「水蒸気」の3つの相が共存する条件はたった一つしかないということである。 水の三重点は、
p = 6.1166 hPa , T = 273.16 K
の時である。 これはどんな条件にも左右されずに決まってしまうことなので、科学的に厳密に温度の定義をするのには大変都合のいい話である。 実際に「水の三重点の 1/273.16 を 1ケルビンとする」と定義されている。
えーっと、ちょっと待てよ? 絶対零度は -273.15℃ なのではなかったか。 その通り。 「絶対温度とセ氏温度の差は 273.15 である」と定義されている。
すると三重点は絶対温度で 273.16 K。 つまり摂氏温度で表すと 0.01℃ だということになってしまうではないか。 その通り。 摂氏温度は三重点を元に定義されているのではなく、昔から「1気...