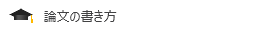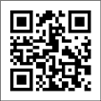資料紹介
ジュール・トムソン効果
恩恵を受けているにも関わらず、 誤解は大きい。
実験の改良
2つ前に話した「ゲイリュサック・ジュールの実験」を思い出してもらいたい。 熱力学は熱平衡に達した状態での状態量の関係を論じる学問だから、気体が真空中に広がろうとしている途中での状態に対してはあまり確かなことが言えない。 内部エネルギーが体積変化に依存しないとは言っても途中ではどうなっているんだと突付かれると困ってしまう。 しかもこの実験は一瞬で終わってしまうので精密な測定が難しい。
そこでこの実験を改良して、容器の間を繋いでいたパイプの中に綿を詰めて、気体がゆっくり真空中へもれるようにしたらどうだろうか。 熱平衡に近い状態を保ったまま変化し続ける状況が作り出せるだろう。
この実験で面白いことが起こる。 容器Aから容器Bへゆっくりと気体を噴き出させると、容器Bの側の気体の温度が変化するのだ。 この現象を「ジュール・トムソン効果」と呼ぶ。 なぜこんなことが起こるのだろう?
それを考える前にこの実験装置の他の改良点についても確認しておこう。
まず容器Aと容器Bをつなぐ管の中に綿を詰めた。 これは気体が一気に流れてしまうのを防ぐためである。 両方の容器の中で平衡状態が保てるようにゆっくり流したい。
しかしこれだけでは不都合がある。 容器Bの中に気体が流れ込んでくると容器Bの中の圧力が徐々に高まってゆくだろう。 それでは状態が時々刻々と変化してしまう。 これを一定に保つために、容器Bにピストンをつけてその上におもりを乗せ、常に一定の圧力が保てるようにしておこう。
気体を流してやるためには、容器Aの側に容器Bよりも強めの圧力をかけてやる必要がある。 そちらの圧力も一定に保てるように、容器Aの側にも同じ仕組みを作る。 そして容器Bよりも少し重いおもりを乗せてやる。
両方の容器には温度計を設置しておく。 これで変数を完全にコントロールした状態での実験が出来るわけだ。 容器Aの温度を一定に保ち、容器Bでの温度を測ることにする。
前の実験では容器Bの側を真空状態にして始めたが、この実験では予め容器Bにも気体を入れておく。 そうしないと平衡状態を作り出せないからだ。
ここまで変えてしまうと、これはすでに前の実験とは全く性格の異なる実験になってしまっているのではないだろうかと不安になることだろう。 その通り、全く違う実験であるから、あまりそこで悩まないで欲しい。
等エンタルピー変化
容器Aでは圧力は pa で常に一定、容器Bでは圧力は pb で常に一定。 綿の栓(細孔栓と呼ぶと専門的でかっこいい)を挟んで圧力の異なる気体が接している。
準静的でありながら不可逆過程。 前に「準静的過程は可逆過程だ」と説明したが、それを全く覆すような実験である。 このような、系の全体では平衡ではないが部分的に平衡状態が保たれた状況を「広義の準静的過程」だと見なすことがある。 「広義の準静的過程」を含める場合、可逆過程だとは限らないということだ。
これで何が起こるかを分析してみよう。
容器Aの中の気体の一部分、例えば体積 Va が容器Bへと流れると、そこでは圧力が違うので体積に変化があるだろう。 それで Vb になったとする。 その時にこの「移動した気体」の内部エネルギーにはどれほどの変化があるだろうか。
この気体は圧力 pa で押し出されて出て行った。 つまり pa Va の仕事をされた。 そして圧力 pb が掛かっているところへ押し入って行った。 そ
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
ジュール・トムソン効果
恩恵を受けているにも関わらず、 誤解は大きい。
実験の改良
2つ前に話した「ゲイリュサック・ジュールの実験」を思い出してもらいたい。 熱力学は熱平衡に達した状態での状態量の関係を論じる学問だから、気体が真空中に広がろうとしている途中での状態に対してはあまり確かなことが言えない。 内部エネルギーが体積変化に依存しないとは言っても途中ではどうなっているんだと突付かれると困ってしまう。 しかもこの実験は一瞬で終わってしまうので精密な測定が難しい。
そこでこの実験を改良して、容器の間を繋いでいたパイプの中に綿を詰めて、気体がゆっくり真空中へもれるようにしたらどうだろうか。 熱平衡に近い状態を保ったまま変化し続ける状況が作り出せるだろう。
この実験で面白いことが起こる。 容器Aから容器Bへゆっくりと気体を噴き出させると、容器Bの側の気体の温度が変化するのだ。 この現象を「ジュール・トムソン効果」と呼ぶ。 なぜこんなことが起こるのだろう?
それを考える前にこの実験装置の他の改良点についても確認しておこう。
まず容器Aと容器Bをつなぐ管の中に綿を詰めた。 これは気体が一気に流れてしまうのを防ぐためである。 両方の容器の中で平衡状態が保てるようにゆっくり流したい。
しかしこれだけでは不都合がある。 容器Bの中に気体が流れ込んでくると容器Bの中の圧力が徐々に高まってゆくだろう。 それでは状態が時々刻々と変化してしまう。 これを一定に保つために、容器Bにピストンをつけてその上におもりを乗せ、常に一定の圧力が保てるようにしておこう。
気体を流してやるためには、容器Aの側に容器Bよりも強めの圧力をかけてやる必要がある。 そちらの圧力も一定に保てるように、容器Aの側にも同じ仕組みを作る。 そして容器Bよりも少し重いおもりを乗せてやる。
両方の容器には温度計を設置しておく。 これで変数を完全にコントロールした状態での実験が出来るわけだ。 容器Aの温度を一定に保ち、容器Bでの温度を測ることにする。
前の実験では容器Bの側を真空状態にして始めたが、この実験では予め容器Bにも気体を入れておく。 そうしないと平衡状態を作り出せないからだ。
ここまで変えてしまうと、これはすでに前の実験とは全く性格の異なる実験になってしまっているのではないだろうかと不安になることだろう。 その通り、全く違う実験であるから、あまりそこで悩まないで欲しい。
等エンタルピー変化
容器Aでは圧力は pa で常に一定、容器Bでは圧力は pb で常に一定。 綿の栓(細孔栓と呼ぶと専門的でかっこいい)を挟んで圧力の異なる気体が接している。
準静的でありながら不可逆過程。 前に「準静的過程は可逆過程だ」と説明したが、それを全く覆すような実験である。 このような、系の全体では平衡ではないが部分的に平衡状態が保たれた状況を「広義の準静的過程」だと見なすことがある。 「広義の準静的過程」を含める場合、可逆過程だとは限らないということだ。
これで何が起こるかを分析してみよう。
容器Aの中の気体の一部分、例えば体積 Va が容器Bへと流れると、そこでは圧力が違うので体積に変化があるだろう。 それで Vb になったとする。 その時にこの「移動した気体」の内部エネルギーにはどれほどの変化があるだろうか。
この気体は圧力 pa で押し出されて出て行った。 つまり pa Va の仕事をされた。 そして圧力 pb が掛かっているところへ押し入って行った。 そのために pb Vb の仕事をしたことになる。 さて、これは結局エネルギー的に得をしたのか損をしたのか、どちらだろうか。 確かに pa > pb だが、それゆえに Va < Vb であり、これだけではどちらが大きいのか分からない。
理想気体の場合は pV = 一定 が言えるので差し引き0になるのではないだろうか? しかしそれは温度が一定の場合の話であって、今回、容器Bの側の温度は特に制御しているわけではない。 それほど簡単な話ではないだろう。
いや待てよ。 理想気体の場合にはその考えが使えそうだ。 仮に容器Bの側の温度がAよりも高ければ、膨張するために内部エネルギーを余計に消費して温度が下がり、その逆は逆の結果になる。 それで結局は容器Aと温度が変わらないところで安定するだろうという予想がつく。 そう、それでいい。
しかし実在気体についてはそう簡単ではない。
この状況を式で書くと、
ということであり、これを変形すると、
となっている。 よく見ると移動の前後でエンタルピーを一定に保っているではないか。 つまり、気体膨脹のエネルギーを含めた全エネルギーという意味では変化はしていないことになる。
それを踏まえて考えを整理し直そう。 先ほど「押し出されて出て行った」という表現を使ったが、気体を押し出すためのエネルギーを容器A側が負担したのだろうか。 そう見えるかも知れないが、それは出て行った気体の内部エネルギー Ua とそれ以外の部分 paVa を分けて考えているからであって、それらの全量は元々気体自身がエンタルピーとして持っていたものだと考えた方がよい。 容器Aはエネルギーを持った気体が出て行ったことによってのみ、エネルギーを失っただけだと考えるのである。
容器Bも気体が入ってきてそこで膨張することによって余計にエネルギーを得たように見えるが、流入してきたエネルギーの全量は結局、流入してきた気体が持っていたエンタルピー分でしかないのである。
容器Aから容器Bへエネルギーが移動したとか、どちらがエネルギー的に得をしただとかいう見方をすると無用な混乱をしてしまうので注意しようということだ。
結局、気体は自身の内部エネルギーと膨張のエネルギーを交換して自分で出て行ったのである。 ややこしいことを考えないで、後は気体自身に任せればいいだけの話だ。 移動によって内部エネルギーが増えたのか減ったのかは気体自身がやりくりしていることになる。 もし内部エネルギーが増えれば代償として温度が高くなるし、減っていれば温度は低くなるだろう。 (温度が内部エネルギーだけで決まるのは理想気体だけの話だが、おおよそそういう傾向があるということは言える。)
さて、実在気体の場合、温度は上がるのか下がるのか一体どちらになるのだろうか。 そしてそれを決めている主原因は何だろうか。
計算で検証
それを知るためにどれほどの圧力差 Δp を与えるとどれほどの温度変化 ΔT を生じるのかを計算してみればいい。 つまり知りたいのは、等エンタルピー変化における ΔT と Δp の比、(∂T/∂p)H である。 これは「ジュール・トムソン係数」と呼ばれている。
計算すればいいだけなので詳しい説明は省こう。 前に紹介した「マクスウェルの規則」を使えば、
が言える。 これを次のように変形する。
右辺の (∂H/∂p)T を分かりやすい形に直したい。 dH = TdS+Vdp であることより、
であり、さらにここに「マクスウェルの関係式」を使えば、
となる。 この結果を先ほどの式に代入して、
を得る。 これが望んでいた係数だ。
これには1モルあたりの体積、定圧比熱、定圧膨張率などが含まれており、同じ実験をしても物質の種類によって温度の変化の仕方に違いがあることが分かる。 また同じ物質であっても温度や圧力によって値が変化するようだ。 だから正確な温度変化を求めたければ、
のような積分計算をする必要があるだろう。
この係数の中でも一番大きな影響がありそうな部分は、分子のカッコの中身であって、 Tβ が1より大きいか小さいかによって、この係数全体が正にも負にも0にさえなるようである。 この係数が正ならばこの実験で(圧力が下がるのに合わせて)温度は下がるし、負ならば逆に温度は上がることになる。
理想気体の場合は常に Tβ = 1 であるから、係数全体は0。 よってこの実験で温度変化は起こらない。 先ほど考えた通りの結果だ。
ところが実在気体の場合には、低温の時に膨張率が高いために Tβ > 1 になり、高温になると膨張の割合が減るので Tβ < 1 になるという傾向がある。 つまり低温の気体を使えば温度が下がるが、高温の気体を使えば逆に温度が上がることになるのである。
どこかに係数がちょうど0になるような温度があるはずで、それは「逆転温度」と呼ばれている。 しかしその温度も圧力によって変化する。
物質を温めるのは容易だが、冷やす方法は限られている。 この現象を冷却に応用しようと思ったら、逆転温度がなるべく高い物質を使うのが有利になるだろう。 少なくとも常温以上でないと空調には使えない。
冷房の仕組み
これと同じ原理が冷蔵庫やクーラーに応用されている。
以前は内部の気体として、逆転温度が高く、化学的にも安定していて人体に無害で耐久性があり機械にも優しいフロンガスが使われていたが、オゾン層の破壊という点では無害とは言えなかったため、最近では主に代替フロンが使われている。 しかしこれも二酸化炭素の数千倍に相当する温室効果を及ぼすという点で問題があることから、代わりに二酸化炭素やプロパンなどを使った「ノン・フロン冷蔵庫」なども登場してきたようだ。 冷房に使うこれらの作業気体、作業物質を「冷媒」と呼ぶ。
時々ブーンという音が聞こえるのはコンプレッサーの動く音だ。 これは気体の断熱圧縮をしてい...