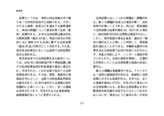連関資料 :: 政治
資料:494件
-
 日本政治思想史
日本政治思想史
- 回、夏期レポート課題として、多木浩二氏の著作である「天皇の肖像」を読み、それをレポートすることとなった。政治学科を専攻する私にとって、天皇の御真影を通した江戸~明治日本の移り変わり、それは大衆から特権階級、ひいては天皇自身をも取り巻く環境の変化であり、西洋文化の流入に苦慮しつつも、国体維持のために多くの文化をとりいれようとする多くの流れがかいま見える。それは、実際には予想もし得ない事柄も含めて、大日本帝国の幕開けであった。そして、それはポツダム宣言の受諾まで続くわけだが、過去の日本の姿を捉え、またそのあまりに知られていない成り立ちを知るには絶好の著書であった。今回、それらの事柄について見識を少しでも深められたことに感謝しつつ、著書を自分なりに解きほぐしていきたい。しかしながら、私自身の不勉強も相まって、いささか難しい箇所も多々あった。読み苦しいところもあるかも知れないが、最後までお付き合い頂きたい。まず、時系列にまとめていこうと思う。江戸から幕末への移り変わりの中、江戸時代において、将軍が実質的な権威であり、天皇はあくまでも象徴である、とする「消極的権威」から、大久保利通ら新政府の人間達の手により、まだまだ幼かった明治天皇は実質的にも日本国の指導者、元帥となるべく教育を受ける。その中で、女性的であった宮廷を大きく変革し、天皇をより男らしい、多くの人間を統率出来る人間へ、また民衆にもそれを知らしめるための改革を行った。なんと言っても、幕府が消え去った中で、新政府はその力を国内的にも、また対外的にも見せていかなくてはならなかった。国内では権力を失った豪族が蔓延っていたし、民衆も体制の変化に不安を見せていたためである。そういった中で、唯一無二の天皇という存在を大きくしていき、国民に対しての「顔」または「リーダー」とすることは、国内の秩序を保つ上で非常に重要な意味があった。また、国家の力を強めていくに当たって、軍事的な意味での統率も視野に入れる中で、天皇の存在は非常に有効だったのかも知れない。その中で、名前しか知らず、実質的に何の力も持たない天皇に対して国民が持つイメージはあまりに希薄であった。こういったところから、肖像の有効性は発揮されていったとも言えよう。御真影と共に、天皇と国民との間を近くしたのは巡幸であった。実際に天皇自ら全国を行脚し(実際
- 法政 法学 政治学
 550 販売中 2012/04/12
550 販売中 2012/04/12- 閲覧(2,599)
-
 住民投票(政治学)
住民投票(政治学)
- 投票というのは、市民の政治活動の中で最も多くの市民が参加する活動である。大きく分けると議員、首長などを選出する議員選挙と、特定の問題について賛否を問う住民(国民)投票がある。日本の住民投票は憲法改正の国民投票(憲法96条)、特定の地方公共団体にみに適用される法律に関する住民投票(憲法95条)が明文として存在する。その他、地方自治体単位においては条例で住民投票を定める例がある。 地方自治体での住民投票を巡る動きについては、1982年に高知県窪川町で原発設置に関する町民投票条例が町長提案で議会に提出され、可決された。これが全国で始めての住民投票条例である。その後、原発、産廃処分場建設を中心として、全国で住民投票条例制定の動きがあり、90年代後半からは提案の数が飛躍的に上昇している。しかし、多くの提案は否決されており、可決されるのは首長提案、議員提案が多いように見受けられる。 住民投票にはいくつかの問題点・課題がある。第1の課題が法律上の規定が無く、法的拘束力が無いことである。例えば、原発建設で住民投票の結果が賛成45、反対55の場合に、法的拘束力があれば原発は建設されない。しかし、現
- レポート 政治学 住民投票 直接参加 条例 リコール
 770 販売中 2006/11/26
770 販売中 2006/11/26- 閲覧(2,158)
-
 社会主義の政治思想
社会主義の政治思想
- 社会主義思想の誕生 保守主義が文明社会を貴族主義的リーダーの下に従属させ、その弊害を矯正しようとするのに対して、文明社会のあり方そのものに疑問を持ち、その否定を唱える社会主義が登場してくる。 それは豊かな文明社会の持つ暗い面、(貧困、不平等の広範な存在、資本家と労働者との階級対立)を主張する。また、このことが人間の道徳的・政治的発展にとって大きな阻害となっていることを主張する。 サン・シモン 彼は18世紀以来の産業社会の到来に注目した。 ■ 歴史の動向 軍事的段階→→→→→産業的段階へと向かっている ■ 社会の中核となる 身分的秩序の人々(旧来)→→→産業活動に従事する人々(今) 旧来の身分的秩序に代わって産業活動に従事する人々がいまや社会の中核になりつつある。 反身分制的産業社会は人間に対する人間の支配を含まない、基本的に平等でもっぱら人間による物の管理に尽きるものとして描かれている。この偉大な進歩は、現実には自由放任主義や個人主義(エゴイズム)のためにまだ実現されていない。これと対決するためには、新しい社会秩序を作らなければならない。 そこで彼は産業社会の自由放任とその結果としての経済的無秩序に反対し、全体的視野を持った経済エリートを頂点とする産業の組織化の必要を説く。したがって指揮命令関係自体は存在しているが、それは国民経済の発展と生産という共通の目的を前提にした、いわば技術的な指揮命令関係である。 かくして政治の問題は技術的問題に還元される。
- レポート 政治学 サン・シモン 社会主義 エゴイズム 政治思想
 550 販売中 2005/10/16
550 販売中 2005/10/16- 閲覧(1,701)
-
 新アメリカ政治史
新アメリカ政治史
- アメリカにおける政党の発展と有権者の意識
 1,100 販売中 2010/07/02
1,100 販売中 2010/07/02- 閲覧(1,484)
-
 政治学原論3
政治学原論3
- 憲法制定時の状況 占領軍による憲法制定が進められており、これに口出し、批判すると公職追放されてしまうことになってしまう恐れがあった。さらに天皇制の廃止を避けることに重点がおかれていたため、9条の議論については積極的に行われていなかった。 しかし、そのような状況においても帝国議会においては後の議論よりはるかに自由な意見が出ている。例えば、後の護憲の中心政党の社会党や共産党議員ですら自衛権の重要性を認識した発言をしている。全面講和の急先鋒である南原繁議員も貴族院で、国連に加盟した場合に軍事的制裁に貢献する権利と義務を放棄してしまうことは「人類の自由と正義を擁護するがために、互いに血と汗の犠牲を払うことによって相共に携えて世界恒久平和を確立するという積極的理想は、却ってその意義を失われるのではないか」と、湾岸戦争で非難を浴びてしまった日本を予言しているかのような発言まである。 その一方で9条に賛成する意見も出てきている。横田喜三郎は国連に日本の安全保障を求め、自衛権の行使は国際連合が必要な措置を採る間に限るとした。国連における武力制裁の参加に関しては、戦争に参加せず、参加しないことが同意され
- 政治学 東洋大学 通信教育課程
 550 販売中 2008/03/17
550 販売中 2008/03/17- 閲覧(1,218)
-
 公務員の政治活動の制限
公務員の政治活動の制限
- 公務員の政治活動の制限について 憲法21条1項の保障する表現の自由に由来する政治活動を行う権利は、絶対無制限のものではないばかりでない。 それは全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない国家公務員の身分を取得することにより、ある程度の制約を受けざるを得ないことについては議論の余地はない。 従って政治活動を行う国民の権利の民主主義社会における重要性を考えれば、国家公務員の政治活動の制約の程度は、必要最低限のものでなければならない。 公務員の政治活動の合憲性を争った事件として代表的なものとして、猿仏事件(最判昭49.11.6)が挙げられる。行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保することは
- 法学 公務員 政治活動
 550 販売中 2008/06/06
550 販売中 2008/06/06- 閲覧(2,749)
-
 近代日本の政治の歴史
近代日本の政治の歴史
- 憲法発布後10年 藩閥勢力‐「超然主義」「超然内閣」 政党ではなく藩閥が一致協力して天皇にかわって国政の責に任ずる 初期議会期 「超然内閣」vs「民党」 憲法第67条 議会の予算審議権の制限の問題 政府vs衆議院 明治24/5/6 第一次松方内閣 民党「政費節減・民力休養」に対抗し積極政策 第二次伊藤内閣 1893/2 「和協の詔勅」 日清戦争後、政府、政党との提携を求め始める(政党と政府の利害の一致?) 1896(明26)/4 自由党総理板垣退助の内務大臣就任 明治29 第二次松方内閣 進歩党と提携、党首大隈重信外相主任 保守系官僚グループの反発(元老山県有朋) 1900(明33)/9 伊藤系官僚グループと自由党(憲政党)が合同、立憲政友会 進歩党(憲政本党)は野党 第二次松方内閣、地租増徴案に反発 進歩党は同内閣と提携を断絶→総辞職 1898(明31)/1/12 第三次伊藤内閣 増税案→自由党離れる 自由党、進歩党合同、憲政党に(6月)(衆議院の3分の2近く) 増税案不可能に、伊藤内閣総辞職 6/30 第一次大隈内閣 日本初の政党内閣 酒税大幅増徴(軍拡の代償) 憲政党、憲政党(旧自由党)、憲政本党(旧進歩党)に分裂、政党内閣崩壊 11/8 第二次山県内閣(保守系官僚グループ) 地租増徴案 憲政党‐賛成、伊藤系官僚に好印象 憲政本党‐反対 1900(明33)/8 伊藤系官僚グループと憲政党が合同、立憲政友会 10/19 第四次伊藤内閣 過半数政党は政友会 陸海軍大臣、外相以外は政友会員 首相、内、蔵、法相は伊藤系官僚からの入党者
- レポート 政治学 日本政治 戦前 超然内閣
 550 販売中 2006/01/11
550 販売中 2006/01/11- 閲覧(3,069)
-
 マスメディアが政治に与える影響
マスメディアが政治に与える影響
- ■テーマ設定の動機 マスメディアは新聞やテレビなどの形で存在しており、近年急速に普及したインターネットもマスメディアの一つということができる。私自身政治に関する情報を見聞きするのはすべてといっていいくらいマスメディアを介してのものである。もはやそれは当たり前になりすぎていることではあるが、元々は別のものであるはずである。そこで今回はその「マスメディア」が政治に与える影響についてスポットをあててみることにする。 ■現代における「マスメディア」の位置 まず、現代において「マスメディア」がどのような位置に存在しているかについて考える。 そもそもマスメディアが存在しなかった時代には政治権力と大衆は隔絶されており、両者相互を通じ合わせる媒介はほとんど存在しなかった。独裁制をとっていたならなおさらである。しかしその後マスメディアや普通選挙制の確立などにより両者は除々に密接に関係するようになってきた。現代においては大衆の自主性を尊重する民主政治では大衆に十分な情報を提供するために使用される。(また独裁体制下においても大衆動員のためにマスメディアは必要不可欠なものになっている。) これは民衆の「知る権利」に応えるためでもあり、具体的には政策や国家のPR活動、また経済面、国際面などのニュース報道の形となってあらわれている。 またマスメディアは権力側からだけでなく大衆側から発せられるものもある。それは主に世論調査、投書、社会面ニュースなどのものである。そもそも政治権力が大衆より先走ったり立ち遅れたりしていては正しい政策を打ち出すことはできないのである。相互が密接に関係しているといわしめたるゆえんである。 このような意味でマスメディアは現代の政治そのものを成り立たせているといえる。マスコミの媒介なしには政治そのものが存在しえなくなるといっても全く過言ではないのである。
- レポート マスメディア 政治学 情報 マスコミ センセーショナル 扇動 煽動 加熱報道 やらせ 報道 癒着
 550 販売中 2006/01/13
550 販売中 2006/01/13- 閲覧(19,383)
-
 政治家の選挙活動
政治家の選挙活動
- この章では、候補者が選挙で勝つためにどのようなことをするかが述べられている。党の公認を受けた候補者は、選挙でどう勝つかということに関心を持つようになる。日本の候補者は具体的にどのような選挙戦略と立て、行動するのか述べていくことにする。 まず、選挙でどう勝つか、ということであるが、それは、選挙制度だけが原因ではない。「候補者がどの集団を重視し、どの集団を軽く見るかは、選挙制度が教えてくれるものではない。選挙戦略というものは、選挙区内で長い時間をかけて作られてきた具体的な人間関係を背景として立てられるものである。また、選挙制度が変わっても、支持者を動因する基本論理に変わりがあるわけではない。」と述べられている。小選挙区制の導入により、当落の基準が変えられた。それによって、より狭い地域の中で、より多くの支持者を動員しなければならなくなったのである。では、その支持者を動員するために具体的にどのようなことがなされるのであろうか。3つの論理について考えてみる。 小選挙区制のように、少しでも多くの支持者を集めるためには、さまざまな論理が働く。まず、第一に、包接と排除の原理である。この論理は、まず、選挙戦略を立てることから始まる。選挙区民のすべてを自分の支持者にしようとするのではなく、自分に票をくれないであろうと考えられる人には初めからキャンペーンの対象外とする。それまでの歴史的な流れの中で形成されてきた中核者を中核として、政治活動を始める。こうすることにより、中核的な支持者を裏切れなくなり、さらに、敵視してきた集団に手を伸ばせなくなる。第二に、統合と拡張の論理である。これは、自分の足元の固定票を固めた上で、その外側にいる有権者に支持を呼びかけるという方法である。この方法では、成功するかどうかは、党組織の柔軟性と開放性にかかっている。
- レポート 経済学 選挙 政治家 候補者
 550 販売中 2006/01/16
550 販売中 2006/01/16- 閲覧(1,282)