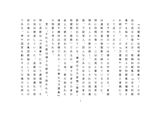代表キーワード :: 日本文学
資料:184件
-
 山椒魚について
山椒魚について
-
井伏文学はヒューマニズム文学とはいえ、暖かく、穏やかで、けっして極端ではない。普通、無力の主人公の無力な抵抗を利用して、自分のまた人並みの日本人の悲しみや嘆きなどの気持ちを表し出したのだ。井伏鱒二氏は今の時代の人々がたぶん理解できないが。しかし、思想的な一つの...
 550 販売中 2005/11/06
550 販売中 2005/11/06- 閲覧(1,214)
-
-
 今昔物語集における天狗
今昔物語集における天狗
-
天狗と聞いて多くの人が想像するもの。それは、真っ赤な顔をし、長く大きな鼻を持ち、白い山伏のような衣服を纏ったものだろう。翼が生えていて、羽団扇をもっている、という特徴もある。 私は、天狗といっても、特にこれといった思い浮かぶエピソードもないのだが、中世では、天...
 550 販売中 2006/02/09
550 販売中 2006/02/09- 閲覧(5,574)
コメント(1)
-
-
 箱男を読んで
箱男を読んで
-
箱男とは、ダンボールの箱を頭からすっぽり被り、街を徘徊する人間のことである。箱に開けられた小さな穴から外世界を覗くことはできるが、外世界からは自分の姿を見られることはない。また、箱男とは、浮浪者や乞食とは異種の存在なのである。浮浪者や乞食はかろうじて社会の一員...
 550 販売中 2006/01/12
550 販売中 2006/01/12- 閲覧(2,133)
コメント(2)
-
-
 「知の基本武装 言葉」について
「知の基本武装 言葉」について
-
「リンゴが木から落ちる」「木から落ちるリンゴ」似たような一文であるが前者は目に見えない事柄であり、後者は目に見えるものを意味している。言葉とはもともと「言の葉」つまり「ことの端」のことです。「こと」とは物事で、「端」は物の隅、はし、の意味です。だから、言葉=「...
 550 販売中 2005/11/03
550 販売中 2005/11/03- 閲覧(1,519)
コメント(1)
-
-
 三四郎(夏目漱石)
三四郎(夏目漱石)
-
「三四郎」を読んで 時代を反映した小説を著してきた漱石は「三四郎」でも、明治の時代に対して警告を鳴らした。明治42年に朝日新聞に連載された「三四郎」は、新聞小説がリアルタイムに情報を発信できるという特性を生かして、社会批評を客観的かつ冷静に展開している。例えば...
 550 販売中 2007/09/25
550 販売中 2007/09/25- 閲覧(4,650)
-
-
 夏目漱石の作品
夏目漱石の作品
-
夏目漱石の作品は、自伝的な要素を含んだものが多い。どの時期に書いたのか、それが分かればその時の作者の実際の心情が作品から伺うことが出来る。「自転車日記」などはその通り日記調で、一つの小説というよりまるで本当に漱石の日記であるかのように読むことが出来る。そして、...
 550 販売中 2005/12/09
550 販売中 2005/12/09- 閲覧(6,917)
コメント(55)
-
-
 額田王と大海人皇子の贈答歌について
額田王と大海人皇子の贈答歌について
-
私は額田王と大海人皇子の贈答歌のうち二一の歌に絞って、二人の関係、歌に込められた想いを調べた。以前は愛し合っていた二人だが、額田王は天智天皇に仕えてしまった。大海人皇子はどのような気持ちでこの歌を返したのだろうか。また、この歌はなぜ雑歌に分類されているのかを考...
 550 販売中 2006/07/18
550 販売中 2006/07/18- 閲覧(3,439)
-
-
 『万葉集』の特質と意義
『万葉集』の特質と意義
-
『万葉集』は現存最古の和歌集で、この作品の成立以降には、勅撰和歌集の『古今和歌集』を始め、日本では数々の和歌集が編纂され続けた。この『万葉集』の特質と意義について述べてみたい。 まず特質の一つは様々な作者である。冒頭は雄略天皇の御製歌で飾られているように、特に...
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03- 閲覧(2,189)
-
-
 「伊豆の踊子」に描かれる悲劇
「伊豆の踊子」に描かれる悲劇
-
私はこのレポートを書くために、初めて「伊豆の踊子」を読んだ。小学生の頃に漫画化された「伊豆の踊子」を読んだこともあったが、それが少女漫画だった所為もあり「伊豆の踊子」は新潮文庫の裏表紙に書かれたような「美しい青春の譜」であると信じきっていた。しかし、実際に読ん...
 550 販売中 2006/04/10
550 販売中 2006/04/10- 閲覧(3,437)
コメント(1)
-
-
 二十四の瞳
二十四の瞳
-
戦争という時代を背景に主人公の大石先生とその教え子である十二人の子供たちの成長を描いた作品です。苦しみながらもそれを乗り越え懸命に生きる彼らの姿が描かれています。貧しくても平和だった彼らの生活を崩したのが戦争でした。十二人の教え子のうち三人が戦死、一人が失明、...
 550 販売中 2006/07/26
550 販売中 2006/07/26- 閲覧(5,136)
コメント(1)
-
-
 怨霊について
怨霊について
-
「京都異界実地調査」で早良親王が祭られている上御霊神社を調べてきたので、今回の授業レポートはその延長、怨霊について書くことにした。 平安時代の人々は御霊信仰を生活の規範にしていた。たとえば結婚式は大安の日に行い、友引の日は葬式をしないなど、いくつかの習慣は現代...
 550 販売中 2006/04/06
550 販売中 2006/04/06- 閲覧(1,844)
-
-
 午後の曳航
午後の曳航
-
13歳の主人公は自分が天才であること、世界はいくつかの単純な記号と決定で出来上っていること、父親や教師は存在自体が害悪であることを知っている。彼の父が他界して5年が経つが、母親は今、息子が抽出の小さな穴から盗み見ているともしらず、とある二等航海士との情事にふけ...
 550 販売中 2005/07/17
550 販売中 2005/07/17- 閲覧(3,224)
コメント(1)
-
- 資料を推薦する
- 優良な資料があれば、ぜひ他の会員に推薦してください。
資料詳細ページの資料右上にある推薦ボタンをクリックするだけでOKです。
- 会員アイコンに機能を追加
- 会員アイコンをクリックすれば、その会員の資料・タグ・フォルダを閲覧することができます。また、フレンドリストに追加したり、メッセージを送ることも可能です。
- ファイル内検索とは?
- 購入を審査している資料の内容をもう少し知りたいときに、キーワードを元に資料の一部内容を確認することができます。
広告
 今昔物語集における天狗
今昔物語集における天狗
 550 販売中 2006/02/09
550 販売中 2006/02/09 「知の基本武装 言葉」について
「知の基本武装 言葉」について
 550 販売中 2005/11/03
550 販売中 2005/11/03 額田王と大海人皇子の贈答歌について
額田王と大海人皇子の贈答歌について
 550 販売中 2006/07/18
550 販売中 2006/07/18 『万葉集』の特質と意義
『万葉集』の特質と意義
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03 「伊豆の踊子」に描かれる悲劇
「伊豆の踊子」に描かれる悲劇
 550 販売中 2006/04/10
550 販売中 2006/04/10