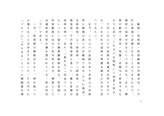代表キーワード :: 日本文学
資料:184件
-
 額田王と柿本人麻呂の作品について
額田王と柿本人麻呂の作品について
- 額田王は、万葉集初期の女流歌人である。その出自・経歴年・生没年は不明である。それは、額田王について伝える資料がごく限られていることによる。万葉集の十二種の作品と、日本書紀に「天皇、初め鏡王の女額田姫王を娶して、十市皇女を生しませり」という一文以外に伝えるものは...
 550 販売中 2006/01/14
550 販売中 2006/01/14- 閲覧(4,840) コメント(2)
-
 源氏物語における斎院の考察
源氏物語における斎院の考察
- この場面は、女三宮が斎院になり、儀式・御禊をするところである。 斎院とは何なのか。また、儀式とは何なのか。 「斎院」について、『源氏物語有職の研究』には、「天皇即位の度毎に、その命に依り賀茂神社に奉仕する、未婚の内親王若くは女王。(中略)初め斎院に卜定がある...
 550 販売中 2006/03/13
550 販売中 2006/03/13- 閲覧(2,329)
-
 『途上』における探偵要素
『途上』における探偵要素
- はじめに 『途上』はこの短編作品の中で数少ない探偵小説的要素を持っている作品である。物語には探偵と話をしているうちに追い詰められていく犯人の描写がうまく書かれている。これを読んだ江戸川乱歩が「海外にも類例のない探偵小説」と絶賛し、この作品を紹介するために「プロ...
 550 販売中 2006/12/02
550 販売中 2006/12/02- 閲覧(3,615)
-
 中学国語科模擬授業案 枕草子について
中学国語科模擬授業案 枕草子について
- 国語科教科教育法A 模擬授業指導案 一二〇四〇五三 小林由布子 授業テーマ : 「古典を身近に読もう!」 設定学年 : 中学二年生 教材・使用目的 : 『枕草子』(第一段) 清少納言 『桃尻語訳 枕草子(上)』 橋本治 一年生で古典の導入(『竹取物語』)を学び、苦手意識が芽生え...
 550 販売中 2007/09/26
550 販売中 2007/09/26- 閲覧(10,597)
-
 平安文学に見る内裏・後宮
平安文学に見る内裏・後宮
- 『源氏物語』の「桐壺」に見られる内裏・ 後宮のかかわりについて 1.はじめに 平安時代の後宮の発展により、ここに住む女性達によって作り出された女流文学も洗練され、一層リアルに近づいたものとなった。 その中でもあまりにも有名な『源氏物語』では、内裏・後宮はどのように...
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03- 閲覧(1,490)
-
 動詞・形容詞の共通点と相違点
動詞・形容詞の共通点と相違点
- 動詞・形容詞・形容動詞の共通点は、いずれも単独で述語となることができるもので、語形に活用があるという点である。また、事物の動作・存在・性質・状態など叙述するものでもあり、この三つを総称して用言と呼ぶ。 ではこの三つの品詞の相違点は何であろうか。それぞれの品詞の...
 550 販売中 2010/08/03
550 販売中 2010/08/03- 閲覧(3,408)
-
 佛教大学 M6104 日本文学概論 第1設題
佛教大学 M6104 日本文学概論 第1設題
- 『最新版』 佛教大学通信教育課程の合格済みレポートです。 ●図書館で資料を集めてから作成。参考文献も記載しています ●文章構成やレイアウトにも気を配りました。 ●設題の意図を正確に捉え簡潔にまとめています。ぜひ参考にしてください。
 1,100 販売中 2014/03/26
1,100 販売中 2014/03/26- 閲覧(1,869)
-
 東海道四谷怪談について
東海道四谷怪談について
- まず注目すべき点としては、この作品には「忠臣蔵」の世界と関わりを持つ登場人物が出てくる、とう事が挙げられる。 『東海道四谷怪談』を読んでみると、まず、この四谷怪談は「仮名手本忠蔵」の脇筋の仇討ち話になっていることに気づく。すなわち、伊右衛門は忠臣蔵の浅野(仮名...
 550 販売中 2005/07/09
550 販売中 2005/07/09- 閲覧(2,470) コメント(2)
-
 日本文学に見る楊貴妃像
日本文学に見る楊貴妃像
- 理想的な美人像は固有名詞に託されて語られることが多い。いくら美しい女性でも、「伝説」がなければ、永遠に語り継がれる美女にはならない。実際に顔立ちが美しかったかどうかよりも、男達がいかに魅惑されたかのほうが、興味をそそられるものである。中国では、西施などの美人像...
 550 販売中 2005/11/11
550 販売中 2005/11/11- 閲覧(4,727) コメント(39)
-
 七夕の由来 七夕ものがたり・乞巧奠・民間の七夕とのかかわりについて
七夕の由来 七夕ものがたり・乞巧奠・民間の七夕とのかかわりについて
- 夏の風物詩である七夕は、牽牛・織女の七夕ものがたりと、中国伝来の乞巧奠の風習とが習合したものであると言われている。この七夕ものがたりと乞巧奠について概説しながら、現在の日本の七夕に至るまでを述べていく。 この七夕ものがたりの内容は「機織仕事をしていた織女が、牽...
 550 販売中 2005/12/05
550 販売中 2005/12/05- 閲覧(3,008) コメント(2)