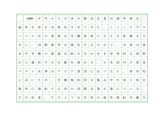連関資料 :: 日本の経済について
資料:153件
-
 日本経済史-分冊2 合格リポート
日本経済史-分冊2 合格リポート
- 戦前から戦時期までに形成された日本経済は、戦争によって形成された経済であった。その連続的側面と非連続的側面について、ここでは以下のように定義づける。 連続的側面・・・戦前から戦時期にかけて連続した経済政策。 非連続的側面・・・戦前から戦時期そして戦後にかけて、連続することなく途切れた、もしくは新たに発生した経済政策。 戦時期から戦後経済にかけて述べるには、その経緯について知る必要がある。 統制経済とは国家が資本主義的自由経済に干渉したり、これを規制したり、計画化する経済のことである。この統制経済が始まったのは、軍需増大を見越した輸入増により国際収支が危機に陥った1937年の輸入為替管理令からである。その後日中戦争が勃発し、臨時資金調整法や輸出入品等臨時措置法等が相次いで制定された。この経済統制は緊急度が高い分野から実施され、次々と経済統制に関する法律が制定され、この経済統制が本格化したのである。この時代では外貨不足が最大の懸念事項であり、経済統制についても外貨不足問題が強い規制力を持っていた。また、これらの規制により民需生産は徹底的に抑圧され、軍需生産への切り替えが進められ
- 日本大学 通信教育部 0722 日本経済史 戦前 戦後 連続 不連続 分冊2
 2,200 販売中 2008/12/26
2,200 販売中 2008/12/26- 閲覧(3,040)
 6
6
-
 消費税の引き上げが日本経済に及ぼす影響
消費税の引き上げが日本経済に及ぼす影響
- 消費税の引き上げについて 1 消費税引き上げ論 2007年10月、内閣府直属の経済財政諮問会議が「財政を黒字化した上で医療・介護給付の水準を維持するためには2025年度に約14兆~31兆円分の増税が必要となり、消費税でまかなうなら11~17%まで税率を引き上げる必要がある」と現行と比べて最大で12パーセント消費税率を引き上げる可能性がある試算を公表した。 2008年(平成20年)10月30日、麻生首相は消費税率について、「大胆な行政改革を行った後、経済状況を見た上で」と断った上で、「3年後に消費税の引き上げをお願いしたい」と述べた。具体的な上げ幅について言及はなかったが、上げ幅を5%とし、最終的に10%とする案を検討していることが報じられている。この3年後というのはあくまでも目安であり、景気が悪いときに消費税を上げては経済に更なる悪影響を及ぼすため、実態としては 景気が良くなったときであるとみられる。そして11月27日、政府の経済財政諮問会議(議長・麻生首相)が年末までにまとめる税制抜本改革の「中期プログラム」の骨格案が明らかになった。骨格案は、高齢化で急増する社会保障費について「消費
- 経済 社会保障 社会 企業 医療 消費 国際 消費税 GDP
 550 販売中 2009/07/06
550 販売中 2009/07/06- 閲覧(3,255)
-
 日本経済史-分冊1 合格リポート
日本経済史-分冊1 合格リポート
- 明治時代から第一次世界大戦の間は日本経済にとって最大の転換点であったと言って過言ではない。なぜなら在来産業と呼ばれる明治維新前の国内に発達の起源を持つ伝統的な産業から、産業革命を経て、工場制大工業・機械制工業として成長し、近代産業型の経済へと成長したためである。この大規模な経済成長を多面的に捉えようと試みると、連続および不連続という側面が見えてくるのである。それは産業革命によるところがその一因である。産業革命とはイギリスから欧州諸国へ波及し、その後に日本に波及した革命である。経済を取り巻く産業の技術的基礎が一変し、工場制手工業(マニュファクチュア)や小規模生産者から大規模機械制工業へ移行し、生産効率が飛躍的に向上した。江戸時代末期から明治時代初期にかけては、工場制手工業や小規模生産者を中心とした綿織物業や絹織物業を代表とした低生産性産業に支えられた経済であった。それは日本経済の基礎的条件が脆弱であったとも換言することができる。しかし産業革命により日本にも資本主義の考え方が主流になり、資本主義の影響による会社制度の発展や生産効率を向上させる機械の導入、大幅に輸送効率を高める蒸気機関車の
- 日本大学 通信教育部 0722 日本経済史 在来産業 連続 不連続 分冊1
 2,200 販売中 2008/12/26
2,200 販売中 2008/12/26- 閲覧(2,870)
-
 日本が今後、東アジアにおいてとるべき経済戦略とは
日本が今後、東アジアにおいてとるべき経済戦略とは
- 日本が今後、東アジアにおいてとるべき経済戦略とは 現在の日本経済の現状としては、少子高齢化、原油高、株安、物価上昇などにより、スタグフレーションという最悪の状態になりつつある。我々の世代では、バブルの時期がまだ幼少期であったため、バブルの記憶もなく、「失われた10年」や「デフレスパイラル」などという嫌なイメージの言葉ばかりの中で生きてきた。また、バブル崩壊から十数年を要しジュグラーの波のような長さで谷にたどり着き、景気回復をしたと思いかけたところでキチンの波のような速さで山へ、そして景気後退という状況は若者が希望を持てなくなる気持ちもわかる。それがまたスタグフレーションとなれば、なおのことであろう。 しかし、現在東アジアの経済成長は大きなチャンスであると言えるだろう。中国の経済は日本のバブルのようだとする見方もあるが、13億人の人口はそれだけで力となるであろうし、また、シンガポールもGDPで日本を上回るなど、東アジアを無視した日本の未来はないと考える。そこで私は、東アジア共同体、また、共通通貨の実現を日本が目指すべきと考える。 現在、日本の諸外国との貿易、特にアジアとの貿易(輸出)
- 東アジア レポート 政治 経済 グローバル 中国 韓国 東海大学
 1,100 販売中 2009/01/12
1,100 販売中 2009/01/12- 閲覧(2,037)