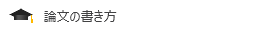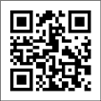資料紹介
ジェンダークィア、あるいはジェンダーの自由の公正な分配 --「トランスジェンダリズム」批判
1.はじめに 私も編集段階から関わった書に、 『トランスジェンダリズム宣言・性別の自己決定権と多様な性の肯定』 がある。この書は、性別の越境について、「性同一性障害」というものの見方に対して、「トランスジェンダー」(これの意味するところは後で論じる)という見方を提示するものであった。この書が出版されてから2年、その間に「性同一性障害特例法」の成立・施行、それに付随するマスメディアでの「性同一性障害ブーム」があり、情勢は大きく変わった。それと共に、「トランスジェンダー」というあり方の意味するものも、大きく変質したのではないかと思う。本文は、この書の出版と、それに関連した動きについての、私なりの総括である。 この点、提示された「トランスジェンダリズム」とは、最大公約数的に見て、性別を個人の意思により自己決定できるものと考えることを論じていた。これは、生まれながらの性別に違和感を感じることを「性同一性障害」という疾患と捉え、治療の対象とする考え方に対してのアンチテーゼであった。 そして、その性別の自己決定を阻むものが、性別は男女の二つに限り、また「男らしさ」「女らしさ」を固定的に捉える性別二元論と、それに基づいて造られた社会制度であり、この社会制度を改め、性別をゆるやかに捉えることが性別に関する個人の自由を保障する、というものであったはずである。 しかし、今日「トランスジェンダリズム」といえば、個人の生き方、あるいは生き様の問題であると捉えられている。そこでは、性別二元論や社会制度への批評は、既に影をひそめている。性同一性障害批判という形で展開されていた医療批判は、医療を自由に使いこなす個人の存在が確立されることを条件に、既に解決済の感がある。
ここで、性別の問題は個人の問題であり、単に個人が努力すれば解決できる問題なのであろうか。もちろん、ここで直ちに社会の問題であるという結論を出すには、慎重でなければならないかもしれない。既に、性別に関するバックラッシュの環境の中で、どれだけの説得力を持ちうるのかは、慎重に見極められなければならない。 しかし、個人の問題と捉える限り、性別に関してよりよい生活を得られる者は、ごく一部の勝ち組、それも本人の努力とは関わりないところで決定される勝敗による、でしかないことについて、「性別の自己決定権」論者は、今後どのような回答をするのか。 私はここで、性別違和を疾患と見なす「性同一性障害」の立場に回帰するつもりは全くない。しかし、「性同一性障害」の立場の方が、結果として多くの当事者のニーズをすくいあげたことは直視すべきであると思う。言い換えれば、自由に自己決定できない状況のもとにいる者の声を、「性別の自己決定」論者は、どれだけ耳にしてきたのか。
本来、自己決定権は、自由主義経済下で、「弱者」「マイノリティ」という地位に置かれた者に、「強者」「マジョリティ」と対等な資格を与えるという扱いをすることにより、その者が持つ文化的背景を尊重するという戦術であったはずである。 むしろ求めるべきなのは、文化的背景の複数性を許容するシステムであり、性別の多様性の問題もその中で位置づけられるべきである。すなわち、ジェンダーについてクィア(変態)なものが共存するシステムである。自己決定権は、この複数性を承認するための、自由主義経済下での手段でしかないはずである。
2.トランスジェンダリズムの変質 『トランスジェンダリズム宣言』(社
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
ジェンダークィア、あるいはジェンダーの自由の公正な分配 --「トランスジェンダリズム」批判
1.はじめに 私も編集段階から関わった書に、 『トランスジェンダリズム宣言・性別の自己決定権と多様な性の肯定』 がある。この書は、性別の越境について、「性同一性障害」というものの見方に対して、「トランスジェンダー」(これの意味するところは後で論じる)という見方を提示するものであった。この書が出版されてから2年、その間に「性同一性障害特例法」の成立・施行、それに付随するマスメディアでの「性同一性障害ブーム」があり、情勢は大きく変わった。それと共に、「トランスジェンダー」というあり方の意味するものも、大きく変質したのではないかと思う。本文は、この書の出版と、それに関連した動きについての、私なりの総括である。 この点、提示された「トランスジェンダリズム」とは、最大公約数的に見て、性別を個人の意思により自己決定できるものと考えることを論じていた。これは、生まれながらの性別に違和感を感じることを「性同一性障害」という疾患と捉え、治療の対象とする考え方に対してのアンチテーゼであった。 そして、その性別の自己決定を阻むものが、性別は男女の二つに限り、また「男らしさ」「女らしさ」を固定的に捉える性別二元論と、それに基づいて造られた社会制度であり、この社会制度を改め、性別をゆるやかに捉えることが性別に関する個人の自由を保障する、というものであったはずである。 しかし、今日「トランスジェンダリズム」といえば、個人の生き方、あるいは生き様の問題であると捉えられている。そこでは、性別二元論や社会制度への批評は、既に影をひそめている。性同一性障害批判という形で展開されていた医療批判は、医療を自由に使いこなす個人の存在が確立されることを条件に、既に解決済の感がある。
ここで、性別の問題は個人の問題であり、単に個人が努力すれば解決できる問題なのであろうか。もちろん、ここで直ちに社会の問題であるという結論を出すには、慎重でなければならないかもしれない。既に、性別に関するバックラッシュの環境の中で、どれだけの説得力を持ちうるのかは、慎重に見極められなければならない。 しかし、個人の問題と捉える限り、性別に関してよりよい生活を得られる者は、ごく一部の勝ち組、それも本人の努力とは関わりないところで決定される勝敗による、でしかないことについて、「性別の自己決定権」論者は、今後どのような回答をするのか。 私はここで、性別違和を疾患と見なす「性同一性障害」の立場に回帰するつもりは全くない。しかし、「性同一性障害」の立場の方が、結果として多くの当事者のニーズをすくいあげたことは直視すべきであると思う。言い換えれば、自由に自己決定できない状況のもとにいる者の声を、「性別の自己決定」論者は、どれだけ耳にしてきたのか。
本来、自己決定権は、自由主義経済下で、「弱者」「マイノリティ」という地位に置かれた者に、「強者」「マジョリティ」と対等な資格を与えるという扱いをすることにより、その者が持つ文化的背景を尊重するという戦術であったはずである。 むしろ求めるべきなのは、文化的背景の複数性を許容するシステムであり、性別の多様性の問題もその中で位置づけられるべきである。すなわち、ジェンダーについてクィア(変態)なものが共存するシステムである。自己決定権は、この複数性を承認するための、自由主義経済下での手段でしかないはずである。
2.トランスジェンダリズムの変質 『トランスジェンダリズム宣言』(社会批評社,2003)は、そもそもは、治療の対象としての「性同一性障害」に対するアンチテーゼとして、自己決定による性別選択という概念を提示したものである。しかし、「性同一性障害」が性別二元論を前提として、「治療」という形でのそのどちらかへの完全な移行を目指したものであるのに対して、「トランスジェンダリズム」は、「性別に対する認識をゆるやかに」(p.209)と主張し、戸籍や住民基本台帳ネットなどの制度的性別の撤廃を求めたものであった。すなわち、「自己決定権」という切り口から、個人の性別に関する自由を束縛する制度への批評が込められていた。 もっとも、一方で米沢泉美は「トランスジェンダリズム」について、
そして本書が唱えるトランスジェンダリズムは、デフォルトセッティング(性役割が予め生まれながらの性別により固定されていること:引用者註)からの自由、そして社会とのかかわりの中での自己肯定という回路をもって、トランスジェンダーの社会生活・自己主張を行う思考、感覚、生き様を指している、とお考えいただきたい。(『トランスジェンダリズム宣言』p.181)
と記し、その解決を究極的には個人の努力の問題としている。 また、三橋順子は、その後に著された論文において以下のような定義を試みている。
これ(性同一性障害:引用者註)に対して、性自認と身体の性別のずれをどのように認識するかは、個人的な問題であって、医学によって一方的に不健全か健全かを決められたくはないと考える人たちがいます。性自認と異なる身体を持ちながら社会生活を送ることはいろいろな困難や苦痛をともなうが、それは自分で折り合いをつける問題であり、ずれを「個性」のひとつと考えれば、ずれを抱えたままでも社会生活を送れると考えます。(三橋順子『性別を越えて生きることは「病」なのか』,情況2003年11月号)
三橋の所論については、性別越境者(トランスジェンダー)が「障害者」と呼ばれることに抵抗を覚えるということについて、身体などに障害をもつ者に対する差別感があるのではないかという別の問題があるが、この点については論旨がそれるため割愛する。
ここでは、そもそも「自己決定論」が目指したものは何かを再検討してみよう。自己決定権とは、他者の権利を害しない限り、個人の私的なことがらについて、他者に干渉されずに自由に意思決定できる権利のことを言う。もともとは市民革命期に端を発する、新興の支配階級の思想であったが、1970年代の人工妊娠中絶の問題を皮切りに、支配的でないジェンダーやセクシュアリティをもつ者にとっては、社会において支配的な価値観や社会制度による干渉を拒む、理論上の根拠となった。 そして、「トランスジェンダリズム」が「性別の自己決定」を要求するのなら、それは生まれながらに二つの性別のどちらかに固定し、それに対応する性役割を強いるマジョリティの文化に対する異議申立てであったはずである。それは、男/女という二分法にとらわれない、異なる文化の存在の表明でありうるはずである。
しかしこれが、単なる「個人の生き様」としての性別越境を意味するなら、それは異議申立てであるどころか、マジョリティの文化の中に一定の位置を占めただけのことにしかならないであろう。性別二元論の枠組みを変えないまま、「第三ジェンダー」を特例として認めるだけであれば、「性別の変更」を疾患の治療を理由に特例として認める、性同一性障害の枠組みとどれほど違いがあるのであろうか。 そもそも、「自己決定権」という戦術は、1980年代から今日に至る、レーガン政権・ブッシュ父子政権下の「新自由主義」イデオロギーが支配的になる中で、歪曲されていった可能性がある。ウーマンリブにおいても、80年代以降、女性は以前より十分に権利を得たから、後は個人の生き様が問題になるだけであり、フェミニズムは役割を終えたとの、ポストフェミニズムと呼ばれる論調が目立った。 この点、自己決定が社会のマジョリティのもつ規範を受け入れ、その下での競争へ参加する資格を保障するだけであるなら、それは単なる同化主義である。トランスジェンダーについて言えば、医療による治療を選択し、法律上の性別変更を選択することにより、社会の多数派に編入する自己決定のみが推奨されるなら、そもそも立論の意義がどれだけあったということなのか。 今や以前とは異なり、医療や法律(性同一性障害特例法)の助力を借りれば、というよりそれらが推奨する規範に乗るという選択をすれば、トランスジェンダーであってもそれなりの受け入れを社会に求めることもできるようになった。
しかし、その選択肢をとることができない者も数多くいる。経済的理由、家庭環境、雇用環境、地域社会の環境、身体的理由、宗教的理由、その他さまざまな事情で、医療やそれを前提とする法律上の性別変更を受けられない、あるいは自己の意思によりそれを行わない者は数多く残されている。あるいは、トランスジェンダーではない者も含めて、不当な性役割の押しつけに甘んじている者はそれ以上に多い。そもそも、性差別の問題は、個人の自由意思による選択、個人の能力ではどうにもならない制度の問題であったはずである。 「個人的なことは政治的なことである」(Personal is political)という、ラディカル・フェミニズムの標語がある。ジェンダーの問題は公的領域からは無視されて来たところ、個人的自由の問題は政治問題であることを言い表したものである。これに対し、自己決定の問題を単に生き様の問題としてのみ捉えるなら、むしろそれはジェンダーの公正の獲得に向けた動きに逆行するものである。
3.トランスジェンダーからジェンダークィアへ---ジェンダーの自由の公正な分配について ここで、私はあえて初心に戻りたいと思う。性別の越境について当事者が被る不公正については、ジェンダーの公正の獲得により解決されるべきであると。 もう少し敷衍すれば、ジェンダーの問題はすべての...