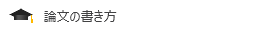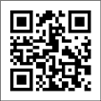資料紹介
不確定性原理
歴史を振り返らないと見えないものがある。
私の疑問
「不確定性原理」という言葉を聞いたことがあると思う。 解説はそこら中にあふれている。 要はミクロな領域では粒子の位置と運動量は正確には決められず、
という「不確定性関係」が成り立つ、というものだ。 一方の測定誤差を極めて小さくすれば他方の誤差が極めて増すことになり、結局誤差の積を一定以下には下げることが出来ない。 そこにプランク定数が関係している。 ・・・という内容である。 これがさっぱり分からない。
いや、理屈が分からないのではない。 私の疑問は普通とはちょっと違って、おおよそ次のようなものだ。
果たしてそんなに有難がるほどの概念だろうか。 歴史上、どんな文脈で出てきたのか。 量子力学にとってどれほどの意味を持つのか。
偉そうな疑問だ。 まぁ一緒に疑ってみようじゃないか。 そして不確定性原理が「要る」のか「要らない」のかはっきりさせてやろう。 めちゃめちゃ態度でかい気がするが。
本当に原理か?
「原理」というだけあって、この概念を基にして量子力学の体系が作られているのだろうかと考えてみたが、これだけでは当然無理だ。 波長と運動量、周波数とエネルギーの関係も導き出せないし、波動関数やシュレーディンガー方程式が出てくるわけでもない。
むしろ逆であって、不確定性関係は量子力学の体系から自然に導かれるものであるようだ。 ちょっとやってみようか。
と言ってもいきなりやるのは不親切だ。 まず「交換関係」について確認し、次に「誤差の意味」について考え、最後にそれらを使って式変形を行う、という3段階に分けて説明するとしよう。
交換関係
量子力学では物理量は演算子で表される。 すると、物理量を掛け合わせる時にどちらが先に来るかによって結果が違ってしまう組み合わせがありうる。 座標と運動量が典型的な例である。 先に座標を掛けてしまうと、運動量には座標微分が含まれているから、これは座標と波動関数の両方に演算しなければならなくなる。
一方、その逆の場合にはそんな心配はない。 つまり、計算する時に勝手に掛ける順番を交換してはいけないことになる。 これを「非可換である」と言う。 二つの演算子が交換できるかどうかは、実際に交換してみて両者の差を取ってやったものを計算しておけばよく分かる。 もし0になるならばどちらを先に掛けようが差はないわけで、交換可能だというわけだ。 座標と運動量についての「交換関係」がどうなっているか計算してみよう。
ψ は計算に誤解がないように書いておいただけのもので、省略してやることが多い。
この関係を「交換子」と呼ばれる記号を使って、
とシンプルに表現することもよく行われる。 他にもエネルギーと時間について、
という関係も成り立っている。 他の物理量、例えば角運動量などについても同様の関係があるが、それらについてはまだ定義さえ説明していないので出てきたときについでに話すことにしよう。 とりあえずはこれくらい知っていれば十分だ。
ここで計算した交換関係と不確定性原理との間には深い関わりがあるのだが、それはこの後の式変形を見れば理解できるようになる。 途中でこの関係を当てはめて導くことになるのだから。 その前に量子力学でいう「測定誤差」とは何なのかを確認しておかないといけない。
誤差の意味
標準偏差という言葉を知っているだろうか。 テストの採点結果が全体的にどれだけばらついているかを数値化したい時などに使うものだ。 まぁ普通は起こり得ない
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
不確定性原理
歴史を振り返らないと見えないものがある。
私の疑問
「不確定性原理」という言葉を聞いたことがあると思う。 解説はそこら中にあふれている。 要はミクロな領域では粒子の位置と運動量は正確には決められず、
という「不確定性関係」が成り立つ、というものだ。 一方の測定誤差を極めて小さくすれば他方の誤差が極めて増すことになり、結局誤差の積を一定以下には下げることが出来ない。 そこにプランク定数が関係している。 ・・・という内容である。 これがさっぱり分からない。
いや、理屈が分からないのではない。 私の疑問は普通とはちょっと違って、おおよそ次のようなものだ。
果たしてそんなに有難がるほどの概念だろうか。 歴史上、どんな文脈で出てきたのか。 量子力学にとってどれほどの意味を持つのか。
偉そうな疑問だ。 まぁ一緒に疑ってみようじゃないか。 そして不確定性原理が「要る」のか「要らない」のかはっきりさせてやろう。 めちゃめちゃ態度でかい気がするが。
本当に原理か?
「原理」というだけあって、この概念を基にして量子力学の体系が作られているのだろうかと考えてみたが、これだけでは当然無理だ。 波長と運動量、周波数とエネルギーの関係も導き出せないし、波動関数やシュレーディンガー方程式が出てくるわけでもない。
むしろ逆であって、不確定性関係は量子力学の体系から自然に導かれるものであるようだ。 ちょっとやってみようか。
と言ってもいきなりやるのは不親切だ。 まず「交換関係」について確認し、次に「誤差の意味」について考え、最後にそれらを使って式変形を行う、という3段階に分けて説明するとしよう。
交換関係
量子力学では物理量は演算子で表される。 すると、物理量を掛け合わせる時にどちらが先に来るかによって結果が違ってしまう組み合わせがありうる。 座標と運動量が典型的な例である。 先に座標を掛けてしまうと、運動量には座標微分が含まれているから、これは座標と波動関数の両方に演算しなければならなくなる。
一方、その逆の場合にはそんな心配はない。 つまり、計算する時に勝手に掛ける順番を交換してはいけないことになる。 これを「非可換である」と言う。 二つの演算子が交換できるかどうかは、実際に交換してみて両者の差を取ってやったものを計算しておけばよく分かる。 もし0になるならばどちらを先に掛けようが差はないわけで、交換可能だというわけだ。 座標と運動量についての「交換関係」がどうなっているか計算してみよう。
ψ は計算に誤解がないように書いておいただけのもので、省略してやることが多い。
この関係を「交換子」と呼ばれる記号を使って、
とシンプルに表現することもよく行われる。 他にもエネルギーと時間について、
という関係も成り立っている。 他の物理量、例えば角運動量などについても同様の関係があるが、それらについてはまだ定義さえ説明していないので出てきたときについでに話すことにしよう。 とりあえずはこれくらい知っていれば十分だ。
ここで計算した交換関係と不確定性原理との間には深い関わりがあるのだが、それはこの後の式変形を見れば理解できるようになる。 途中でこの関係を当てはめて導くことになるのだから。 その前に量子力学でいう「測定誤差」とは何なのかを確認しておかないといけない。
誤差の意味
標準偏差という言葉を知っているだろうか。 テストの採点結果が全体的にどれだけばらついているかを数値化したい時などに使うものだ。 まぁ普通は起こり得ないことではあるが、テストを受けた全員が全員、平均値と全く同じ点数であった場合には標準偏差は0だということになる。 どういう計算をすればそういう意味の値が導けるだろう?
まず各人の点数と平均点との差を取る。 それを全員分合計してやればそれらしい意味になりそうだが、そのままではプラスとマイナスが入り混じって結局0になってしまって意味がない。 それを防ぐために2乗してから合計するのである。 なぜ2乗するのだろう? 代わりに絶対値を取るのではだめなのだろうか? まぁそれでもバラツキを表すという目的は果たせるのだが、2乗しておいた方が扱いやすく、統計上面白い応用があるなどと言った利点があるので良く使うだけの話である。
さて、ばらつきを合計しただけでは受験人数が多くなればなるほど数字が大きくなってしまうので人数で割ってやる。 そうして出来た値を「分散」と呼ぶ。 このままでもばらつきを表す数字になっているのだが、前に2乗した分が気持ち悪いので平方根を取って次元を合わせてやったものが「標準偏差」だというわけである。
余談だが、大学受験などでよく使われる「偏差値」というのは、自分の点数が平均値と全く同じなら50、そこから「標準偏差」と同じだけ上にずれると60、標準偏差の2倍ずれると70などとなるように(割と人為的な定義で)計算したものだ。 例え平均点よりメチャクチャ高い点数を取ったとしても、全体の点数が広い範囲にばらついていればそんなに珍しい成績でもないだろう、という判断ができるわけだ。
量子力学における「測定誤差」はこの標準偏差と同じ意味である。 ただし平均値からの差ではなく、期待値からの差を考えることになる。 つまり、ある物理量を測定した時に、どうしても確率的にばらついてしまうわけだが、 その測定値が期待値の周辺に集中して見出される傾向があるのか、それとも広い範囲に散らばって見出される可能性の方が高いのか、 ということを表す数字なのである。 よってよくある勘違いだが、不確定性関係に出てくる「測定誤差が Δp である」という表現は、実測値が期待値から ±Δp だけずれた範囲内に必ず収まると言う意味ではない。 確率は低いがその範囲からひどく外れた値になることだって十分あり得るのだ。
このばらつきは測定機器の精度や外来ノイズによるものではなくて、量子力学の確率の問題でどうしても生じてしまうものだということに注意しよう。 多くの人は、この「原理的なばらつき」の原因が、測定することによる対象への撹乱によるものだと信じ切っているようである。 そういう人には意外かも知れないが、ここで言っているのは、測定するために何かをぶつけなくてはいけないから結果が不正確になるということではない。 入門書の中にはそういう説明をしているものの方が遥かに多いが、それについては後で話すことにしよう。
今は取り敢えず先へ進む。 量子力学における「誤差」を実際に式でどう表せるのかを計算してみよう。 まず、測定値の期待値からの差を計算し、2乗する。
先ほどのテストの点数の例ではこの値を合計して人数で割ったが、同様の意味のことを行うには、どの測定値がどの程度の割合で現れるかという「確率の重み」を考慮に入れて積分することになる。 つまり、
のように計算する。 期待値 <p> はすでに実数として求められているので積分の外に出してやって構わないから、
ということになる。 つまり、物理量 p の誤差 Δp は、
のように定義してやることができるのだ。
不確定性原理の導出
ようやく準備が整った。 これで不確定性原理を数学的に導くことが出来る・・・と思ったが、よくよく調べてみると考えていた以上に高度な式変形が要求されるようだ。 教科書によっては非常に簡単に見えるやり方を紹介しているものがあるが、その方法にはどうにも不自然な仮定が持ち込まれているようで納得が行かない。 私としては少々複雑でも不明な点を何も残さないやり方の方がいいと思うのだ。
複雑とは言っても、第2部で出てくる「複素関数の内積」の概念や、「エルミート演算子」の概念を使えば何とかなる程度ではある。 しかし仕方ない。 話の流れを邪魔しないために、詳細は補習コーナーで説明することにして、ここでは結果だけを書いておこう。
「シュワルツの不等式」などの数学的な定理を援用して、このような関係が導かれることになる。 この式が厳密な意味での不確定性原理の式である。
この式の右辺には前に書いた「交換関係」の式が含まれている。 A と B の代わりに x と p を代入してやれば初めに書いた不確定性原理の式になるわけだ。 このことから、交換できない2つの物理量の間には必ず「不確定性関係」が成り立つということが言えるのである。
鋭い指摘
こうなると不確定性原理というやつは、単なる量子力学の「注意書き」くらいの存在に思える。 これは量子力学の体系から導かれた概念であって、その逆ではないからだ。 実際にこの原理が指摘されたのは、現在の量子力学の入門書に載っているほとんどの事柄が議論されてしまった後のことであり、現在の教科書の順とは違って初めから問題になった事ではないし、量子力学の建設の基礎になっていたわけでもない。
しかし、この辺りの量子力学の発展の歴史は(ほんの1、2年の間の出来事ではあるが)なかなか複雑である。 ハイゼンベルクは急激な発展を続ける量子力学について、その基礎となるものがあまり議論されていないことに憂いを感じ、土台をどこに置くべきか、量子力学をどこに着地させるべきかを考えていた。
彼は元々、波動関数などという本当にあるかどうか分からないものに基礎を置くことを嫌い、測定して得られる結果だけに信頼を寄せ、その関係のみに注目した理論である「行列力学」をシュレーディンガーよりも前に作り出して量子力学の基礎を築いた経緯のある人物である。
こういう話を聞くと、彼が堅物の老人...