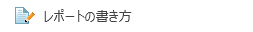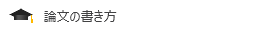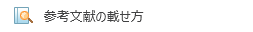All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
サービスを科学する
日本の自動車産業が、製造工程を「科学する」ことにより、今日の地位を築いたことはよく知られている。基本は不良品ゼロ、歩留まり向上を目指すための品質管理活動。品質管理(QC)活動を通じて社員達は、ヒストグラムや、パレート図、特性要因図、散布図など「QC七つ道具」と言われる、科学的な分析手法を身につけることになる。更にQC活動のサークルリーダー達は、たとえば歩留まり向上のためのQC活動が製造原価にどう影響を与えるかの講習も受け、幹部候補生として育っていく。製造工程を科学したことが、トヨタがGMを追い抜いた背景にはある。
ならばサービス工程を科学してはどうか。生産性が低いと、かねて揶揄されているサービス産業であってみれば、サービスを科学しない手はない。
数年前からIBMは、「SSME(サービスサイエンス、マネジメント・アンド・エンジニアリング)University」を展開。最近、それに触発されたオムロンフィールドエンジニアリング社の諏訪良武氏が、これまでの実践をベースにした研究成果をまとめた、『顧客はサービスを買っている』を上梓した。見所は、サービス行為を産業分類ではなく、21の「サービスメニュー」に分類した分析ツール。そして「事前期待」の概念を導入、製造業との違いを明らかにした点にある。
「サービスメニュー」
ホンダの戦略車である、エコカー「INSIGHT」には、エコアシスト(エコロジカル・ドライブ・アシスト・システム)が搭載されていて、そのコーチング機能、ティーチング機能が「売り」。具体的には、走行中のドライブ状況を視覚化し低燃費運転に誘導したり、運転後にエコ度を採点して教えてくれる。これは「サービスメニュー」番号<情報提供サービス1.> に該当する。
つまり、産業分類ではなく、サービス行為の分類作業を通して、実は製造業も「サービス」を売っていること、製造業も「サービス」が競争の命運を分けるようになってきていることに気付かされる。実際、「サービスメニュー」番号<モノ提供サービス1.>の定義は「ユーザーに作ったモノを提供する」とあり、製造業も「サービス」行為のひとつの種類と分類されている。上梓された本のタイトル『顧客はサービスを買っている』の由来はここにある。
アマゾンの成功は、協調フィルタリング技術をベースにした「この商品を買った人はこんな商品も買っています」や、「カスタマーレビュー」のレコメンデーション機能にあると言われている。確かに、本を購入する人の77.0%が、ネット書店の「レビュー」を参考にしているとの調査もある 。これも「サービスメニュー」番号<情報提供サービス1.>だ。
また2000年初頭危機に瀕していたP&Gは、生活者参加型の口コミサイトの運営で、新しい成長を手に入れた。それは従来型の、企業が予め作った仮設に基づいて顧客を「利用」するサンプリング手法などとは本質的に異る発想の仕組みだった 。顧客同士が双方向でコミュニケーションでき、「サービスメニュー」番号<情報提供サービス2.(知りたいことを教える)>、<情報提供サービス3.(いろいろなことを相談する)>、さらに<快適提供サービス1.(安心安全を提供)>を実践したと考えられる。
このように自社の事業内容を、どのサービスメニューを実践しているのか、棚卸ししてみるのは有益だろう。また競争力を高めるにはどのサービスメニューを加えるべきかを考察するのにも便利なツールだ。たとえば同じホテル業でも、形態に応じサービスメニューは異なることがこのツールでわかる(下記表参照)。
「事前期待」
さてゲーム市場では、08年激震が走った 。100億円を超える開発費のクライムアクション型ゲームの「グランドセフトオート4」が、開発費10億円以下の「Wii」のソフトに負けた。クライムアクション型とは主人公となる人物を操作し、殺人・強盗などの犯罪行為が行えるゲームで、最近は「操作性」に向けた競争が激化、たとえば主人公が保有するケータイの着信音を変更できるまでの、ディテールに凝った作りこみが行われていた。ところが「これまで男の子のものという色彩の強かったゲームを家族のコミュニケーションのツールに高めた 」「WiiFit」に、販売本数で及ばなかった。
この現象はサービスサイエンスの観点からは、「事前期待」のコントロールの失敗事例と整理されそうだ。サービスの満足度はサービスの絶対レベルより、期待値との相対関係に左右される。アカデミー賞のアニメ「つみきのいえ 」は、受賞の前に観た人と、後に見た人とで満足度が違う可能性がある。「あれはすごい」という前評判を散々聞かされた人は、「事前期待」のレベルが上がり、実はいい映画なのに、「悪くはなかったけど」という感想になるのかもしれない。
「グランドセフトオート」も改訂を重ねるたびに、またネット上での口コミで、期待値はあがり続けていたに違いない。サービスでは、「事前期待」のマネジメントが重要である。
「無料で遊べるメールポータルサイト」ニワンゴの杉本誠司社長は、「ユーザーはデザインや音楽に対価を支払っているのではなく、コミュニケーションの手段に対価を支払っている」、そこでは「客観的でなく主観的に消費行動が行われるから、そこを演出することが重要である」と述べているが、同じような話だ 。
技術的に可能なことを無限に追求していくより、「事前期待」に答えることこそが重要で、それは、価格コム安田幹広氏の経験とも平仄があう。氏は「収益ポイントを見いだすには、枯れた技術をチューニングするだけでも十分かも知れない」と話している。 さあ、サービスを科学しよう。
2
情報社会生活マンスリーレポート 09年03月号
【今月の参考クリップ】
1.
・サービスサイエンスによる企業変革の実践
http://www.supply-chain.gr.jp/download/scm_seminar/2008/20080926/080926_SCMSeminarinOsaka_Suwa.pdf
サービス行為を産業分類ではなく、21の「サービスメニュー」に
分類。その「メニュー」を既往の「産業」に割当てる発想が斬新。(by 神宮司信也)
2.
・ネット書店購入者の約8割がレビューを参考に インターワイヤード調査
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090203/129303/
本の購入場所(複数回答)は、「書店」が82.2%、「インターネッ
ト書店」42.9%。「月に10冊以上」も「全く読まない」も若い人。(by 神宮司信也)
3.
・生活者参加型マーケティングでV字回復した P&G
http://japan.internet.com/wmnews/20090216/8.html
P&G の知的財産を外部の技術やアイデアにつなげ(コネクト)、
製品を開発する(デベロップ)、オープンモデルを構築。(by 神宮司信也)
4.
・欧米市場を襲った「Wii」旋風 GDCを読む(3)
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITew000013022009&cp=2
高度な技術があっても収益を生み出せることにはならないと、世界
が知った08年。それはコスト構造変革の09年へと続くはず。(by 神宮司信也)
5.
・2008年 文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 優秀賞 Wii Fit
http://plaza.bunka.go.jp/festival/2008/entertainment/001034/
「これまで男の子のものという色彩の強かったゲームを家族のコミュ
ニケーションのツールに高めた」。ゲームの未来を垣間見る、と。(by 神宮司信也)
6.
・2008年 文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門 大賞 つみきのいえ
http://plaza.bunka.go.jp/festival/2008/animation/001039/
ハリウッドでアカデミー賞(短編アニメ部門)をとった「つみきの
いえ」は、国内では文化庁メディア芸術祭でも受賞。(by 神宮司信也)
7.
・mixi、価格com、ニコニコ動画らに学ぶ、ネットサービスの収益化
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20387983,00.htm
「『楽しさ』×『便利』=『集まる』コミュニティサービスの今後
について。『コンテンツの一般化』と『収益モデル』に向けて」。(by 神宮司信也)
【参考情報】
・『顧客はサービスを買っている』 著者:諏訪良武 ダイヤモンド社(2009年1月)
・Honda | クルマ | インサイト | エコアシスト
http://www.honda.co.jp/INSIGHT/assist-system/index.html
・GTAIV Street [グランド・セフト・オート4 情報サイト]
http://gta4.blog46.fc2.com/
Column
顧客は、サービスを買っている
神宮司信也