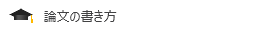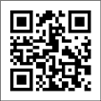資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
目的
変形しない、断面積が一定の、滑らかな円管内の水の流れを取り上げ、内部流れの性質について理解する。
理論
直径が変化しない、まっすぐで十分細長い円環の内部の流れは、入り口付近や出口付近のわずがな部分を除けば管軸方向のどのx位置でも管軸に直角な断面内の流速分布は同じで、u=u(r)となる。また、管内壁での摩擦のために圧力は下流に向かって降下するが、その勾配dp/dxも管軸方向に一定となる。このような特徴を持った流れを「十分発達した円管流」と呼ぶ。一方、入り口付近では境界層が形成され、断面の流速分布は壁面付近の境界線と中央部の一様流の部分からなる。このような上流部分では境界層の発達と共に流れは下流方向に徐々に変化し、u=u(r,x)となる。管軸方向への圧力勾配も一定にならない。この領域を助走領域という。助走区間の長さLeは、
で見積もることができる。ここで、Reは円管流の場合のレイノルズ数、
Dは管の内径、Vは断面平均流速で、Qを体積流量とすると、
の関係がある。
水平な十分発達した円管流では、慣性力も重力も働かないから、両端の圧力差と管壁での摩擦力の釣り合いで運動が決まる。すなわち、
ここで、Δpは管両端の圧力差、τWは壁面せん断応力、Lは管の長さ、dは管の内径である。一方、壁面せん断応力τWは、運動エネルギーρV2/2に比例することが知られていることから、式(5)は、
と書くことが出来る。ここで、fは無次元の比例定数で管摩擦係数と呼ばれる。
管摩擦係数の値は、レイノルズ数Reと管内面の相対粗さε/dによって変わる。円管の管摩擦係数は層流の場合には管内面の粗さには無関係になり、
となることが理論的に導かれる。この関係はほぼRe<2300で成立すると言われている。一方、乱流の場合には管内面の粗さにも依存するが、滑らかな円管の場合には経験式、
によって表される。管摩擦係数fをレイノルズ数と管内面の粗さを広範囲に変えて測定した結果をまとめたものはMoody線図と呼ばれる。
十分発達した円管流の流速分布は、層流の場合は理論的に、
で与えられる放物線となり、最大流速は管中心軸上(r=0)で、
これらより、
となる。このような流れのことを円管ポアズイユ流と呼ぶ。
一方、乱流の場合には半経験式、
が成り立つ。ここで、u*は摩擦速度で、
により定義され、式(5)(6)から、
により求めることが出来る。
実験方法
実験1「管摩擦係数の測定」
・試料と測定機器など
作動流体:水道水
試料:内径の異なる十分滑らかな円管
使用機器など:
圧力差Δp(mmHg) 半導体圧力変換器(Validyne DP15-34)
体積流量Q(liter/min) 電磁流量計(SIKA VTH15K5-40)
管内径d(mm) ノギス
水温T(℃) アルコール温度計
・方法
備え付けのマニュアルに従って、各管ごとに流量を10回変え、体積流量Qと圧力差Δpを記録した。
実験2「断面流速分布の測定」
・試料、測定機器など
作動流体:水道水
試料:内径50mmの透明アクリル円管
使用機器など:
流速:レーザードップラー流速計(カノマックス DSP8007, He-Ne 14.5mW)
その他は実験1と共通
・方法
備え付けのマニュアルに従って、測定位置を直径上で20点程度変えながら、各半径位置での時間平均流速と乱れ強さを記録した。同時に電磁流量計が指示する体積流量を記録した。
実験結果
実験1「管摩擦係数の測定」
測定結果から横軸に体積流量Q、縦軸に圧力差Δpを取り、管内径dをパラメータとしてプロットすると、図1のようになった。
流量をレイノルズ数Reの形に、また圧力差を管摩擦係数fの形に無次元化し、付図2に管内径をパラメータとしてプロットした。なお、計算にあたり実験室の温度T=20℃より、水の密度ρw=998.41kg/m3とした。
実験2「断面流速分布の測定」
得られた各半径位置での流速を無次元化して図2に示した。
流量、温度の測定結果よりレイノルズ数はRe=10238と定まった。
考察
実験1「管摩擦係数の測定」
図1より、管の内径が大きくなるほど曲線の勾配はより緩やかになっていることがわかる。また、どのグラフも勾配は単調増加をしている。つまり、管の内径が実験範囲以上に大きく変化した場合も、このグラフだけを使って圧力差はある程度推定できる。しかし、流体の種類や管の長さが変わった場合は、それを要因にする圧力差を推定できるものが見つからないので、このグラフだけからは推定できない。
付図2を見ると、3本の曲線は非常に近接している。
より、管内径dは管摩擦係数fの値には関係しない。よってこの曲線は1本にまとまるはずであるが、勾配の様子から完全には一致しておらず、Moody線図上のどの他の曲線とも一致しているとはいえない。ただ、勾配の符号は各曲線と一致しているので、今回のデータは完全に悪い質のものであるとはいえないだろう。
実験2「断面流速分布の測定」
式(8)よりこの円管の管摩擦係数はf=0.031415と見積もれる。よって式(14)より、u*=0.012916 m/s。これを用いて式(12)から得られたuを乱流の場合の流速分布の理論値とし、今回の測定結果とともに図3に示した。また、乱れ強さの分布もプロットし図4に示した。図3より、実験値と理論値のグラフは他方を縦軸に平行移動したものと見れる。また、図4より乱れ強さ、つまり流速の偏差の変動係数は4%以上あることがわかる。一般的に、変動係数が1%以上あるというのは、分布のばらつきが大きいということである。よってこれは乱流といえる。
6.参考文献
F.M.White, Fluid Mechanics, 5th Edition, McGraw-Hill, 2003