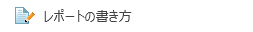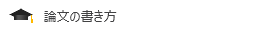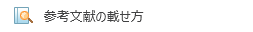資料紹介
- -1
現在の司法修習制度について
第1 司法修習制度の概要
○ 司法修習では,司法試験合格者である司法修習生に対し,法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識,技能のほか,法曹倫理などを養成
するため,実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は,1年6か月間行われ,導入教育である「前期集合修習」
(司法研修所で実施・3か月),実践的教育である「実務修習」(全国の
修習地で実施・1年),仕上げ教育である「後期集合修習」(司法研修所
で実施・3か月)から構成されている。最後に最終試験(司法修習生考
試)が行われ,これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在,司法修習生の年間養成数は,約1000人である。
1 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは,一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では,法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識,法的思考力,法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており,実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は,司法官(裁判官,検察官)と弁護士とは別々に養成されていたが,
戦後,司法研修所が発足し,統一的で体系的な法曹養成教育を実施すること
になり,我が国の法曹の水準の向上,法曹相互の理解に基づく適正・迅速な
裁判の実現に寄与してきた。
2 司法修習の概要(資料1参照)
(1) 司法修習の期間は,従前は2年間であったが,平成11年からは1年6か
月に短縮された。
(2) 修習の中心は臨床的な実務修習であるが,これをより効果的なものにする
- -2
ため,司法研修所で前期・後期の集合修習が行われる。研修所での教育体制
は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の5科目を中心として
構成され,司法修習生約1000人に対し,各教科14人合計70人の教官
が指導に当たる。司法研修所における集合修習でも実務を重視し,教室での
授業においてビデオ教材を活用したり,講義以外にも各種のロールプレイ,
法廷教室を利用した模擬裁判なども行われている。(資料2参照)
(3) 実務修習では,全国各地の弁護士事務所,検察庁,裁判所において,指導
官(現役の弁護士,検察官,裁判官)による個別的な指導を受けながら,実
際の事件について種々の実践的,体験的学習を行うもので,一種の臨床教育
である。(資料3参照)
(4) 司法修習生の養成数は,昭和39年ころから長らく年間約500人程度で
推移していたが,平成4年から増加し,平成11年から約800人,平成1
2年からは約1000人となっている。(資料4参照)
(5) 司法修習の最後に実施される最終試験(司法修習生考試)は,司法試験の
次の試験という意味で,「二回試験」と呼ばれており,これに合格すること
により法曹資格が与えられる。
第2 司法修習の具体的内容
○ 構成
司法修習は,毎年4月に開始し,前期集合修習(3か月),実務修習
(1年),後期集合修習(3か月)の順序で行われ,司法修習生考試を経
て,翌年の10月初めに終了する。
○ 集合修習
・集合修習は,司法研修所に全司法修習生を集めて実施し,1クラス約7
0人のクラス制を採り,民事弁護,刑事弁護,検察,民事裁判,刑事裁判
の基本5科目を中心として,それぞれの立場からの法律実務の指導を,起
案(事件記録教材に基づく基本的な法律文書の作成)の添削と講評を中心
として,各種演習,講義等により行っている。
・最初の3
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
- -1
現在の司法修習制度について
第1 司法修習制度の概要
○ 司法修習では,司法試験合格者である司法修習生に対し,法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識,技能のほか,法曹倫理などを養成
するため,実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は,1年6か月間行われ,導入教育である「前期集合修習」
(司法研修所で実施・3か月),実践的教育である「実務修習」(全国の
修習地で実施・1年),仕上げ教育である「後期集合修習」(司法研修所
で実施・3か月)から構成されている。最後に最終試験(司法修習生考
試)が行われ,これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在,司法修習生の年間養成数は,約1000人である。
1 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは,一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では,法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識,法的思考力,法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており,実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は,司法官(裁判官,検察官)と弁護士とは別々に養成されていたが,
戦後,司法研修所が発足し,統一的で体系的な法曹養成教育を実施すること
になり,我が国の法曹の水準の向上,法曹相互の理解に基づく適正・迅速な
裁判の実現に寄与してきた。
2 司法修習の概要(資料1参照)
(1) 司法修習の期間は,従前は2年間であったが,平成11年からは1年6か
月に短縮された。
(2) 修習の中心は臨床的な実務修習であるが,これをより効果的なものにする
- -2
ため,司法研修所で前期・後期の集合修習が行われる。研修所での教育体制
は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の5科目を中心として
構成され,司法修習生約1000人に対し,各教科14人合計70人の教官
が指導に当たる。司法研修所における集合修習でも実務を重視し,教室での
授業においてビデオ教材を活用したり,講義以外にも各種のロールプレイ,
法廷教室を利用した模擬裁判なども行われている。(資料2参照)
(3) 実務修習では,全国各地の弁護士事務所,検察庁,裁判所において,指導
官(現役の弁護士,検察官,裁判官)による個別的な指導を受けながら,実
際の事件について種々の実践的,体験的学習を行うもので,一種の臨床教育
である。(資料3参照)
(4) 司法修習生の養成数は,昭和39年ころから長らく年間約500人程度で
推移していたが,平成4年から増加し,平成11年から約800人,平成1
2年からは約1000人となっている。(資料4参照)
(5) 司法修習の最後に実施される最終試験(司法修習生考試)は,司法試験の
次の試験という意味で,「二回試験」と呼ばれており,これに合格すること
により法曹資格が与えられる。
第2 司法修習の具体的内容
○ 構成
司法修習は,毎年4月に開始し,前期集合修習(3か月),実務修習
(1年),後期集合修習(3か月)の順序で行われ,司法修習生考試を経
て,翌年の10月初めに終了する。
○ 集合修習
・集合修習は,司法研修所に全司法修習生を集めて実施し,1クラス約7
0人のクラス制を採り,民事弁護,刑事弁護,検察,民事裁判,刑事裁判
の基本5科目を中心として,それぞれの立場からの法律実務の指導を,起
案(事件記録教材に基づく基本的な法律文書の作成)の添削と講評を中心
として,各種演習,講義等により行っている。
・最初の3か月に行う前期修習は,大学レベルでの理論的教育から実務に
- -3
おける実践的教育に移るための導入とも言うべきものであり,主に,事実
を法的に分析・構成するための法律実務についての基本的な知識,技能を
体系的に修得させることを目的としている。
・最後の3か月に行う後期修習では,修習の総仕上げとして,実務修習期
間中体験的に学んだ成果を踏まえて,理論的体系的に整理するとともに,
実務修習での体験内容のばらつきを補正し,実務に就くための確実な基盤
を確保することを目的としている。
○ 実務修習
・実務修習は修習の中核であり,司法修習生は,実際の事件処理の中で,
現役の弁護士,検察官,裁判官による個別的で実践的な指導を受け,この
過程を通じて実務的な知識と技能を修得するほか,法曹倫理,法曹として
の心構えを体得する。
・実務修習では,司法修習生は,全国50か所の実務修習地において,弁
護士会(3か月),検察庁(3か月),裁判所(民事裁判3か月,刑事裁
判3か月)に順次配属され,それぞれの立場に立って事実の法的分析・構
成,証拠の収集,検討,法廷活動の傍聴,準備書面や判決書の作成などを
実地に体験することにより,法曹として活動を始めるのに必要な法律実務
の知識,技能等を修得する。
○ 司法修習生考試(二回試験)
修習の最後に,民事弁護,刑事弁護,検察,民事裁判,刑事裁判,一般
教養の各科目について司法修習生考試が行われ,合格者は法曹資格を取得
する。
○ 司法修習生の身分
司法修習生は,国家公務員に準じた身分を有しており,国庫から,一定
額の給与と,各種手当が支給されている。司法修習生は,修習期間中,修
習専念義務,兼業・兼職の禁止,秘密保持義務などの義務を負っている。
1 集合修習について(資料2参照)
(1) 司法研修所における集合修習(前期・後期修習)では,修習生約1000
人を14クラスに分け(1クラスの人数は約70人),各クラスに5人(民
- -4
事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の各科目1人ずつ)の担当教
官を置くクラス担任制が採られている。実務経験が15年から30年程度の
経験豊かな現役の裁判官,検察官,弁護士が教官となっている。弁護教官及
び検察教官の任期は3年程度,裁判教官の任期は4年程度である。各科目と
も,カリキュラムの内容は,これまで数十年の蓄積をベースとし,教材や資
料等を始めとして,教授内容に至るまで各科目の全教官による徹底した合議
がなされるのが特徴である。
(2) 各科目とも,講義や問題研究などを行っているが,大きなウエイトを占め
ているのは,「起案」である。これは,実際の事件記録をもとに作成した記
録教材に基づいて,司法修習生に,判決,起訴状,準備書面,弁論要旨等の
基本的な法律文書を作成(起案)させるとともに,当該事件の事実認定上及
び法律上・手続上の問題点等についても論述させ,後日,教官が司法修習生
の起案を添削して返却し,教室で講評を行うというものである。記録教材は,
各教官室が全国各地に出掛けて,教材に適した事件記録を収集し,争点や事
実関係等を修習生のレベルに合わせるなど教材用に手直しした上,教官室で
合議を繰り返して作成している。そのため,1つの記録教材を作成するため
には,通常,半年ないし1年程度の期間を要している。(資料5参照)
(3) 現在の法学教育,受験教育等の状況を反映して,司法修習生の多くは,民
法,刑法などの実体法と,民事訴訟法,刑事訴訟法などの訴訟手続法との有
機的な関連を理解していないのが実情である。また,相対立する証拠から何
が真実であるかということを認定する能力も十分に身についていない。こう
した状況を踏まえ,研修所教育は大まかにいうと次の3つを主要な内容とし
ている。
① 法規の構造を解明した上,事実を法的に分析・構成する教育(民事科目
における要件事実教育)
② 証拠による事実認定教育
③ 訴訟運営,手続遂行に関する教育
(4) さらに,最近の傾向として,多様化する法的ニーズに応えるため,司法修
習生に基本的な知識を提供し,専門性を深める契機を与えるカリキュラムと
して,専門的法分野についての選択制講座を実施している。(資料6参照)
- -5
2 実務修習について(資料3参照)
(1) 実務修習中は,司法修習生は,各実務修習地の弁護士会,検察庁,裁判所
に配属され,現役の弁護士,検察官,裁判官の個別的な指導のもとに,現実
に生起している事件の処理を自ら体験する。また,この過程で,多くの法曹
から様々な経験や,法曹としての心構え等を学ぶ機会にも恵まれる。(資料
7参照)
(2) 弁護修習では,指導担当弁護士の事務所に配属され,その指導を受けなが
ら,当事者・被疑者・被告人との面接・事情聴取,訴状・準備書面・弁論要
旨・各種申立書の起案などを行う。また,指導担当弁護士が行う訴訟活動や
訴訟外の弁護士活動に立会うなどして,弁護士業務の実情を学んでいる。
(3) 検察修習では,担当検察官の指導・監督の下で,実際に,被疑者・参考人
の取調べ等の捜査を行い,起訴,不起訴の処分ついて意見を述べ,証拠の整
理,公判廷の傍聴,起訴状・冒頭陳述・論告等の起案などを行い,それらの
添削指導を受けて検察実務の基本とその実務の実情について学んでいる。
(4) 裁判修習では,法廷を傍聴するとともに,記録を検討し,裁判官との合議,
判決,決定等の起案などを行う。なお,裁判官の合議は非公開であるが,司
法修習生はこれを傍聴することができる(裁判所法75条1項)とされ,む
しろ,合議で自らの意見を述べることが求められている。裁判官は,判決等
の起案の添削のほか,適宜,事件内容・手続の解説や質疑応答をするなどし
て,裁判実務について指導している。
(5) 平成11年以降,実務修習中に,社会に対する広い視野と公共的精神とを
養うため,法が対象としている社会の実相に触れる...