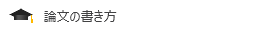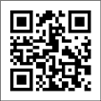資料紹介
局所直線座標系
一般相対論の思想に関わる話。
接続係数は0にできる
接続係数すなわちクリストッフェル記号は、テンソル量ではないが故に、少し特別な性質を持っている。 それは座標の取り方によって、ある地点での値を0にできるということだ。
しかしあらゆる地点での値を同時に0に出来るというのではない。 どんなにうまく座標系を選んでも、地面が曲がっている限り、その地点を少し離れると0ではなくなってしまう。 接続係数の微分までは0にできないということだ。
テンソル量の場合にはこのようなことはできない。 ある地点での値が0だったならば、それを別の座標系を使って表してみても0のままである。 逆に言えば0以外の値のものはどんな座標変換で表しても決して0には出来ないということになるだろう。
ある特別な座標系を選んだ時にだけ、一点での接続係数が0にできるというのはちっぽけなことに思えるが、それをわざわざ取り上げるのには理由がある。 このことを知っていると今後の式変形で非常に有利になるのだ。
例えば共変微分の定義には接続係数が含まれていて計算がかなり面倒くさい。 しかし座標の選び方によってはそれが0にできて、普通の微分として計算できることになる。 そしてもし計算した最終結果がテンソルになったなら、それは、その座標系に限らずあらゆる座標系でも同じことが成り立っていると結論できるわけだ。 そのような事例が後で出てくることになるだろう。
0に出来る保証はあるか
少し心配なのは、接続係数を0にするような座標系が、どんな場合であっても必ず見付かるかどうかということだ。 これを確かめておこう。
第3部の初めの記事「 共変微分 」の式番号 (8) で、次のような変換側を導いた。
説明の都合上、ダッシュの有る無しを反転させてある。 変換後の座標系にダッシュが付いていた方が見慣れているだろう? ある点 P での Γ tij を座標変換して Γ ' plm(P) = 0 となるようにしたい。 そのためには、
(1)
が成り立っていればいい。 この式はどこでも成り立っている必要はなくて、点 P において両辺の値が等しければいいだけである。 だから左辺は定数だと考えれば良いのであり、手が付けられないほど複雑な問題ではないようだ。
しかし左辺は定数とは言え多数の成分を持っており、単純に A とでも置いて簡略化するわけにはいかない。 まぁ、微分したら0になるということだけは言える。 まずは当たりを付ける為、次のような単純な座標変換を考えてみよう。
これを (1) 式の右辺の2階微分に代入すれば、定数 Γ tij(P) が残ってくれるだろう。 しかしもう一方の1階微分のところに代入した時が厄介だ。 x' を x で偏微分して逆数を取ってやれば計算は出来るが、余計な項が残り過ぎる。 そこで少し改良してやろう。
ci というのは P 点での座標値である。 計算した後で xi に ci を代入するので、こうしておけば残った項もすっきりと消えてしまうだろう。 いや消え過ぎだ。 0では困るのでさらに細工。
これでとりあえずは解決。 x'i と xi はこれに加えて定数分だけずれていても大丈夫なので、それを形式美にこだわって表現するなら次のようになる。 それと実際に計算してみると (1/2) が必要である事が分かるから今の内に入れておく。
(2)
この変換で全てがうまく行くはずだ。 まぁ初めからいきなりこれを示して確認に入っても良かったの
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
局所直線座標系
一般相対論の思想に関わる話。
接続係数は0にできる
接続係数すなわちクリストッフェル記号は、テンソル量ではないが故に、少し特別な性質を持っている。 それは座標の取り方によって、ある地点での値を0にできるということだ。
しかしあらゆる地点での値を同時に0に出来るというのではない。 どんなにうまく座標系を選んでも、地面が曲がっている限り、その地点を少し離れると0ではなくなってしまう。 接続係数の微分までは0にできないということだ。
テンソル量の場合にはこのようなことはできない。 ある地点での値が0だったならば、それを別の座標系を使って表してみても0のままである。 逆に言えば0以外の値のものはどんな座標変換で表しても決して0には出来ないということになるだろう。
ある特別な座標系を選んだ時にだけ、一点での接続係数が0にできるというのはちっぽけなことに思えるが、それをわざわざ取り上げるのには理由がある。 このことを知っていると今後の式変形で非常に有利になるのだ。
例えば共変微分の定義には接続係数が含まれていて計算がかなり面倒くさい。 しかし座標の選び方によってはそれが0にできて、普通の微分として計算できることになる。 そしてもし計算した最終結果がテンソルになったなら、それは、その座標系に限らずあらゆる座標系でも同じことが成り立っていると結論できるわけだ。 そのような事例が後で出てくることになるだろう。
0に出来る保証はあるか
少し心配なのは、接続係数を0にするような座標系が、どんな場合であっても必ず見付かるかどうかということだ。 これを確かめておこう。
第3部の初めの記事「 共変微分 」の式番号 (8) で、次のような変換側を導いた。
説明の都合上、ダッシュの有る無しを反転させてある。 変換後の座標系にダッシュが付いていた方が見慣れているだろう? ある点 P での Γ tij を座標変換して Γ ' plm(P) = 0 となるようにしたい。 そのためには、
(1)
が成り立っていればいい。 この式はどこでも成り立っている必要はなくて、点 P において両辺の値が等しければいいだけである。 だから左辺は定数だと考えれば良いのであり、手が付けられないほど複雑な問題ではないようだ。
しかし左辺は定数とは言え多数の成分を持っており、単純に A とでも置いて簡略化するわけにはいかない。 まぁ、微分したら0になるということだけは言える。 まずは当たりを付ける為、次のような単純な座標変換を考えてみよう。
これを (1) 式の右辺の2階微分に代入すれば、定数 Γ tij(P) が残ってくれるだろう。 しかしもう一方の1階微分のところに代入した時が厄介だ。 x' を x で偏微分して逆数を取ってやれば計算は出来るが、余計な項が残り過ぎる。 そこで少し改良してやろう。
ci というのは P 点での座標値である。 計算した後で xi に ci を代入するので、こうしておけば残った項もすっきりと消えてしまうだろう。 いや消え過ぎだ。 0では困るのでさらに細工。
これでとりあえずは解決。 x'i と xi はこれに加えて定数分だけずれていても大丈夫なので、それを形式美にこだわって表現するなら次のようになる。 それと実際に計算してみると (1/2) が必要である事が分かるから今の内に入れておく。
(2)
この変換で全てがうまく行くはずだ。 まぁ初めからいきなりこれを示して確認に入っても良かったのだが、完全に天下りで話を進めるのはあまり好きでない。 まず、(2) 式の x' を x で1回微分すると、
であるから、これの逆数を取って xi に ci を代入したものは、
となる。 これが (1) 式の右辺の初めの1階微分に相当する。 また2回微分すると、
となる。 これが (1) 式の右辺の2階微分である。 よって、
であるから、(2) 式の座標変換を採用することでいつでも (1) 式の条件を満たすと言えるのである。 このように接続係数を0にする変換は必ず在るということが分かって一安心だ。
しかもその変換は一通りではなく、無数に存在すると言える。 上のやり方で求まった座標系を線形変換した座標系でも条件に合うからである。
相対論のイメージ
今回の話を取り上げた理由は今後の式変形の為だけではない。 この、接続係数が0になる座標系が必ず見出せるという事実は、一般相対論の思想を実現するためにはとても重要な概念なのである。
ちょうど測地線の話をした直後でもあるし、ここでこのような話題を入れておくのはちょうどいいだろう。 測地線についての物理的考察をほとんどしなかったのも気がかりだった。
接続係数が至る所で0であるというのは直線座標の性質である。 平行移動によってベクトルやテンソルの値が変化しないということだ。
ところが今回の話では、たとえ地面が曲がっていたとしてもある一点に限っては接続係数を0にできるのだという。 つまり、その特別に選んだ座標系を使って表す限りは、その点のごく近くに関しては、平らな空間と同じ性質が成り立っていると見なせて、平らな空間と同じ法則が同じ形で記述できるのである。
それは例えばこういうことだ。 ビルの屋上で重力を感じている人がいる。 この人がビルから飛び降りれば重力を感じない世界を手に入れることができるだろう。 つまり自分のいる一点に限って言えば、空間が重力によって曲がっていないと錯覚できるのである。
さて、飛び降りずにビルの上で静かに見ている人にとっては、この飛び降りた人は加速度的に遠ざかって行くだろう。 それで、座標変換とはすなわち移動する事なのだろうか、という疑問が生まれる。
ここまで学んできたリーマン幾何学によれば、座標変換とは自分の位置を変えないままで、地面に描かれた座標軸だけを書き替えるという静的なイメージのものだった。 もし曲がった面上を移動すればその場その場での地面の曲がり具合だって刻々と変化するだろうから、面倒な問題が加わる事になるだろう。 実際に空間を移動する事がここまでリーマン幾何学で考えてきた座標変換と同じことに相当するとはとても思えない。
このイメージの乖離を解消するためには次元の違いに注意を払うことが必要である。 我々はここまで主に2次元の曲面のイメージに頼ってきた。 この曲面上を移動するというのは、この2次元とは別に時間という概念が存在して、その経過に従って位置を変えるということである。
ところが相対論ではその時間でさえも曲がった面の中にあるのである。 曲面そのものが4次元であって、その外には時間と呼べるものは存在しない状況である。 ではビルから飛び降りた人の振る舞いは4次元曲面上では何に相当するだろう? それは曲面上に描かれた線である。 決して移動する事の無い静かな一本の線である。 ではビルの上でじっとしていた人の振る舞いはどうだろうか。 これも線である。 点ではない。 横軸を時間、縦軸を移動距離で表した時の、横真一文字の直線が静止状態を表すのと同じ理屈だからだ。
このようにして曲面上に2種類の線が描かれた。 曲面上の座標軸の引き方によって、どちらの線が静止状態を表すかという解釈を変えて見ることが出来る。
ビルから飛び降りた人は、飛び降りる事で座標変換を無理やり実行したわけではない。 彼は飛び降りている自分の状態を静止状態と見なすような座標の取り方もあり得ることを実感したに過ぎない。 そしてその座標を使えば重力という余計なものの存在が消えて、現象がすっきりと表せる事を示したのである。 「飛び降り=座標変換」ではないということだ。
しかしまだどこか疑問がすっきりしない。 何だろうか。 飛び降りた人は終始重力を感じなかった。 すると飛び降りた人が描いた曲面上の軌跡の上では常に接続係数は0だということだろうか。 先ほど接続係数を0にできるのは1点のみだという話をしたが、この場合、接続係数を線に沿ってずっと0にすることの出来る座標系をうまく見出したことになるのだろうか。
そうではない。 この人の速度は常に変化している。 それだけでなくもし重力が変化すればこの人の加速度さえも変化する。 いつも同じように進んでいくのではないわけだ。 傍から見れば彼の描く曲面上の軌跡はくねくねと曲がっているように見えるだろう。 その彼が常に静止しているような見方をするためには、その場その場で座標軸の描き方を変えてやらないといけない。
彼自身はと言えば、常に接続係数が0であるような座標系で世界を見ている。 彼はそのような座標系に次々と乗り換えながら移動しているのである。 もし彼がある時点で使っていた座標の取り方で4次元世界全体を見ると、自分が描いた線上の別の点の接続係数は0でないように見えることに気が付くだろう。
彼はこうして、自分自身が等速直線運動をしているとみなせる座標系で等速直線運動を続けている。 曲面上を常に真っ直ぐ移動し続けた軌跡は「測地線」と呼ばれるのだった。 彼は空間の曲がりに従って、測地線を描いて移動していたことになる。 先ほど話した「傍から見てくねくねと曲がった線」は実は測地線だったわけだ。
さあ、これで相対論とリーマン幾何学との対応がイメージできるようになっただろうか。 数学を少しかじっただけでも、数式なしでここまで説明できるようになるものだな、と少し驚く。
資料提供先→ http://h...