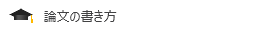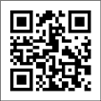資料紹介
ジェンダーフリーとバリアフリー
1.はじめに 近年、性別に関わる問題を論じるとき、「ジェンダーフリー」という言葉を耳にしないことがない。しかし、この言葉が、性別の問題を一挙に解決する、呪文のような使われ方がされることはあっても、その意味が掘り下げて考えられることはあまりないのでないだろうか。 「ジェンダーフリー」という言葉は、日本で考案された、いわゆる和製英語にあたる。現在この言葉は性別問題に関わる市民団体や官庁の部門により、頻繁に用いられるようである。
この文脈で「ジェンダーフリー」は、主に女性に対する差別をなくすために、少なくとも公的な諸制度について、性別に基づいた区別や差別を撤廃することを意味する。あるいはさらに踏み込んで、言語や服装といった文化的な部分に関する、性別に基づいた区別を撤廃し、性差のない文化を作ることを意味することもある。これらの場合、"free"とは「~がない」という意味であり、「ジェンダーフリー」とは、英訳するならば"state of no gender"(性別のない状態)とでもいうべきことになろう。 そして、この「性別のない状態」を作る出すことができるということは、いわゆる社会的性別(gender)に関する社会構築主義(social constructionism)に基づいていると考えられる。ここで社会構築主義とは、社会的意味での性別は、先天的に決定されている生物学的意味での性別(sex)とは異なり、それぞれの社会や文化において人為的に作り出されたものである、とする理解をいう。この立場からすると、教育や啓発活動を通じて、性別に二分された人々の意識を変え、性別を区別する文化や社会慣習そのものを変えていくことができることになる。 これに対して、本質主義(essentialism)、すなわち社会的性別についても生物学的性差によって決定されているという立場からは、およそ社会的に性別のない状態を作り出すことは不可能であり、社会的性別が男性/女性に二分されることは、時代や文化を問わず普遍的ということになる。 現在、少なくとも自然科学的な理解においては、本質主義的な理解が優勢になりつつある。すなわち、いわゆる脳の性分化説によれば、女性と男性では脳の特定の部分の構造に差異があり、そのことが知覚や意識、行動様式の差をもたらし、ひいては社会行動にも性別に基づく差異が現れる、というものである。 一方、人類学や社会学の領域では、社会的な性差が後天的な構築物であるという社会構築主義は、ほぼ当然の前提になっているようである。ポスト構造主義哲学のような相対主義思想の影響下に、性別の分類及び内容もまた文化により異なり、普遍的な「女性」「男性」概念は存在しないことが、暗黙の了解事項になっている。 私は、ここで本質主義/社会構築主義の優劣を論じようとは思わない。すなわちこの議論は、性差は人間の知覚の外に実在するか(実在論)、それとも人間が名付けただけの存在であるか(唯名論)という神学論争であり、決着のつかないものだからである。むしろ、問題にすべきなのは、ジェンダーの根拠についていかなる理解をするにせよ、果たしてどのような社会的条件を整えれば、個人が生きやすい社会を作ることができるか、ということである。すなわち、性別については依然、公的な場面でも私的な場面でも大きな関心が払われているが、その中で個人の自由を確保するにはどのようにすればよいか、ということである。 このように考えるとき、「ジェンダーフリー」とは「性差のない状態」を意味するのでな
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
ジェンダーフリーとバリアフリー
1.はじめに 近年、性別に関わる問題を論じるとき、「ジェンダーフリー」という言葉を耳にしないことがない。しかし、この言葉が、性別の問題を一挙に解決する、呪文のような使われ方がされることはあっても、その意味が掘り下げて考えられることはあまりないのでないだろうか。 「ジェンダーフリー」という言葉は、日本で考案された、いわゆる和製英語にあたる。現在この言葉は性別問題に関わる市民団体や官庁の部門により、頻繁に用いられるようである。
この文脈で「ジェンダーフリー」は、主に女性に対する差別をなくすために、少なくとも公的な諸制度について、性別に基づいた区別や差別を撤廃することを意味する。あるいはさらに踏み込んで、言語や服装といった文化的な部分に関する、性別に基づいた区別を撤廃し、性差のない文化を作ることを意味することもある。これらの場合、"free"とは「~がない」という意味であり、「ジェンダーフリー」とは、英訳するならば"state of no gender"(性別のない状態)とでもいうべきことになろう。 そして、この「性別のない状態」を作る出すことができるということは、いわゆる社会的性別(gender)に関する社会構築主義(social constructionism)に基づいていると考えられる。ここで社会構築主義とは、社会的意味での性別は、先天的に決定されている生物学的意味での性別(sex)とは異なり、それぞれの社会や文化において人為的に作り出されたものである、とする理解をいう。この立場からすると、教育や啓発活動を通じて、性別に二分された人々の意識を変え、性別を区別する文化や社会慣習そのものを変えていくことができることになる。 これに対して、本質主義(essentialism)、すなわち社会的性別についても生物学的性差によって決定されているという立場からは、およそ社会的に性別のない状態を作り出すことは不可能であり、社会的性別が男性/女性に二分されることは、時代や文化を問わず普遍的ということになる。 現在、少なくとも自然科学的な理解においては、本質主義的な理解が優勢になりつつある。すなわち、いわゆる脳の性分化説によれば、女性と男性では脳の特定の部分の構造に差異があり、そのことが知覚や意識、行動様式の差をもたらし、ひいては社会行動にも性別に基づく差異が現れる、というものである。 一方、人類学や社会学の領域では、社会的な性差が後天的な構築物であるという社会構築主義は、ほぼ当然の前提になっているようである。ポスト構造主義哲学のような相対主義思想の影響下に、性別の分類及び内容もまた文化により異なり、普遍的な「女性」「男性」概念は存在しないことが、暗黙の了解事項になっている。 私は、ここで本質主義/社会構築主義の優劣を論じようとは思わない。すなわちこの議論は、性差は人間の知覚の外に実在するか(実在論)、それとも人間が名付けただけの存在であるか(唯名論)という神学論争であり、決着のつかないものだからである。むしろ、問題にすべきなのは、ジェンダーの根拠についていかなる理解をするにせよ、果たしてどのような社会的条件を整えれば、個人が生きやすい社会を作ることができるか、ということである。すなわち、性別については依然、公的な場面でも私的な場面でも大きな関心が払われているが、その中で個人の自由を確保するにはどのようにすればよいか、ということである。 このように考えるとき、「ジェンダーフリー」とは「性差のない状態」を意味するのでなく、むしろ性差のいかんにかかわらず、行動の自由を保障する「性差に関するバリアフリー」として捉えられるべきと考える。 2.ジェンダーとは何か ジェンダーとは、既に社会的性別と訳したとおり、人が社会生活を営む上で認識される性別である。ジェンダーはさらに、個人が自らの性別をどう認識するかである性自認(gender identity)と、他者との関わりにおいてどういう性別に固有の役割を担うかである性役割(gender role)とに区分される。 例えば、服装や言葉遣いは性役割に属するものであり、今では少なくとも表向きには撤廃されつつあるとはいえ、家事や育児、事務は女性の、生産や営業は男性の役割と言ったいわゆる性別分業もこれにあたる。これに対し性自認は、自分が男性であると認識するか女性として認識するかのことである。もっとも、性役割についても性自認についても、女性か男性かを明瞭に区分できるわけでなく、相対的な区分である。 ジェンダーに関する社会構築主義は、この両者について、社会的文化的要因により形成されるとする。ジェンダーという用語はそもそも、フランス語やドイツ語などの言語において、名詞が男性型の冠詞をとるか女性型の冠詞をとるか、という点がもともとの意味であるが、社会構築主義は、社会的性別という意味でのジェンダーについても、言語に代表されるような文化的な所産であると考えるのである。 一方、近年の自然科学的理解は、少なくとも性自認に関して、遺伝的要因や脳の性分化により説明しようとしている。すなわち代表的な説によれば、出生前のある時期に、脳が性ホルモンの影響で形態的に変容を受け、その結果、性自認やある種の知覚や行動様式に性差があらわれる、というものである。 もっともこれらの説も、社会環境による影響を全く否定しているわけではない。とりわけ性役割については、自然科学的に見れば動物行動学的なアプローチが必要となるであろうが、これらが直接すべて、脳の性分化などの生物学的要因から説明されるのかどうかは、定かではない。
では、その学説的な当否はさておいて、これらの説の社会的な意味はどうであるか。言い換えれば、これらの説はいかなる政治的目的のために援用されうるか。 ジェンダーに関する社会構築主義をとる者の多くは、性差別に対して、差別のもととなる性差そのものをなくすか、少なくとも差別につながらないような形に作り替えることにより、差別をなくすことを意図している。すなわち社会構築主義には、性差別の解消という目的があって、そのために差別を惹き起こしている性差を可変的なものと考える、という政治的意図が内包されている。 そしてこの立場からは、本質主義は、性差ひいては差別を固定するものとして批判される。すなわち、ジェンダーが生物学的要素により決定されるなら、個々人が生物学的に定められたジェンダーに沿って生きるのは必然ということになり、固定的な性差に基づく差別が正当化されかねないとの懸念が向けられている。 一方、トランスセクシュアルのうちの一部の者には、脳の性分化のような生物学的要素を根拠に、外性器の性別と一致していない、自己の性自認や性役割の正当性を主張する者もいる。
このように、性差の根拠の問題が性差別の問題や個人の自由の問題を一義的に決定づけるという理解は、ジェンダーを論じる上で、暗黙の前提となっていて、とりたてて論じられるまでもないところとなっている。が、果たしてこの前提に疑うべきところはないのであろうか。言い換えれば、性差の根拠は、性差別の問題や個人の自由と論理必然的に関連するのであろうか。 この点、社会構築主義者と本質主義者は、方向こそ異なるものの、すでに形成されたジェンダーによって、個人の意思が直線的に決定されている、という理解である点には変わりない。言い換えれば、性自認だけでなく、性役割の個人的な選択に関しても、先天的であれ後天的であれ、予め決定されたジェンダーに従属していることが前提とされている。 しかし、ジェンダーが生物学的または社会的に決定されているか否かという問題と、それを前提に個人が社会的にどのような行動を選択するかという問題は、次元の異なる問題ではなかろうか。言い方を変えれば、ジェンダーに関して社会的に可変であるとしても、個人の選択の自由は論理必然的に保障されるとは限らない。一方、仮に脳の性分化説がいうように、少なくとも性自認が生物学的に決定されていると理解するとしても、むしろ重点が置かれるべきなのは個人の選択の自由である。 例えば、性自認に関して後天的に形成されるとの理解のもとに、幼少期の医療事故により男性器を失った者を、女性として養育したという事例が報告されている。この例では、性自認は後天的に形成される、との社会構築主義的理解のもとに、この場合は女性としての養育を徹底すれば、性別の同一性は確立される、という仮説に基づき、女性として育てることが試みられた。ところが、発育に連れて本人は深刻な性別違和に悩まされ、現在は男性として生活しているという(註)。この構築主義に基づいた仮説の破綻は、脳の性分化説の有力な証拠と考えられている。そして、延長線上には、客観的に判定されるべき脳の性別に従うことなく養育したのが誤りであった、とする決定論的理解も可能であろう。 しかし、この事例の問題点は、ジェンダーに関する自己決定の欠如である。すなわち、問題は本人が自ら意思決定を完全に行い得ない幼少期に、女性ジェンダーを生きることを強い、自らの選択に委ねなかった点にある。この考え方を延長すると、身体の性と心の性が一致しない性同一性障害の場合、医師の裁量で心の性を身体の性に合わせる治療が行われてもよいことになる。しかし、仮にそのような治療が行いうるとしても、あくまで本人の意思を尊重すべきことは、今日ではほぼ常識であろう。 次に、性役割について、性差をなくすという意味でのジェンダーフリーの理解のもとに、性別分業の廃止を徹底...